断熱性とは?指標・等級やメリット・デメリットも簡単に解説

「断熱性とはなんのこと?」
「断熱性が高い家をつくるポイントを知りたい」
家づくりを進めるなかで、上記のような疑問を感じる方は多いでしょう。
本記事では、断熱性の意味や断熱性が高い家をつくるポイントを解説します。断熱性が高い家のメリット・デメリットも紹介するので、参考にしてください。
この記事でわかること
- 断熱性の意味や指標
- 断熱性が高い家のメリット・デメリット
- 断熱性が高い家をつくるポイント
住宅性能や家づくりについて理解を深めたい方は、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」をご活用ください。
THINK HAUSでは、ヘーベルハウスの断熱性について詳しく解説したコンテンツをご用意しています。その他にも、家づくりの参考となる施工事例や住まいの動画を多数提供しています。無料で登録できるので、ぜひご利用ください。
断熱性とは

断熱性とは、熱の移動を抑える性能のことです。なお、断熱性の読み方は「だんねつせい」です。
熱は高温から低温に移動する性質をもち、家では天井・壁・床などを介して熱が出入りしています。断熱性の低い家は熱移動が激しく、冬場であれば室内の暖かい空気が室外へ移動して室内で寒さを感じやすいため、注意が必要です。
断熱性を高めることで熱の移動を遮断し、室温を一定にキープできます。断熱性の高さは住まいの快適性に直結しており、家づくりを進めるうえで重要な性能の一つです。
断熱性を表す指標

断熱性を表す指標は、以下のとおりです。
断熱性の基礎知識について、理解を深めましょう。
1. UA値(外皮平均熱貫流率)
UA(ユーエー)値とは外皮平均熱貫流率のことで、外皮から家全体の熱がどの程度逃げやすいかを示す数値です。UA値は、数値が小さいほど熱が逃げにくいことを表します。
なお、外皮とは住宅の外周部分を指し、具体的には以下の箇所です。
- 屋根
- 外壁
- 床
- 窓
- ドア
UA値の数値基準は気候条件に違いがあるため、全国を以下のように8つの地域に分割し、基準を定めています。
| 地域区分 | 主な地域 |
|---|---|
| 1 | 北海道 |
| 2 | |
| 3 | 青森県・岩手県・秋田県 |
| 4 | 宮城県・山形県・福島県・栃木県・新潟県・長野県 |
| 5 | 南関東・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州 |
| 6 | |
| 7 | 宮崎県・鹿児島県 |
| 8 | 沖縄県 |
同じ都道府県でも地域区分が異なる場合があるので、確認する際は注意しましょう。
また、断熱性を表す指標には、熱損失係数を示す「Q(キュー)値」があります。ただし、2013年の省エネ基準改正からUA値を使うようになったため、Q値は使われなくなりつつあります。
※参照:国土交通省「地域区分新旧表」
※参照:国土交通省「【参考】住宅における外皮性能」
2. ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)
ηAC(イータエーシー)値とは冷房期の平均日射熱取得率のことで、家にどの程度の日射熱が入るかを表す数値です。
ηAC値は「窓から入る日射の熱」と「窓以外から日射の影響で熱伝導によって入り込む熱」の両方を踏まえて計算します。
また、ηAC値は数値が小さいほど家に入る日射の熱量が少なく、冷房効果が高いと判断できます。UA値と同様に、ηAC値の数値基準も8つの地域区分によって異なるため、建築予定地に合わせて基準をチェックしましょう。
※参照:国土交通省「【参考】住宅における外皮性能」
断熱性の等級

断熱性の等級には、品確法によって定められている「断熱等性能等級(断熱等級)」があります。
断熱等級は1〜7段階に分かれており、断熱等級は数字が大きいほど熱の出入りが少なく、断熱性が高いことを意味します。断熱等級の内容は、以下のとおりです。
| 断熱等級 | 内容 |
|---|---|
| 7 | HEAT20のG3グレードと同等 |
| 6 | ZEH+やHEAT20のG2グレードと同等 |
| 5 | ZEH水準と同等 |
| 4 | H28省エネ基準(平成28年)と同等 |
| 3 | 新省エネルギー基準(平成4年)と同等 |
| 2 | 旧省エネルギー基準(昭和55年)と同等 |
| 1 | 上記以外 |
断熱等級のクリアすべき基準は、8つの地域区分によって異なります。たとえば、区分6に該当する東京都で断熱等級4を満たすには、UA値は0.87以下・ηAC値は2.8以下が必要です。
また、現行の省エネ基準は「H28省エネ基準」であり、断熱等級4に該当します。2025年4月以降の新築はすべての断熱等級4以上が義務化されるので、前提にして家づくりを進めましょう。
※参照:国土交通省「家選びの基準変わります」
断熱性が高い家のメリット

断熱性が高い家のメリットは、以下のとおりです。
メリットを最大限に活かして、快適な住まいを実現しましょう。
1. 夏は涼しく冬は暖かい快適な家を目指せる
断熱性が高い家は熱の出入りする量が減り、夏は涼しく冬は暖かい快適な家を目指せます。これは、断熱性によって外気の影響を受けにくくなるからです。
たとえば、冬場に外の冷気が壁や天井などを通って室内へ移動するのを遮断することで、寒さを緩和できます。また、夏場は外気の影響で室内の温度が上昇するのを防ぎ、暑さによる不快感を軽減できます。
部屋単体ではなく家全体の室温を一定に保ちやすいので、「廊下だけ寒い」「玄関だけ暑い」などのストレスもありません。
2. 冷暖房効率が高まる
断熱性が高い家は外気の影響を受けにくいことから冷暖房効率が高く、エネルギー消費量を減らせます。エネルギー消費量が減れば、光熱費の削減につながり、長い目で見ても経済的です。
電気料金の値上げなどがあった場合に、受ける影響が少なく済むのも大きなメリットです。加えて、電気料金の変動に一喜一憂する必要がないため、心理的なストレスを軽くできます。
また、冷暖房にかかるエネルギーを抑えられるので、地球への負荷を軽減でき、サステナブルな社会の実現につながります。
3. ヒートショック予防に役立つ
断熱性が高い家では部屋同士の温度差を小さくできるので、ヒートショック予防に役立ちます。ヒートショックとは、急激な気温の変化によって血圧が変動し、心臓や血管に大きな負担がかかることです。
たとえば、暖かい室内から寒い脱衣所へ移動してお風呂に浸かるなど、温度差が激しい状況でヒートショックが起こる可能性があります。断熱性が高い家では、ヒートショックの原因となる温度差を抑えられます。
ヒートショックを予防してご家族の健康を守るためにも、断熱性が高い家を検討しましょう。
ヘーベルハウスではALCコンクリートと高性能断熱材を組み合わせた二重構造で、高い断熱性能を実現しています。ヘーベルハウスの断熱性についてもっと知りたい方は、以下のページをご覧ください。
また、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」では、戸建系商品で「断熱等級6」を標準化しているヘーベルハウスの断熱性について動画などで詳しく解説しています。また、断熱性を含めた家づくりのポイントについて紹介したコンテンツもご用意しているので、断熱性に関する情報を収集したい方はぜひご活用ください。
断熱性が高い家のデメリット

断熱性が高い家のデメリットは、以下のとおりです。
断熱性が高い家で「イメージと違った」などのミスマッチを回避するために、デメリットをチェックしましょう。
1. 内部結露のリスクがある
断熱性が高い家では断熱材を入れる際にすき間が発生すると、内部結露のリスクがあります。内部結露とは、室内の暖かい空気が壁の内部に侵入し、壁内や天井裏などで結露が発生する現象です。
内部結露は柱や土台の劣化の原因となり、建物の寿命を縮めるおそれがあるので注意しましょう。
断熱性が高い家で内部結露を防止するには、防湿シートを適切に施工して対策が必要です。技術力やノウハウをもつ施工業者に依頼して、内部結露の対策を講じましょう。
2. 建築コストが高くなる可能性がある
断熱性が高い家を建てる場合、断熱性に優れた建材を利用する必要があり、建築コストが高くなる可能性があります。
また、断熱性が高い家を建築するのに、設計力・施工技術が求められる点もコストが高くなる要因の一つです。ただし、断熱性が高い家は光熱費を削減しやすいため、長期的な視点で考えると経済的だといえます。
省エネ性能に優れた家を建てる場合は、国や自治体が提供している補助金制度や税制優遇を利用できるケースがあります。補助金を積極的に活用して、費用負担を軽減しましょう。
3. 夏場にオーバーヒートのリスクがある
断熱性の高い家は一度熱が入ると逃げにくいので、夏場のオーバーヒートのリスクがあります。オーバーヒートとは、夏場に家に入り込む太陽の熱が外に逃げず、室温が上昇する現象です。
断熱性の高い家でオーバーヒートを防ぐには、あらかじめ日照や日射などをシミュレーションしておく必要があります。
ヘーベルハウスでは、住環境シミュレーションシステムの「ARIOS(アリオス)」を使って、建築前に日当たりや風通しを敷地位置に合わせて詳細に検証できます。ARIOSの機能の一部例は、以下のとおりです。
- 夏場に暑くなる部屋を予測する「日射シミュレーション」
- 季節や時間帯に応じた室温を確認できる「室温シミュレーション」
- 日照時間と部屋全体の日当たり具合を確認できる「日照シミュレーション」
上記の機能を参考に、開口部の位置を最適化したり、日よけ対策を検討したりすることで、オーバーヒートを予防できます。ARIOSについてもっと知りたい方は、以下のページをご覧ください。
また、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」では、ARIOSの特徴について解説した動画をご用意しています。無料で登録できるので、ぜひご利用ください。
断熱性が高い家をつくるポイント

断熱性が高い家をつくるポイントは、以下のとおりです。
それぞれのポイントを押さえて、断熱性の高い快適な家を目指しましょう。
1. 窓や玄関ドアの断熱性も重視する
天井・壁・床に加えて、窓や玄関ドアなどからも多くの熱が出入りしているので、開口部の断熱性を重視することが大切です。
資源エネルギー庁の資料によると、開口部からの熱の出入りする割合は以下のとおりです。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 冬の暖房時の熱が流出する割合 | 58% |
| 夏の冷房時に熱が流入する割合 | 73% |
50%以上の熱が開口部を介して出入りしており、断熱対策が必要なことがわかります。開口部の断熱対策を検討する際は、以下の製品を取り入れましょう。
- 樹脂サッシ
- ペアガラス
- トリプルガラス
- 断熱仕様の玄関ドア
地域の気候条件によって窓や玄関ドアに必要な断熱性能が異なるため、施工業者にアドバイスをもらいながら製品を決めると安心です。
※参照:資源エネルギー庁「省エネ住宅」
2. 換気計画にこだわる
断熱性と合わせて、換気システムにもこだわって家づくりを進めましょう。24時間換気システムの種類は、以下のとおりです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 第1種換気 | 外気を取り入れる給気口と空気を排出する排気口の両方にファンを設けて強制的に機械で換気する |
| 第2種換気 | 給気口のみにファンを設置して、自然に換気する |
| 第3種換気 | 排気口のみにファンを設置して、自然に給気する |
なお、2003年以降の新築ではシックハウス症候群の予防を目的として、24時間換気システムの設置が義務づけられています。
第1〜3種換気のどれを選ぶべきかは、換気設備に求める条件や目的によって異なります。
たとえば、安定的に換気をしたい場合には給気口と排気口の両方にファンが設けられた「第1種換気」がおすすめです。また、ランニングコストを抑えたい場合には、排気口のみにファンを設置する「第3種換気」が向いています。
お客さまには、新鮮な空気を取り込み、効率よく換気できる「第1種換気」をおすすめすることが多いです。
3. 実績豊富な施工業者を選ぶ
断熱性が高い家を建てるには、施工業者の技術力が問われます。
技術力の低い施工業者を選ぶと、断熱材を施工する際にすき間ができて内部結露が発生する原因となるので注意が必要です。
施工業者の公式ホームページの施工事例をチェックして、実績を確認しましょう。また、ご自身が建てたい断熱等級のレベルの家の実績があるかを確かめることも重要です。
実際にモデルハウスに足を運んで、断熱性が高い家を実感してみるのもおすすめです。
4. 高い断熱性が長く続く断熱の耐久性も重視する
新築当初の断熱性能の高さが継続するかも重要なポイントです。断熱性の持続期間は断熱材の耐久性に左右されるため、あらかじめ施工業者に確認しましょう。
ヘーベルハウスでは、独自開発した高耐久な断熱材「ネオマフォーム」を使用しています。ネオマフォームは、過酷な耐久性試験で浸食や変形がほとんどないことが確認されており、高温にさらされる屋根などでも長期的な利用が可能です。
また、耐久性に優れた断熱材であっても、湿気によるカビで劣化する可能性があります。断熱材のカビの主な原因は、施工不良による内部結露です。施工不良を避けるために、技術力が高い施工業者を選びましょう。
断熱性が高い家で快適な生活を実現しよう

断熱性とは熱の移動を抑える性能を指し、快適な家を目指すうえでは欠かせない性能の1つです。窓や玄関ドアの断熱性を重視したり、実績豊富な施工業者に依頼したりすることで、断熱性が高い家を実現しましょう。
「断熱性の高い家を建てたい」とお考えの方は、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」にご登録ください。
THINK HAUSでは、断熱等級6を標準化しているヘーベルハウスの断熱性について詳しく解説しています。無料で登録できるので、快適に暮らせる家づくりの情報を収集したい方はぜひご活用ください。
この記事の監修者
ヘーベルハウスのコラム編集部です。
家づくりに役立つ情報をわかりやすく発信中。
注文住宅の基礎知識から、設備や間取りの情報まで、
理想の住まいづくりをサポートします。
関連記事
人気記事
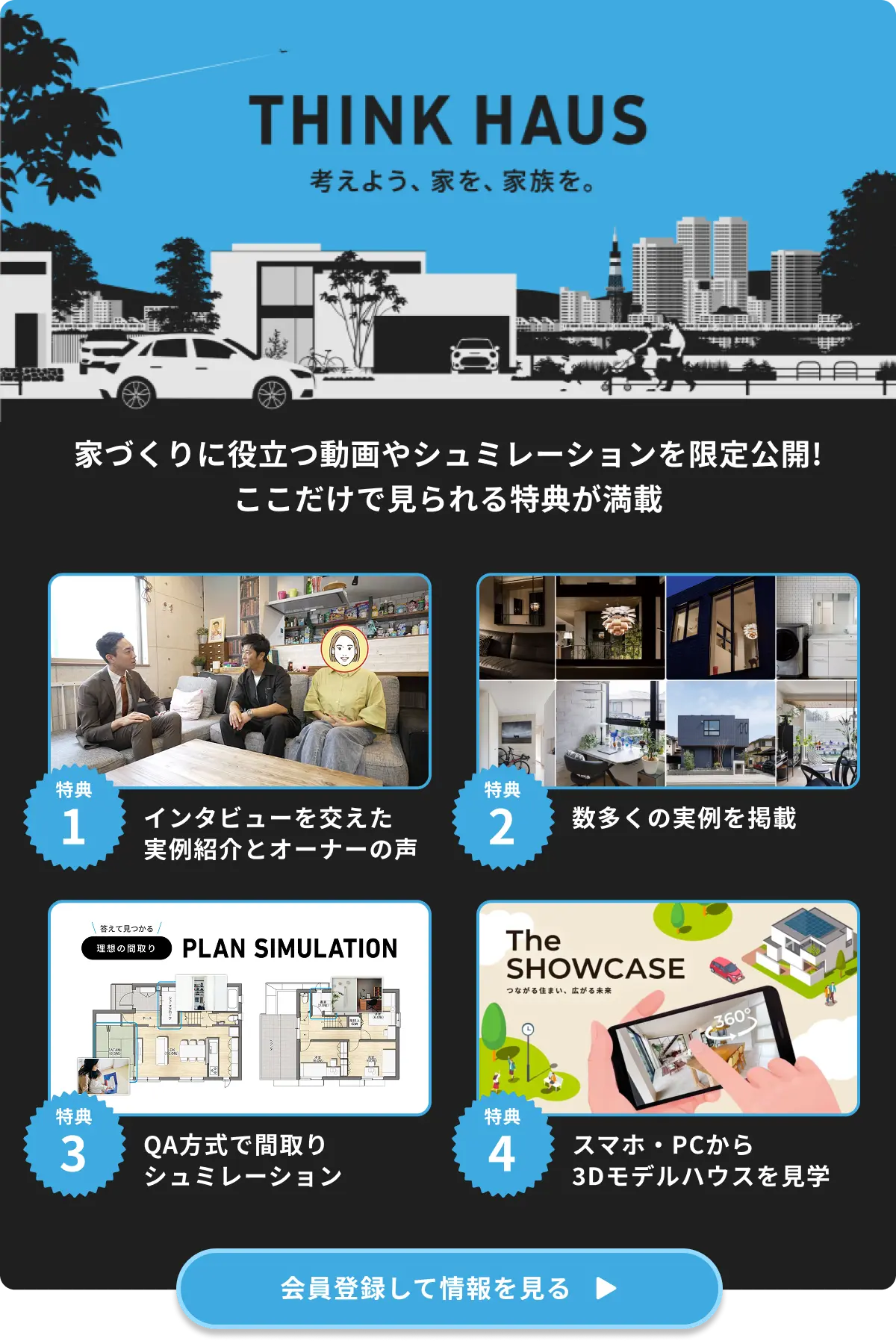









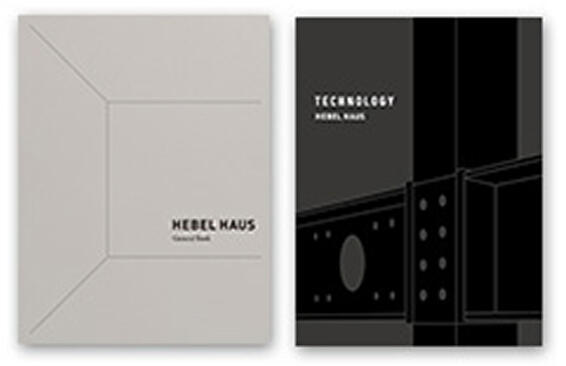
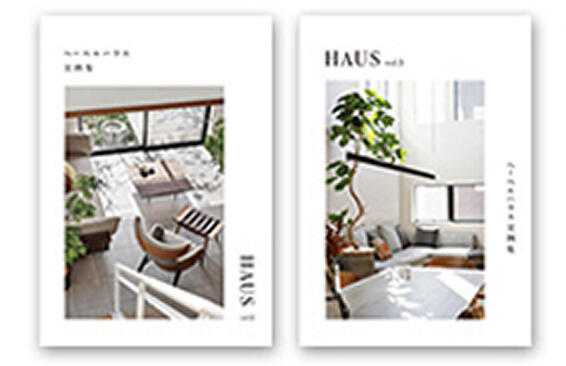

2030年以降の新築の省エネ基準は「断熱等級5(ZEH水準)」にまで引き上げられる予定であり、今後の住宅の基準を考慮すると断熱等級5以上がおすすめです。
また、性能面では、以下のように省エネにつながるとされています。
断熱等級4から5に引き上げた場合:約20%
断熱等級4から6に引き上げた場合:約30%
断熱等級4から7に引き上げた場合:約30%
より快適な住宅を目指したい場合は、なるべく高い断熱等級を選びましょう。