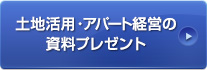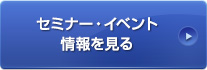前回のマンスリーレポートでご紹介したように、都市部の多くで路線価が上昇しました。また、来年からは相続税の基礎控除が大幅に引き下げられます。これにより、相続税の課税対象者が急増すると言われています。これまで相続税とは無縁だった人にとっては、相続対策をどこからどう手を付ければよいのか、分からない方も多いでしょう。今回は、多くの相続問題を解決してきた落合孝裕税理士に、相続対策の基本についてお伺いしました。
首都圏に戸建てを持っている人は、その多くが課税対象に!
─7月に路線価が発表され、三大都市圏では上昇に転じました。この結果について、どういう印象を持たれましたか?
落合:東京では、ほとんどのエリアが上昇しました。都心だけではなく、郊外も上昇しています。よくランキングにでる路線価は駅前の商業地ですが、例えば中野で7.6%、北千住で6.6%、吉祥寺で4.6%、他には町田4.1%、八王子2.3%とそれぞれ上昇しています。しかし、感覚としてはもっと上昇していてもおかしくないと感じています。なぜなら、路線価は1月1日時点のものですが、すでに7カ月が経過し、その間、景気回復も続いているからです。実勢価格はさらに上昇しているでしょう。このまま、年末まで大きな景気の腰折れ要因でもない限りは、来年はもっと上昇すると思います。そうなると、いよいよ地価は上昇局面に入ると見てよいと思います。
─来年からは相続税の基礎控除が引き下げられ、納税者が増えると言われています。実際、どれほど影響がありそうでしょうか?
落合:全国平均で見ると、相続が発生した人の中で相続税を申告した人は約4%でしたが、これが6%ぐらいに上昇するのではと言われています。さほど大きな割合ではありませんが、これはあくまで、全国平均です。これが東京都となると、話はまったく変わってきます。
平成23年の東京23区の相続税の申告割合をまとめてみました(下表参照)。都心の千代田区では22.6%もあります。注目してほしいのは、住宅街の広がる世田谷区、杉並区でも15.9%が納税していることです。この割合が、来年の相続税の改正で、倍近くになるのではないかと私は思っています。つまり、東京都内で少し広めの敷地に自宅を持っている方は、ほぼ相続税の対象になると見てよいでしょう。
■東京23区の相続税の申告割合(平成23年)
※東京国税局のデータ等より落合会計事務所で作成 |

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎控除は、来年1月1日から3,000万円+600万円×法定相続人に減額されます。相続税の評価基準となる路線価は、実勢価格の約8割ぐらいです。例えば、実勢価格が5,000万円ほどの土地家屋があったとすると、評価額はおよそ4,000万円。親一人、子ども二人のケースで相続が発生すると基礎控除は4,200万円です。その他の預貯金等が200万円以上あると相続税がかかってくるということになります。
─自宅の場合は小規模宅地の特例で、相続税評価が低くなるのでしょうか?
落合:子どもが引き継ぐ場合は、小規模宅地の特例で自宅の相続税評価は8割も低くなります。ただし、要件が厳しく、子どもが引き継ぐ場合は基本的には親と同居していることが条件です。子どもが結婚して独立し、持ち家に住んでいる場合は、この特例は使えません。
対策その1 まずは、資産を把握する
─これまで、相続税の心配をする必要のなかった人まで、影響するということですね。いわゆる相続対策とは、何をすればよいのでしょうか?
落合:取り急ぎ、考えておくべき必要なことが3つあります。
まずは、資産の把握です。土地家屋や預貯金などがいくらあるのか、そして相続税はどの程度かかるのか、ということです。相続税の額によっては納税資金対策も必要になってきます。注意したいのは、資産の実勢価格が、そのまま相続税の対象ではないということ。資産は相続税評価額にした上で、相続税を計算します。土地は買ったときの価格だと思っている方がいますが、そうではなく路線価で評価します。路線価は国税庁のホームページで確認することができます。
概算の方法としては、土地は固定資産税の納税通知書に敷地面積が書かれていますので、それに路線価を掛けてください。建物は固定資産税評価額が相続税の評価額です。アパートの場合は、借家権割合を減じることができるのでさらに3割減です。もちろん預貯金も加味して、資産を把握して相続税がどれだけかかりそうか判断してください。
正確には土地の相続税評価額の計算は、面している道路や土地の形状で計算の仕方が変わってきますので、きちんと計算したい場合は一度専門家に依頼したほうがよいでしょう。
─気をつけた方がよいポイントはありますか?

落合:実は税務調査が入った後、一番多く申告漏れを指摘されるのが預貯金です。例えば、亡くなったご主人より、専業主婦だった奥さんの預金のほうが多すぎる場合は、実質的にご主人の財産とみなされることもあります。名義借りで奥さん名義の預金口座を作っている場合も認められず、ご主人の財産としてカウントされますので注意してください。税務署が税務調査に入るときには、預金通帳については、誰が作って誰が管理しているのかを厳密に調べます。生前贈与として、贈与税のかからない110万円を毎年贈与するために、子ども名義の口座を作っていても、その存在を子どもが知らずに贈与した側で管理している場合は贈与にはならず、相続財産となりますので注意が必要です。
対策その2 誰にどう分けるか生前に決めておく
落合:次に考えたいのが、財産をどう分割するかということでしょう。どちらかというと、節税対策よりも分割対策のほうが大事と言ってもいいでしょう。結局、相続資産の大小ではなく、どう分割するかでもめるケースが多いのです。相続対策というと、つい相続税対策に目が行きがちですが、その前にどう分割するかを考える必要があるのです。
─公平に分割するポイントはありますか?
落合:公平かどうかは、それぞれの相続人が納得するかどうかでしょう。現金だけなら均等に分けられますが、土地家屋の場合はそうはなりません。どう分けても多少の偏りは出てくるものです。
これを解決する最もオーソドックスな方法が遺言です。一番良いのは公証役場で作成する公正証書遺言です。原本が公証役場に残りますので、紛失や偽造の心配がありません。ただし、遺言を作ることは心理的なハードルが高いため、なかなか進まないことがよくあります。何もないと亡くなった人の意思が全く伝わりません。手紙のようなものでもよいので残しておけば、そこに思いが書いてあるなら、法的な拘束力はありませんが相続人も納得しやすいのではないでしょうか。
─しかし、いざその時が来て、遺言書の内容そのものが不公平だとトラブルになることはありませんか?
落合:あるかもしれませんね。例えば、次男がずっと親の介護をしていた場合、長男よりもっと多くもらってもいいはずだとかいう場合です。これを寄与分と言いますが、実は、法的には寄与分はあまり認められないことのほうが多いです。
こういったトラブルの原因をなくすためにも、私は生前から相続についての意思表示をしておくことが有効だと思っています。きっちりしたものでなくても、相続についてはこんな風に考えていると意思表示することで、親世代も子世代も相続について考えるようになります。
─お盆やお正月など、家族が集まるときがよい機会ですね。
落合:そうですね。それから、昨今の相続については注意したい点があります。 今は長寿社会で寿命が延びていますが、その分、相続問題が先になるかと言うと、そうでもありません。実は今、体は元気でも認知症など、認知能力がなくなるケースが増えています。そうなると、財産は凍結されてしまうことがあります。そうなると、預金は自由に引き出せなくなりますし、土地活用もできません。遺言も書けなくなってしまいます。もう、相続対策はできなくなってしまうのです。
─何か対策はあるのでしょうか?落合:成年後見制度の活用です。成年後見制度は、認知能力がなくなってから活用する「法定後見制度」と、そうなる前に活用する「任意後見制度」があります。任意後見制度を活用すれば、本人が元気なうちに後見人を選び、財産の管理の意向をあらかじめ決めることができます。遺言もセットにしておけば、本人の思いを相続に反映することができます。 |

|
対策その3 相続資産の評価を下げる
落合:最後に必要なことは、相続税対策です。中でも最も効果的なのが、相続資産の評価を下げるということです。納税者の相続資産の51%強は土地家屋です。つまり、この土地家屋をどうするかによって、相続税額が大きく変わってくるのです。土地に関しては、その活用方法で大きく評価が下がりますから。
例えば遊休地がある場合、更地の場合は路線価の価格が100%評価となります。都内のように地価が高いところでは、相続税評価も高いままです。そこで、よく行われている相続対策が、土地活用です。将来の売却を見越して駐車場にしているケースもありますが、青空駐車場は更地と同じ扱いです。コインパーキングでも若干の評価減にしかなりません。
そこで最も評価減の効果があるのが、アパートの建築となります。アパートを建築すると、その土地は貸家建付地となり、評価は約2割下がります。また建物についても、建築費に比べて相続税の評価額は半分程度と大幅に下がります。アパート経営の場合、建築後には収益が上がりますので、それを納税資金として活用するといったこともメリットとしてあげられます。
先ほども触れた、子どもが独立した自宅の場合、小規模宅地の特例は使えませんので、土地は100%の評価です。この場合の対策としては、自宅をアパート併用住宅に建て替える方法があります。小規模宅地の特例は、自宅に使えなくてもアパートに使えば50%評価が下がります。例えば建物の割合が、自宅3分の1、アパート3分の2の場合、敷地の3分の2が50%の評価減(200m2まで)となります。
─その他に資産の評価を下げる対策はありますか?
落合:いわゆる資産の組み換えです。例えば現金を持っていれば、そのままの額が評価額となりますが、その現金で不動産の購入をすれば評価を下げることができます。先ほどの説明のように土地も建物も実勢価格より低く評価されますので、その分相続対策としては資産の圧縮効果があるのです。タワーマンションの高層階を相続対策として購入するケースも少なくありません。
この他、相続対策には生前贈与の活用や納税資金の準備など、さまざまなことが考えられますが、まずは資産を把握して、一度、ご家族で話し合われるのがよいと思います。中には、親世代よりも子世代のほうが、心配しているケースもあります。しかし、なかなか相続について話を切り出すのは難しいものです。ご家族で相続のセミナーに参加したり、税理士など第三者を加えるのも一つの方法です。
落合会計事務所のホームページはコチラ
無料メールマガジン「税理士が教えるとっておきの税金情報」に登録すると、毎週火曜日に最新情報が届けられます。