第69回日本透析医学会学術集会・総会 ランチョンセミナー35
司会
友 雅司 先生大分大学医学部附属 臨床医工学センター
演者
植木 嘉衛 先生医療法人三思会 東邦病院
現地開催
2024年6月9日(日)
12:35~13:35

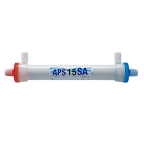


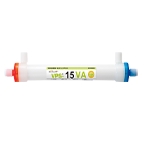










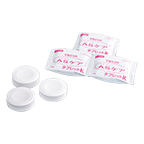




















ホーム 学会・セミナー情報
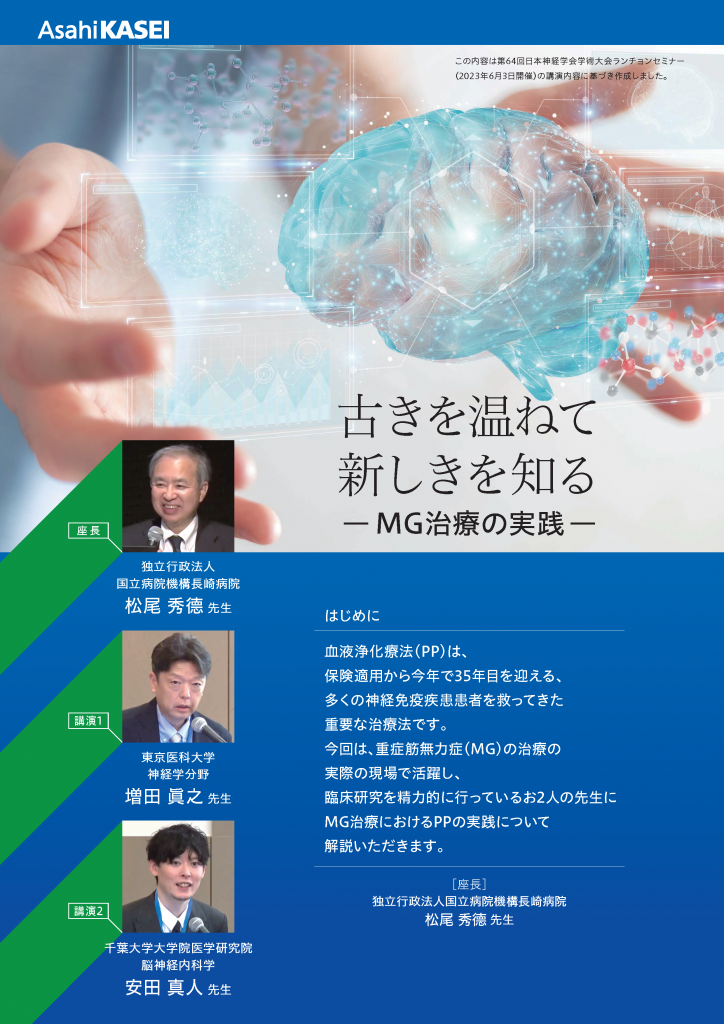
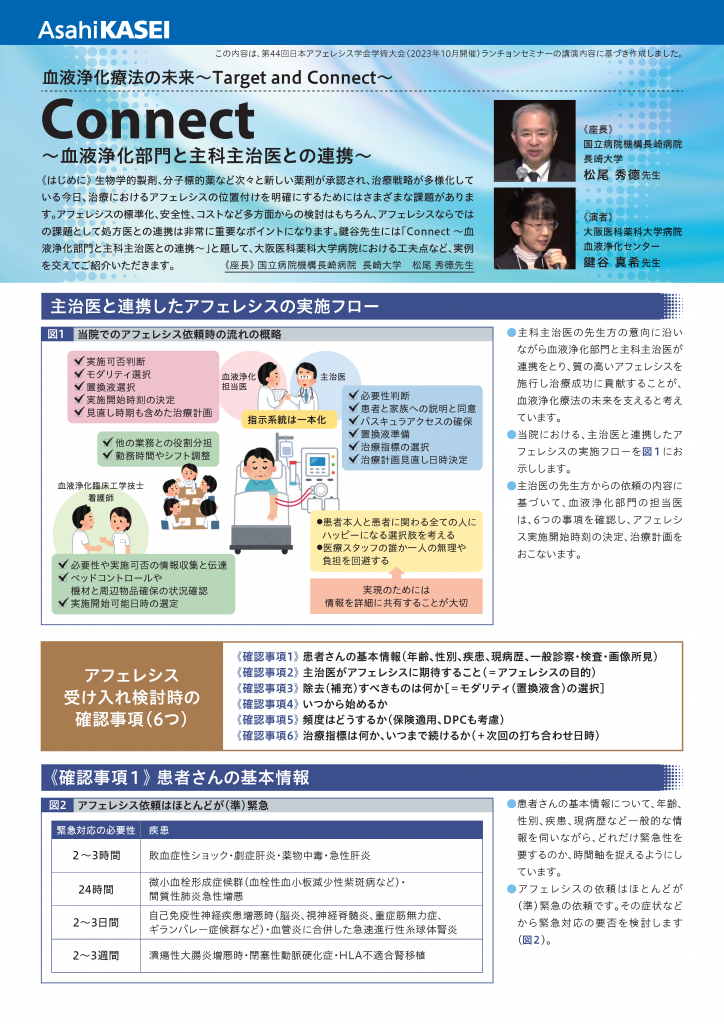

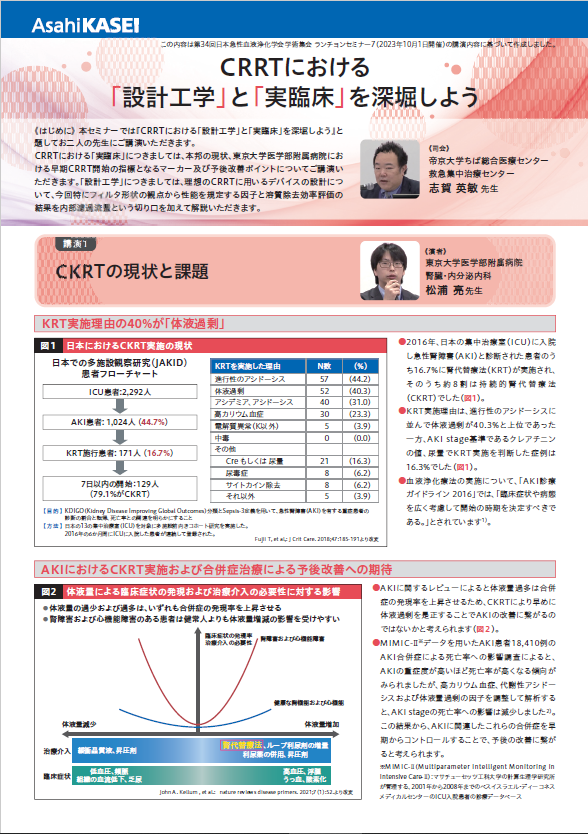
© Asahi Kasei Medical Co., Ltd.