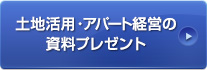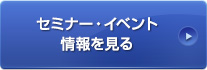7月1日、国税庁より相続税・贈与税の土地評価の算定基準となる路線価が発表されました。今年3月に発表された公示地価の上昇を受けて、主に三大都市圏での路線価の上昇傾向が鮮明になりました。来年からは、相続税も増税され、土地オーナーにとっては相続・贈与の税負担増につながるのではと関心が高まっています。
三大都市圏で路線価は上昇
今年の路線価は、前年と比べて東京1.8%、愛知1.2%、大阪0.3%と三大都市圏で揃って6年ぶりに上昇しました。首都圏で見ても東京の他、神奈川0.8%、千葉0.1%、埼玉0.1%といずれも上昇しています。全国で見ると、前年の上昇は2県でしたが、今年は8都府県に拡大しています。全国平均では0.7%下落しましたが、下げ幅は6年連続縮小しています。
先に発表された公示地価からも、今年の路線価の上昇は予測がついていましたが、これで底打ち感がさらに広がったと言えるでしょう。要因は、ゆるやかな景気回復傾向により、都市部を中心とした再開発、インフラ整備、それにあわせてREIT(不動産投資信託)の動きが活発になったことです。ちなみにREITの2013年の資産取得額は約2兆2,000億円で前年の2.8倍だそうです。
こうなると、土地オーナーとして心配になるのが、来年から増税となる相続税です。ご存じの通り、路線価は相続税・贈与税評価の基準となるものです。すでに、相続対策としてタワーマンションを購入したり、賃貸住宅の建設を進めるオーナーも増え、それも少なからず路線価上昇の要因となっているようです。
■主要都府県の標準宅地の対前年変動率の平均値(単位:%)
|
|
|
東京圏の動向ー五輪、再開発がけん引、東京都の下落地点はゼロ
東京都内の税務署管内ごとの最高路線価は48地点中、青梅の横ばいを除いて47地点で上昇しました。下落地点はゼロです。
東京五輪への期待感から、臨海地域ではマンション販売が好調であり、都心部では銀座、日本橋、虎ノ門と再開発が進んでいます。新宿三丁目は2013年の東京メトロ副都心線と東急東横線の相互乗り入れの効果が出始め、買い物客が増加してオフィス需要も高まっているようです。
また、都心だけではなく再開発、大学移転で昼間人口が2万人増えたという中野駅前が7.6%、再開発の影響が続く北千住駅前が6.6%、住みたい街No1の吉祥寺が4.6%と郊外の人気エリアも高い伸びを示しました。昨年の上昇率トップは川崎駅前で5.7%の上昇でしたから、今回は上位の上昇率がさらに大きく伸びたことが分かります。その川崎駅前は今回も上昇率トップで11.8%と昨年の約2倍の上昇率です。これも駅前の再開発が進んでいることが要因となっています。
また、都内の木造住宅密集地域(木密エリア)を見ると、墨田区京島、江東区北砂エリアで1.8%の上昇、東池袋で2.5%の上昇です。木密エリアは防災対策として、東京都の建て替え促進地域でもあります。このエリアの建て替えが進むと、さらに路線価は上がっていくと予想されます。
■東京圏の最高路線価上昇率トップ5(1m2あたり)
|
順位 |
所在地 |
対前年増減率(%) |
|
|
平成26年 |
平成25年 |
||
|
1 |
川崎市川崎区駅前本町 川崎駅東口広場通り |
11.8 |
5.7 |
|
2 |
新宿区新宿3丁目 新宿通り(四谷) |
9.8 |
▲0.6 |
|
3 |
新宿区新宿3丁目 新宿通り(新宿) |
9.8 |
▲1.0 |
|
4 |
中央区銀座5丁目 銀座中央通り |
9.7 |
0.0 |
|
5 |
港区北青山3丁目 青山通り |
8.1 |
0.6 |
名古屋圏の動向ーリニア新幹線に大規模再開発が進む
昨年の路線価でも上昇した愛知県は、東京都に次いで1.2%の上昇となりました。
今、名古屋圏で最も注目されているエリアが上昇率1位となっている名駅エリアです。今秋には、リニア中央駅新幹線の着工が始まり、期待感が高まっています。また名駅東側では、戦後最大と呼ばれる大型開発が進行中で2017年までには超高層ビルが次々と誕生する予定です。さらに、栄三丁目エリアでは若者向けの飲食店の出店が相次ぎ、賃貸住宅が増えていると言います。
上昇率3位の伊勢市は、昨年の伊勢神宮の式年遷宮による観光客増加の経済効果が続いています。
■名古屋圏の最高路線価上昇率トップ5(1m2あたり)
|
順位 |
所在地 |
対前年増減率(%) |
|
|
平成26年 |
平成25年 |
||
|
1 |
名古屋市中村区名駅1丁目(名駅通り) |
10.0 |
2.4 |
|
2 |
名古屋市西区牛島町(広井町線通り) |
8.8 |
0.9 |
|
3 |
伊勢市宇治今在家町(館町通線通り) |
8.1 |
2.8 |
|
4 |
名古屋市昭和区御器所通3丁目(山王通り) |
6.9 |
0.0 |
|
5 |
春日井市松新町1丁目(勝川駅前広場通り) |
6.7 |
0.0 |
大阪圏の動向ーハルカス効果が今年もけん引
大阪圏では昨年に続き、高さ日本一の複合ビルとなった「あべのハルカス」周辺が20.8%と高い上昇率となりました。昨年の35.1%からは落ち着いたものの、マンション販売戸数が5年前の3倍超となり、「あべのバブル」とも言われるほどの過熱ぶりです。マンション市場は阿倍野の他、ランキングにも入っている天王寺、以前から人気の吹田、豊中エリアが活況で、路線価にもその傾向は表れました。上昇率2位のJR大阪駅北側はグランフロント大阪の開業で注目を集めたエリアです。
阿倍野、JR大阪駅周辺は、いずれも大規模開発で、街の様子が一変するほどです。上昇率も全国で見ても大きなものとなっています。しかし、大阪国税局管内では、近畿6府県の平均変動率は0.4%減で、大阪府を除く5府県では下落しており、二極化傾向が見て取れます。
■大阪圏の最高路線価上昇率トップ5(1m2あたり)
|
順位 |
所在地 |
対前年増減率(%) |
|
|
平成26年 |
平成25年 |
||
|
1 |
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) |
20.8 |
35.1 |
|
2 |
大阪市北区大深町 (JR大阪駅北側) |
14.1 |
93.4 |
|
3 |
大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) |
10.4 |
10.4 |
|
4 |
吹田市豊津町 (大阪内環状線) |
10.3 |
1.8 |
|
5 |
豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) |
9.1 |
0.0 |
景気回復基調は継続、大きな腰折れがなければさらなる上昇も
地価は底打ち感が広がっていますが、今後どうなるかは景気回復が本格化するかにかかっています。消費税駆け込み後の反動は、一段落したとの見方もあります。
今回の路線価は2014年1月1日時点。その後、半年強が経過して大きな景気の腰折れも起こっていませんので、地価もさらに上昇していると見るのが妥当でしょう。もちろん、今後の景気動向については不安要素も少なくはなく、今後の景況感は業界によっても温度差があります。
しかし、このまま今年を乗り切れば、来年の公示地価、路線価はさらに上昇するとみてよいでしょう。特に三大都市圏では大規模な再開発が続き、それが地価上昇のけん引役になっていることを考えれば、しばらくはこの傾向は続き、地価も上昇トレンドに入っていく可能性はあるかもしれません。直近の指標としては、10月に発表される基準地価(7月1日時点)にも注目です。
土地オーナーとして、気を付けたいのは路線価上昇による評価額の上昇と、来年から始まる相続税の増税、そして相続税対策としてアパート建築を検討される方にとっては来年10月に予定されている消費税10%の増税です。時代の変化を見極めながら、対策を講じる必要があるでしょう。