平成28年分の相続税の申告状況が国税庁より発表されました。注目されるのは、相続税の課税対象者の増減です。平成27年分は、相続増税の影響で課税対象者が急増しましたが、その傾向は続いているのでしょうか? また、平成30年度の税制改正は、どのような影響があるのでしょうか? それぞれ見ていきたいと思います。
相続税の課税割合は12.8%(東京)。昨年と同水準で推移
相続税は平成27年より増税となり、平成27年分の相続では課税対象者が急増しました。東京国税局(管轄:東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)での相続税の課税対象者は、これまでの約2倍の12.7%に急増しています。大きな要因は、相続税の基礎控除額の引き下げです。
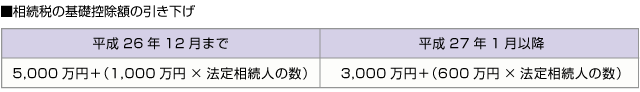
それから1年後、平成28年分のデータが国税庁から発表されました。
それによると、東京国税局の管轄では、課税対象者は12.8%で昨年同様の水準でした。亡くなられた被相続人の約8人に1人が課税対象となっています。増税前は、7%前後で推移していましたが、今後は13%前後で推移していくものと予想されます。
課税対象者の割合は、全国で見た場合も同様の傾向があります。全国と三大都市圏の比較です。
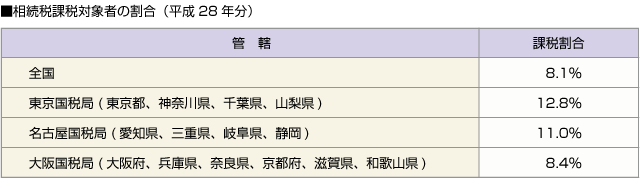
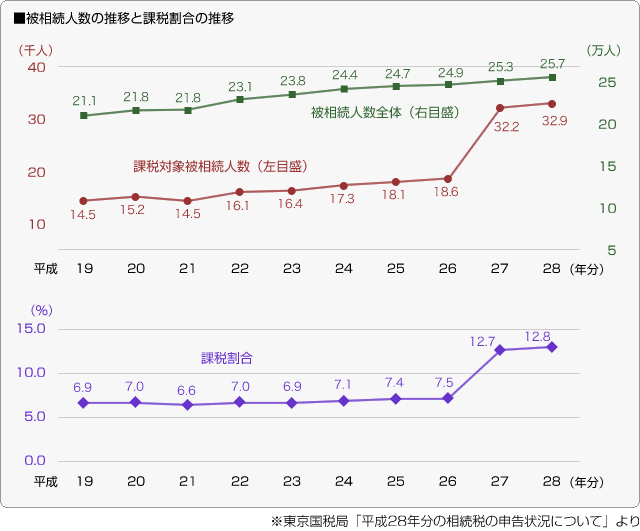
基礎控除引き下げ等の相続税増税により、課税対象者は急増し東京国税庁管轄では平成28年も昨年とほぼ同じ12.8%となった。都心部では、この傾向で定着している。
被相続人1人あたりの相続税額は2,473万円
次に相続税額を見てみます。
まず東京国税局管轄のデータを見ると、相続評価の課税価格の合計は、5兆2,818億円(平成27年5兆1,723億円)です。被相続人1人あたりで見ると1億6,050万円(平成27年1億6,059万円)の相続課税価格となっています。
実際に支払われた相続税額の合計は、8,140億円(平成27年7,615億円)。被相続人1人あたりでは2,473万円(平成27年2,364万円)となっています。
税額も平成27年より増加傾向にあります。相続税増税に加えて、土地の評価のもととなる路線価の上昇や株高も影響していることが要因として考えられます。今も経済は上昇傾向にありますので、土地や有価証券の資産価値はさらに上昇することが考えられます。そうなると、相続評価額も上昇し、土地オーナーにとってさらに注意が必要となってきます。特に相続税増税前の平成26年以前に、相続対策を実施した方は、あらためて資産評価の見直しが必要となってくるでしょう。
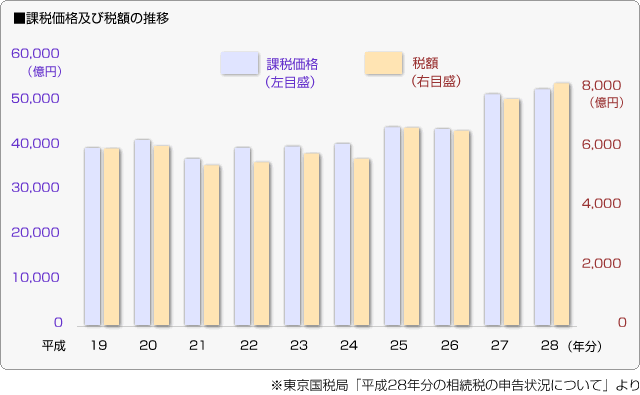
経済活動が活発化すると土地や有価証券の価値も上昇するが、その分相続税評価額も上昇し、相続税の負担は大きくなる可能性がある。定期的な資産評価の見直しが大切。
相続財産の構成比は土地よりも現金が増加傾向
同じく東京国税局管轄のデータから見ていくと、相続財産の金額の構成比は、「土地41.2%」で最も多く、続いて「現金・預貯金等29.4%」、「有価証券14.5%」の順となっています。土地の金額そのものは平成27年より増加していますが、それよりも現金・預貯金の増加が著しく、割合で見ると現金・預貯金が年々伸びています。
相続税対策の観点から見ると、現金はそのままの金額が相続財産として加算されるため、他の資産と比べ相続税の負担が大きくなります。
例えば現金1億円の相続評価は1億円ですが、1億円評価の更地に1億円でアパートを建築すると、合わせて2億円だった資産は約40%も評価が下がり1億2千万円ほどになります。相続評価の引き下げについては、「相続・贈与の基礎知識:財産評価の引き下げ編-土地活用で節税効果」をご覧ください。
また、現金は生前贈与した場合の特例がいろいろと用意されています。「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」「教育資金一括贈与制度」「結婚・子育て資金一括贈与制度」「ジュニアNISA制度」などで、それぞれ税制の優遇措置があります。うまく活用すれば相続税を軽減できる場合もあるでしょう。
生前贈与の活用については、バックナンバー「相続対策の選択肢が増えた"かしこい贈与"」をご覧ください。
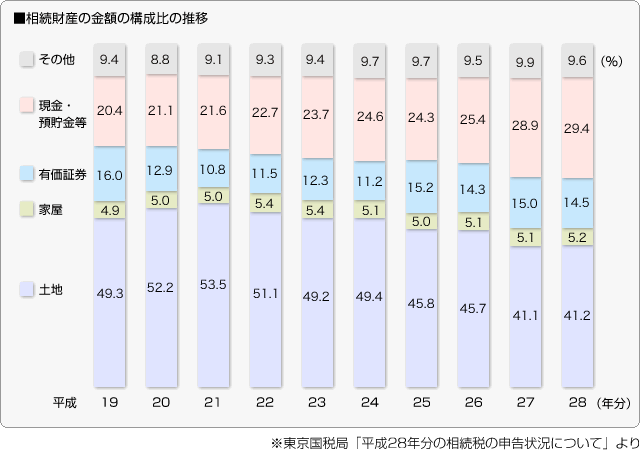
相続財産は現金が増加しているが、現金は相続税の負担が大きい。資産の組み替えや生前贈与で、評価の引き下げや相続財産そのものを減らす検討をすることが必要。
「小規模宅地等の特例」の要件が厳格化、課税対象者はさらに増加する傾向に
相続税の課税対象者が広がった要因は相続税増税ともう一つ、それは平成22年度に改正された小規模宅地等の特例の改正です。もう8年も前になりますが、相続においてこの特例が使えるかどうかは、大きなポイントです。この特例はこれまでも何度か改正が行われ、どんどん要件が厳しくなっています。
前号「平成30年度税制改正のポイント」でもお伝えしましたが、平成30年度の税制改正でもさらに要件が厳しくなり、土地オーナーにとっては大きな影響を及ぼすと思われますので、あらためてお伝えします。
小規模宅地等の特例とは、自宅の土地は330m2まで80%減額、賃貸住宅等の土地は200m2まで50%減額、事業用の土地は400m2まで80%減額されるというものです。このうち、自宅と賃貸住宅の要件が厳格化されました。
自宅の土地で評価減を受ける場合、その宅地を取得する相続人は配偶者か同居している親族に限られます。同居しているというのがポイントなのですが、同居していない親族、主に独立した子どもでも、本人または配偶者の持ち家ではなく賃貸住宅に住んでいれば適用されます(相続開始前3年以内)。今回の改正では、持ち家に住んでいないという要件が厳格化されています。
平成30年度の改正では、相続開始時に持ち家を過去に所有していたことがある場合、また3親等内の親族等が所有する家に住んだことがある場合(相続開始前3年以内)は、特例の対象から除外されることになりました。
これは、自宅から独立し持ち家に住んでいる子どもが、自分の子ども(被相続人から見ると孫)に自宅を生前贈与したり、親戚に売却した上で借りて住んでいたり、事実上持ち家なのに、登記上自身の持ち家ではないと見せかけるケースがあったからです。
もう一つの改正が賃貸住宅の土地の要件です。
一般的には、子ども世帯は持ち家で独立しているケースが多く、自宅に小規模宅地等の特例を適用させるのは難しくなっています。その場合でも、賃貸住宅があれば貸付事業用地の特例を適用させ、相続評価を大きく減額させることができます。しかし、こちらも不正に適用させる事例があります。
例えば、一時的に現金でアパートを一棟買いして小規模宅地の特例を適用させ、相続が終わったらすぐに売却してしまうケースです。この特例制度は、そもそも事業を引き継ぎやすくするために配慮されたもので、節税目的で利用されては意味がありません。
そこで、一時的に活用するのを防ぐため、3年間のしばりが設けられました。相続開始前3年以内に賃貸経営を開始した土地は、この特例では除外されることになりました。言い換えると、賃貸住宅を新たに建てても3年以内に相続が発生すると、この特例が適用できないということです。ただし、3年以上前から事業的規模で賃貸経営をしているオーナーが賃貸住宅を建て替えたり、新築したりした場合を除きます。
この改正は、平成30年4月1日以後に経営を開始した賃貸住宅の土地に適用されます。
特例の要件が厳格化されたことによって、来年以降は相続税の課税対象者や課税額はさらに増加するかもしれません。土地オーナーにとっては、相続の負担が大きくなる傾向にあります。これまで以上に計画的な土地活用や資産活用が必要になってくるでしょう。
小規模宅地等の特例の要件が厳格化。今後はさらに相続税の課税対象者や課税額が増える可能性がある。ますます計画的な土地活用・相続対策が必要。



