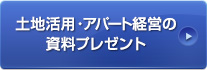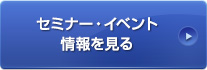インフレの影響で、物価上昇による資産の目減りを防ぐ対策を検討している方も少なくないでしょう。特に土地オーナーにとっては、地価が上昇し資産価値が高まると同時に、管理・運用においては対策を講じる必要があります。インフレ時代の資産管理・運用、特に土地活用をする上でのポイントについて小泉税理士にお話を伺いました。
CONTENTS
■インフレに強い資産、弱い資産
■空き家、遊休地等の保有デメリット
■土地活用はインフレ対策になるか?
■インフレ時の土地活用の注意点
■インフレに強い資産、弱い資産
─インフレに強い資産、弱い資産について教えてください。
小泉:インフレに強い資産は、株式、金、そして不動産、インフレに弱いのは現金です。
つまり、物価上昇に伴い価値が上がっていく資産がインフレに強いといえます。株式については、インフレ時でも利益の上がる企業の株価は上がっていきます。配当や株主優待もあるので、株式は長期保有するというスタンスがよいでしょう。
金もインフレになると価格が上昇するといわれています。また、金は株価が暴落した場合でも影響が軽微なため、資産防衛的な役割も果たします。富裕層の方は一定の割合で金を持っている印象ですね。
同様に不動産についても、インフレ時には上昇します。この10年で地価はかなり上昇しました。特に土地オーナーの方はそれを実感しているのではないでしょうか。財務省が発表した、令和5年度の相続税(相続税+贈与税)の税収は、約3兆5千万円で過去最高となりました。要因の一つは地価や株価の上昇です。

一方、現金はインフレになると価値が目減りしていきます。特に低金利の日本では、銀行に預けていてもほとんど利子はつきません。物価上昇とともに、現金の価値は目減りしていきます。例えば毎年2%の物価上昇が10年続いたとすると、現在の100万円は82万円の価値に、3%の物価上昇で74.4万円の価値に目減りしてしまいます。
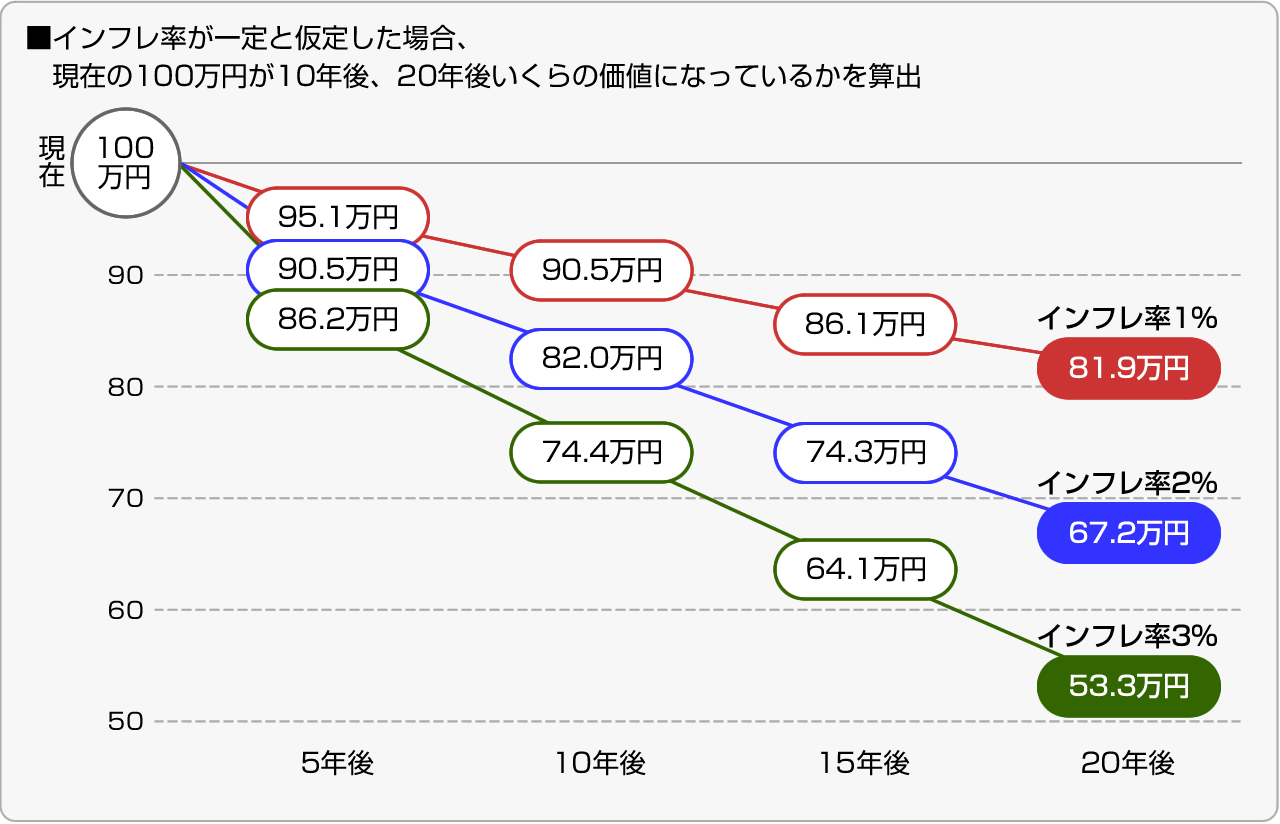
─インフレ対策としては、現金を資産価値が上昇する他の資産に組み替えた方がよいのでしょうか。
小泉:はい。ただし、バランスが大切です。
相続税は、原則現金で納付となりますので、相続が発生したときに納税資金が確保されているか、現金化しやすい資産があるかを確認しておいた方がよいでしょう。たまにあるのは、資産が現金化しづらいものばかりで納税資金が足りずに、土地を手放すケースです。急いで売ることにより、安い価格で売ってしまうことになりかねません。
納税資金や生活費を確保した上で、資産運用を考える必要があります。
インフレが続くと、現金は実質的に目減りする。将来の相続の納税資金を確保した上で、現金を他の資産に組み替えることを検討する。
■空き家、遊休地等の保有デメリット
─実家の空き家や遊休地などの不動産でも保有しておくメリットはありますか?

小泉:不動産は地価が上がれば資産価値も上がっていきます。ただし、空き家や遊休地はデメリットの方が多いと思います。
地価が上がれば、固定資産税も上がるし、相続税評価額も上がります。空き家や更地の場合は貸家建付地等に比べると、相続税評価額も高くなりますので、土地活用などの何らかの対策が必要です。
また、人が住んでいない空き家はすぐに傷んでしまうので、定期的にメンテナンスも必要になります。国も空き家対策に取り組んでいて、「空家等対策特別措置法」の「管理不全空き家」に指定されると固定資産税の住宅用地の特例(課税標準が評価額の6分の1又は3分の1になる)を適用できなくなってしまいます。窓が割れていたり、雑草が繁茂したりしている場合が「管理不全空き家」として想定されています。
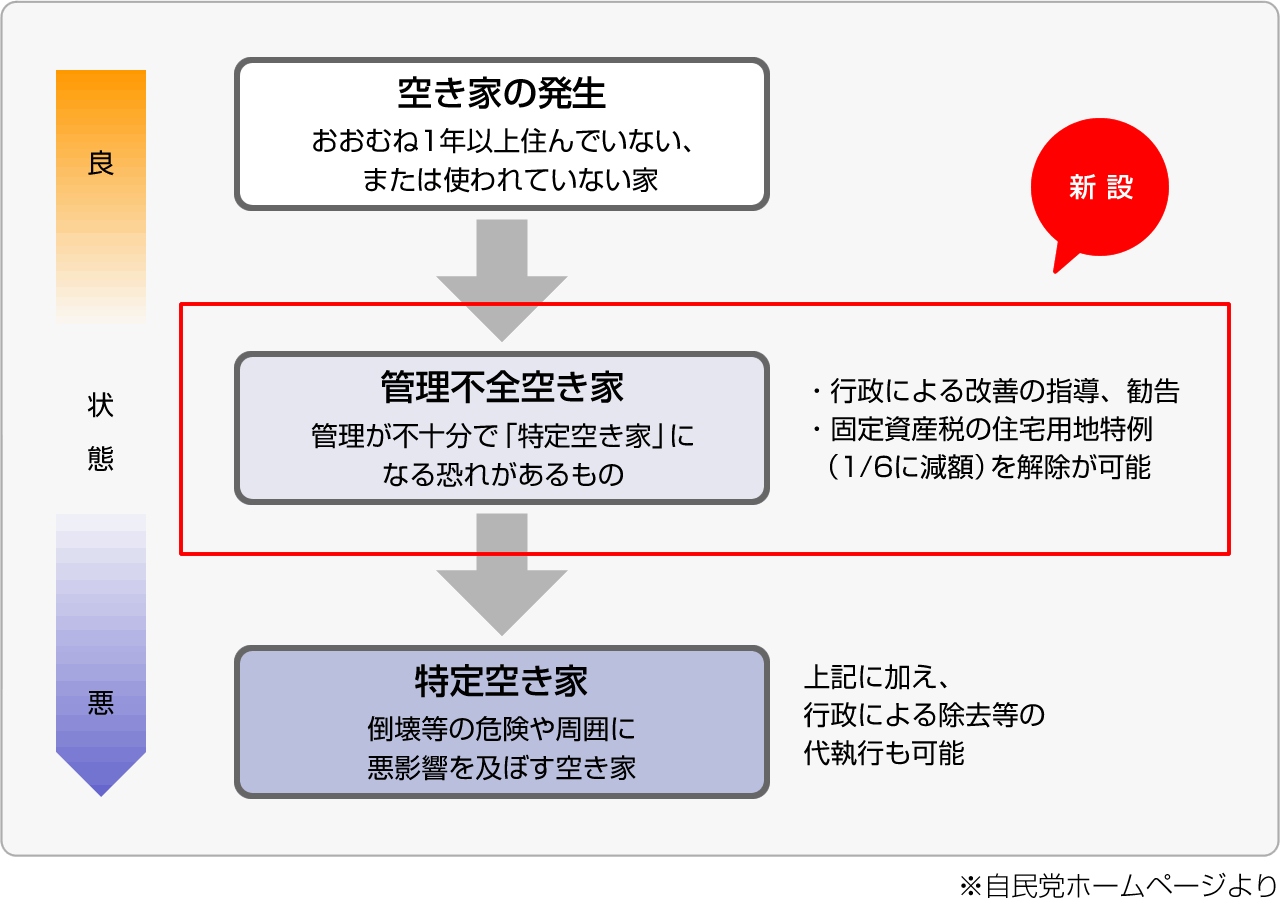
更地の場合は、メンテナンスは必要ないかといえばそうではありません。私の顧客の例ですが、更地を何年も放置していて、数年ぶりに見に行ったら不法投棄の温床になっていたケースがあります。せっかく価値のある土地なのに、そのゴミの処理にその土地の価値と同等の費用がかかる見積もりが出ました。このようなことを避けるためにも、更地でも定期的に見回りに行く必要があります。
空き家や遊休地を持っている場合は、何もしないことのデメリットのほうが大きいです。売却するのも一つの選択肢ですが、都市部の土地は利用価値が高いので何らかの有効活用を検討するべきだと思います。ただ所有しているだけでは何の利益も生みません。
空き家や遊休地がある場合は、何もしないことのデメリットが大きい。有効活用の検討をするべき。
■土地活用はインフレ対策になるか?
─先生の顧客もインフレ対策として不動産投資や土地活用を積極的に行っていますか?
小泉:日本のインフレはコロナ禍が明けた頃からですが、地価は10年前から上昇しています。特に三大都市圏では、商業地に限らず住宅地も上昇を続けています。
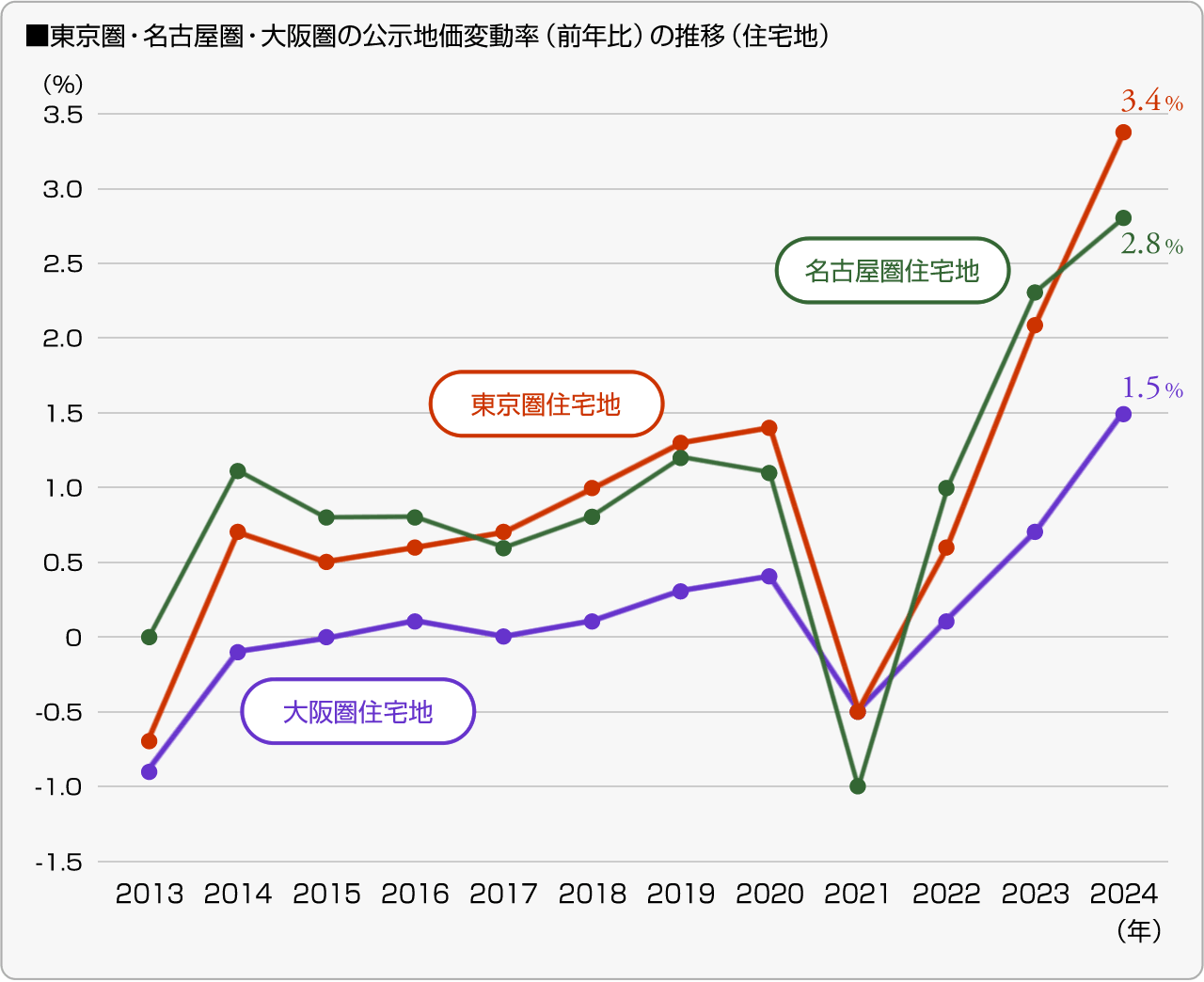

富裕層の方は、これを見越してか積極的に不動産を購入している印象があります。
不動産はインフレに伴い価値が上昇するだけではなく、相続税対策としても有効です。区分所有マンションの相続税評価が是正されましたが、それでも実勢価格の6割ほどになります。
区分所有マンション購入の他にも、より資産価値の高い駅前や都心部の土地を求めて、資産を組み替えるケースもあります。賃貸住宅などの収益性の高い不動産は、相続対策も踏まえた長期の視点で購入しているケースが多く見られます。
地価はこの10年間でかなり上昇した。富裕層は不動産投資や土地活用を積極的に行っている。
─建築費が高騰していると聞きますが、それでも賃貸住宅による土地活用はメリットがありますか?
小泉:インフレ時には家賃も上昇するといわれています。日本の物価上昇が始まったのは2021年後半といわれていますが、家賃もやや遅れて上昇しています。建築費の高騰をカバーするほどの上昇ではないかもしれませんが、プランニング次第で収益は出せますし、相続対策としても有効です。立地が良ければ、土地を買って賃貸住宅を建てる方もいらっしゃいます。
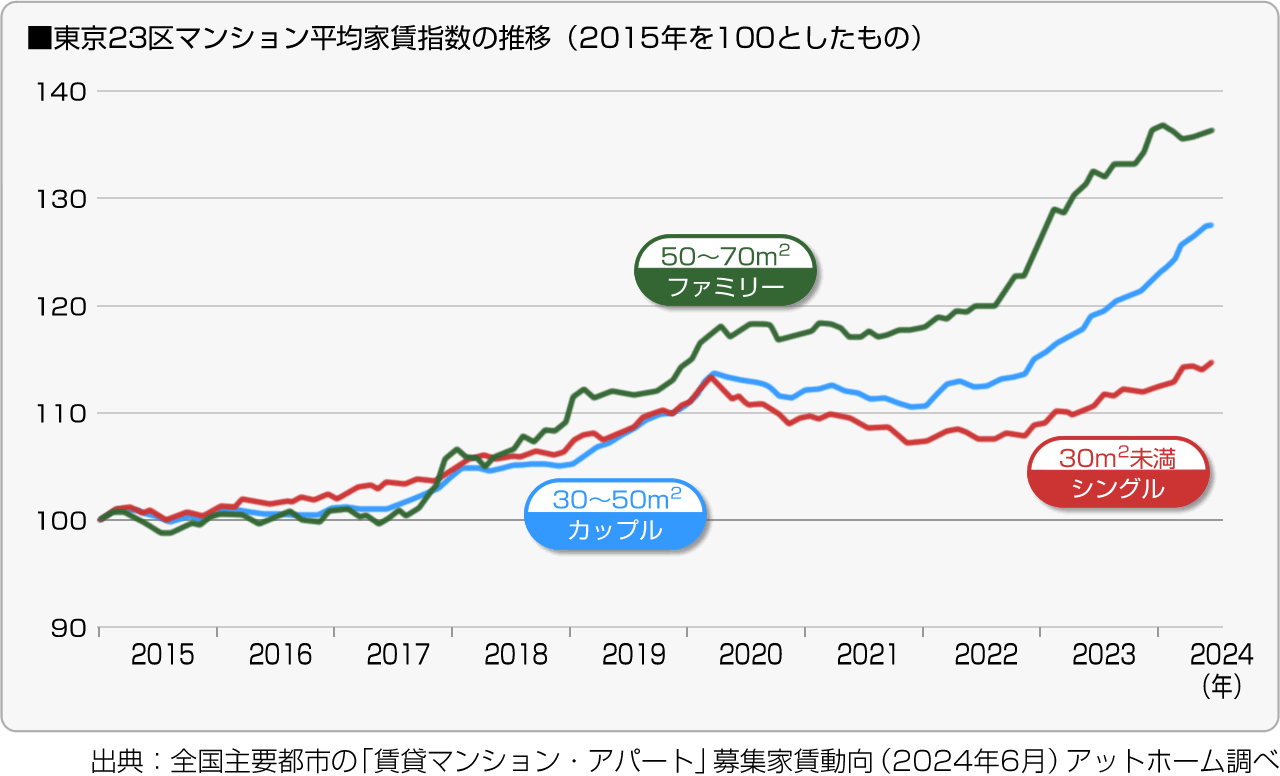
インフレ時の「借入金」は、将来価値が実質的に目減りします。冒頭、インフレ時に現金が目減りすると言いましたが、借入金に当てはめても同じことがいえるのです。
しかも日本は低金利です。借入金に関しては、最も良い環境といえるかもしれません。
また、繰り返しになりますが、土地活用は収益だけではなく、相続対策としても有効です。
インフレ時には家賃も上昇し、借入金は実質的に目減りする。土地活用はプランニングさえ間違わなければ収益は確保できる。
■インフレ時の土地活用の注意点
─土地活用をする上での注意点はありますか?

小泉:賃貸経営は長期事業ですから、やはりプランニングや収支計画をしっかり行うことが大切です。日々の管理や空室のリスクにも対応しなければなりません。私の顧客の賃貸オーナーの方も空室が出ると心配で眠れないと言います。
今は賃貸住宅の管理・運営はプロに任せる時代だと聞きます。そういう意味ではパートナー選びが重要になってくるでしょう。立地の特性に合ったプランニング、日々の運営・管理を安心して任せられるパートナーを選ぶべきです。
また、建築費の高騰により採算が取りづらくなっているのも事実です。インフレ対策だけを目的にした土地活用を考えると躊躇してしまう賃貸オーナーもいるかもしれません。しかし、土地活用のメリットは、これまで話してきたようにそれだけではありません。
相続対策や長期の視点での資産運用など、土地活用の様々なメリットを総合的に判断して、土地活用をすすめていくことが重要になります。既に土地がある場合は、何もしないことのデメリットよりも積極的に土地活用したほうが、長期の資産運用や相続対策の観点からもメリットが大きいと思います。
土地活用は信頼できるパートナー選びが大切。土地活用は採算だけではなく、相続対策も含めた長期的な視点で計画する。
税務部門シニアマネージャー・資産税1課マネージャー/税理士