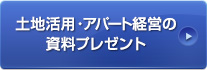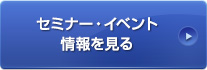相続税・贈与税の土地評価の算定基準となる路線価が、7月1日国税庁より発表されました。今回の路線価は2025年1月1日時点の公示地価をベースに算出されています。地価は上昇トレンドが強まり、今回の路線価にもその動向が顕著に表れています。三大都市圏の路線価とあわせて、地価上昇時に気をつけたい土地の相続対策について解説します。
路線価4年連続上昇、東京は全国平均の3倍 8.1%上昇
全国の平均変動率は4年連続の上昇で2.7%上昇率で、現在の計算方法になった2010年以降で最大の上昇率となりました。都道府県別に見ると東京都が8.1%の大幅上昇で、全国平均の3倍の伸び率です。報道では「東京一人勝ち」の見出しも見られました。
理由の一つが海外からの投資マネー。東京は世界的に見ると香港やニューヨークといった海外主要都市に比べて割安感があることは以前から言われていましたが、昨今の円安もあり、海外富裕層のマンション購入に拍車がかかっているようです。
また、人口の東京一極集中も、地価上昇の理由の一つで、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると2050年時点の人口が2020年より多いのは東京都のみということです。
東京周辺の都市も地価は上昇しています。全国の都道府県庁所在地の最高路線価地点のトップは、さいたま市大宮駅前で11.9%上昇、2位は千葉県の千葉駅前11.2%上昇です。千葉県はコロナ禍でも下落せず12年連続の上昇です。
都道府県別の上昇率トップ3は、東京都(8.1%上昇)の他、インバウンドが回復しリゾート開発が進む沖縄県(6.3%上昇)、「天神ビッグバン」と呼ばれる大規模再開発が進む福岡県(6.0%上昇)でいずれも前年より上昇幅が拡大しています。
税務署ごとの最高路線価の上昇率1位は長野県白馬村(32.4%上昇)で、インバウンド需要の高いスキーリゾート地です。2位は北海道富良野市(30.2%上昇)、3位東京都台東区(29.0%上昇)、4位岐阜県高山市(28.3%上昇)で、いずれもインバウンドの回復が大きな要因です。

東京圏の動向-インバウンドと住宅需要で23区が上昇をけん引
東京国税局内での上昇率1位は、昨年に続きインバウンド回復の象徴でもある浅草「雷門通り」で29%上昇、コロナ前の30%には及ばなかったものの前年より上昇率は12.3ポイント拡大しました。浅草は平日でも外国人観光客で賑わい、ホテルの稼働率も上がり、開業も相次いでいます。
2位は再開発でイメージが一新され、住みたい街としても人気の北千住駅西口駅前広場通りが26%上昇。3位は中野駅北口駅前広場で24.7%上昇。中野は中野サンプラザ跡地の開発計画が白紙になりましたが、駅周辺では10事業が進行中で人口も増加しています。
影響は周辺のエリアにもあり、中野と同じ中央線の荻窪(21.6%)、高円寺(20.1%)が4位、5位となり、住宅需要が旺盛です。東京圏の上昇率トップ10を見ると7位鎌倉(19%上昇)、9位千葉県習志野市津田沼(18.3%上昇)以外はすべて東京23区の地点でした。
また、全国の県庁所在地の最高路線価地点のトップはさいたま市大宮駅前(11.9%)です。
全国最高価格で話題の銀座中央通り「鳩居堂前」は8.7%の上昇となり、路線価格は40年連続の全国トップ。1平方メートルあたり4,808万円、過去最高額を更新しました。


名古屋圏の動向-中心部はやや足踏み、周辺エリアの上昇が鮮明に
今回三大都市圏で唯一上昇率の上げ幅が下がったのが愛知県でした。4年連続上昇したものの上昇率は前年の3.2%から2.8%となり、上昇幅がやや鈍化しました。
名古屋国税局内での上昇率1位は、昨年に続き岐阜県高山市「上三之町下三之町線通り」(28.3%上昇)。全国で見ても4位の上昇率です。高山はアクセスが悪いのにもかかわらず古い街並みが人気の観光地で、去年1年間に高山市内に宿泊した外国人の数は76万9,000人余り、コロナ禍前の2019年と比べ25.7%増え、過去最多となるなど、インバウンドが急回復しています。今後もJR高山駅周辺では宿泊施設の進出が相次いでいます。
2位も観光地で熱海(15.2%上昇)がランクインしました。こちらは東京からのアクセスも良く、インバウンド回復と共に人気が再燃しています。
名古屋駅周辺や中心街の栄は路線価が横ばいで、大規模な開発は続いているものの、需要に減速感が出ています。
一方、上昇が鮮明なのは名古屋中心部への通勤に便利な周辺部のエリア。3位の地下鉄今池駅(名古屋市千種区)は14.3%の上昇。今池では駅直結のマンション高級の建設が進んでいます。4位の刈谷駅北口駅前広場通り(9.3%上昇)でも、駅周辺で再開発が進み、5位の一宮市千歳通り(9.1%上昇)は、名古屋のベッドタウンとして住宅需要が旺盛です。

大阪圏の動向-万博開幕、インバウンド回復で上昇トレンド強まる
大阪圏の上昇率トップは、東京圏・名古屋圏同様にインバウンド回復によるエリア、兵庫県豊岡市のJR城崎温泉駅前(24.2%)でした。
大阪府の上昇率は4.4%で、過去最高の伸び率となりました。最高価格は阪急うめだ本店前(3.2%上昇)で、路線価は1平方メートルあたり2,088万円で、令和2年(2,160万円)に迫る水準に回復し、大阪国税局管内では最高価格42年連続でトップです。大規模再開発が進むJR大阪駅北側「グラングリーン大阪(うめきた2期)」は、一部オープンし、2027年春に全体のグランドオープンの予定です。
2位の大阪市淀川区宮原3丁目(18.5%上昇)は新大阪駅近くで、駅周辺では将来のリニア中央新幹線の延伸を想定した再開発が動き出しているとのことです。
3位の大阪市浪速区難波中2丁目(17.9%上昇)は、なんばパークス近くで、インバウンド向けの民泊需要が好調で、地価を押し上げています。
4位の大阪市西区「四つ橋筋(肥後橋駅)」(17.6%上昇)、5位の大阪市福島区「なにわ筋(福島駅)」(15.9%上昇)は共にJR大阪駅に近く、住宅需要が旺盛なエリア。上昇率はやや鈍化しているものの、マンション開発が進んでいます。
大阪では万国博覧会が開催中ですが、会場・夢洲(ゆめしま)への玄関口の一つ「大阪市港区(大阪メトロ弁天町駅)」近くでは、ホテルやマンションなどの建設が相次ぎ路線価は11%上昇でした。万博の後は統合型リゾート(IR)の開業も予定されていますので、今後も上昇を続ける可能性は高いと見られています。
京都もインバウンドの影響で、四条通(15.0%上昇)をはじめ、7地点が二桁の上昇で、上昇幅も拡大しています。

路線価上昇で気をつけたい土地の相続対策、3つのポイント
路線価は、相続税・贈与税の土地評価の算定基準となります。この10年、コロナ禍を除いて路線価は上昇しています。そこで、路線価上昇で気をつけなければならない土地の相続対策について解説します。
ポイント1:遺産分割の見直し・資産の棚卸しが必要
相続財産に土地が含まれている場合は、10年前、5年前に考えていた相続対策の見直しが必要です。例えば、10年前"公平"に分けたつもりで遺産分割し、遺書を残したとしても、土地を含んでいれば、今は"不公平"になっている可能性が高いと思われます。土地を含んでいる場合は、今の評価で資産を再評価し、遺産分割を考え直す必要があります。
また、相続税評価の土地の評価額と遺産分割を考える上での土地の評価額は違いますので注意してください。賃貸住宅などの収益物件の土地の実勢価格は大きく上昇していると思われます。
ポイント2:相続税の負担が増加! 納税資金の確保が必要
相続税は原則、現金納付です。相続税の負担が大きくなれば、その分の納税資金が必要となります。繰り返しになりますが、資産の棚卸しをすると共に、今、相続が発生したとしたら納税額がいくらかかるのかも試算する必要があります。
納税資金対策としては生命保険がよく活用されています。また、賃貸住宅などの収益物件は、収益が相続財産として蓄積されていきます。賃貸住宅を生前贈与することも一つの方法で、その収益分が相続人に移転され、収益を納税資金として蓄えることができます。
ポイント3:土地の有効活用で資産評価を圧縮
相続対策の一つが財産評価の引き下げです。特に土地は利用状況によって評価が大きく変わってきます。最も有効な対策が土地を有効活用し、賃貸住宅を建てることです。賃貸住宅の建っている土地は「貸家建付地」となり評価が大きく下がります。例えば、評価額1億円の更地に建築費1億円の賃貸住宅を全額ローンで建設すると評価は約8割圧縮できます。
![[例]更地評価額1億円、借地権割合70%、借家権割合30%の土地に、1億円(全額ローン)で賃貸住宅を建設](/maison/chiebukuro/report/2023/07/img/graph-5.gif)
また、気をつけたいのが「空き家の実家」、または「空き家となる予定の実家」です。事実上、評価を下げる手段がありません。早い段階で、賃貸併用住宅に建て替えるなどの対策が必要です。
路線価の上昇は、相続税への影響が大きいのは間違いありません。土地オーナーは、地価の上昇や相続税評価のルール改正など環境の変化にうまく対応して、資産管理をしていく必要があるでしょう。今後も地価動向、経済動向に注視していきたいと思います。