介護保険の特定疾病|65歳未満が介護保険を適用できる条件を解説
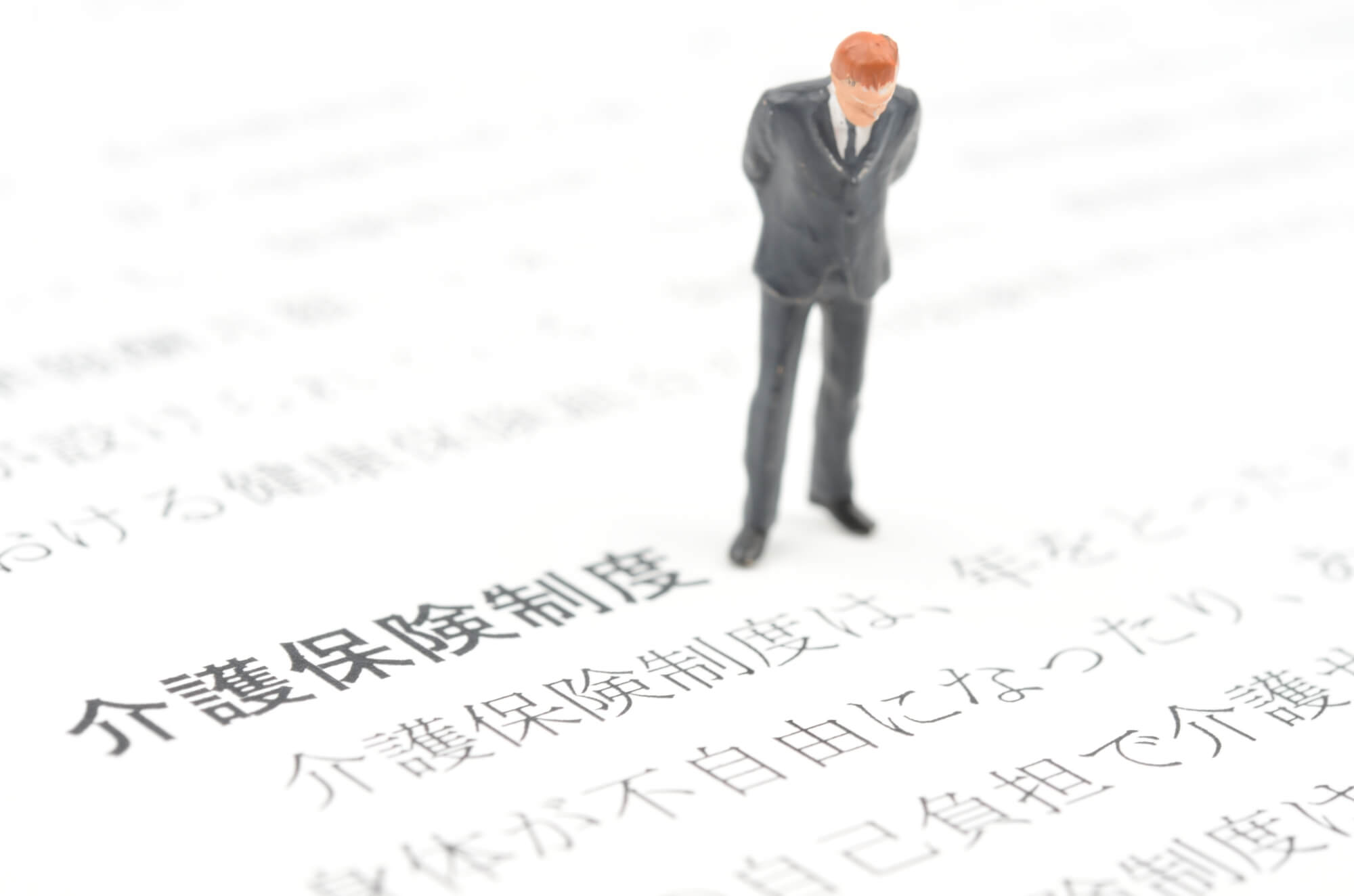
介護保険による介護サービスは、第2被保険者である65歳未満の方でも利用することが可能です。
ただし、介護保険加入者であれば誰でも利用できるというわけではなく、65歳未満の方が利用するには一定の条件を満たさなくてはなりません。
そのため、適用条件についての理解を深めておくことが大切です。
本記事では、介護保険の適用条件や、介護保険の特定疾病の種類、特定疾病を発症した際にすべきことなどについて解説します。
介護保険の適用条件
先述の通り、介護保険は誰でも利用できるものではありません。以下のいずれかの条件に該当する場合にのみ介護保険を利用できます。
- ・65歳以上の高齢者:原因を問わず、日常生活で介護や支援が必要な場合に適用
- ・40歳~64歳の方:介護保険が対象とする特定疾病が原因により、介護や支援が必要な場合に適用
介護保険の適用を受けるには、自治体から要介護認定(要支援を含む)を受ける必要があります。要支援または要介護と判断された場合は、介護サービスの利用が可能となります。
介護保険の特定疾病は全部で16種類
厚生労働省の「特定疾病の選定基準の考え方」によると“特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生じる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である”とされています。
- ・65歳以上の高齢者に多く発生しているものの、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められるなど、罹患率や有病率(類似の指標を含む)などについて加齢との関係が認められる疾病であり、その医学的概念を明確に定義できるもの
- ・3~6カ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病
それでは、16種ある特定疾病を詳しく見ていきましょう。
がん
がん患者は介護が必要な状況に陥ることが多いため、特定疾病の対象となっています。ただし「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。」という条件が付けられています。これは末期がんの方が対象となることを指しており、進行がんのみでは特定疾病にあたらない場合があります。
関節リウマチ
関節リウマチは、関節の炎症が原因で関節の変形や機能障害を引き起こしてしまう病気です。移動や日常生活動作に制限が生じるため、介護保険の特定疾病に指定されています。進行すると、日常生活が困難になることもあります。
筋萎縮性側索硬化症
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、筋肉の萎縮や衰弱が進行することで、呼吸や話すことや、食べることが困難になるため、介護が不可欠な状態になります。そのため、介護保険の適用条件である特定疾病として認められています。
後縦靭帯骨化症
後縦靭帯骨化症は、脊椎にある後縦靭帯が骨化し、脊髄を圧迫する病気です。これにより、歩行困難や痛みが生じ、日常生活に支障をきたすことで介護が必要となる場合があります。
骨折を伴う骨粗鬆症
骨粗鬆症は、骨密度が低下し、骨がもろくなる病気です。特に高齢者は運動能力が低下して転倒しやすく、それが原因で骨折した際に骨折後の介護が必要となるため、介護保険の適用条件である特定疾病に含まれています。
初老期における認知症
初老期における認知症とは、65歳未満で発症する認知症のことです。記憶障害や判断力の低下が見られます。進行した場合、日常生活に支障をきたし、介護が必要となる場合が多く、特定疾病に指定されています。
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
これらの神経変性疾患は、運動機能や平衡感覚に障害を引き起こします。その結果、体の自由が制限され、転倒などの危険も伴うため介護が必要となります。症状が進行すると、日常生活の介助は不可欠です。
脊髄小脳変性症
脊髄小脳変性症になると、小脳や脊髄の変性により運動失調が引き起こされ、歩行や日常動作が困難になります。進行した場合は、介護が必要となることが多いため、介護保険の適用条件である特定疾病に指定されています。
脊柱管狭窄症
脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなり神経が圧迫されることで、腰痛や下肢のしびれ、歩行困難などの症状を引き起こします。重症化すると日常生活で介護が必要となる場合もあります。
早老症
早老症とは、通常の加齢現象が若年期に起こる病気で、身体機能が著しく低下し、日常生活動作に支障をきたします。そのため、介護が必要になることが多く、特定疾病に認められています。
多系統萎縮症
多系統萎縮症とは、複数の神経系が徐々に機能を失う病気で、歩行や排泄、呼吸などに障害を引き起こします。進行性の病気であることから、介護が必要となる場合が多いです。
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
糖尿病による合併症は、神経障害や腎機能低下、視力障害を引き起こし、日常生活に支障をきたします。進行した場合は、介護が必要になることが多く、介護保険の適用条件である特定疾病に認められています。
脳血管疾患
脳血管疾患は、脳梗塞や脳出血などが原因となり、半身不随や言語障害などが生じる病気です。半身不随や言語障害などの症状が起こると、日常生活において介護が必要となることが多いため、特定疾病に指定されています。
閉塞性動脈硬化症
閉塞性動脈硬化症は、動脈が狭くなり血流が悪くなることにより、歩行困難や潰瘍などの障害を引き起こします。進行した場合は、日常生活での介護が必要となることがあります。
慢性閉塞性肺疾患
慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは、肺の機能が低下し、息切れや呼吸困難が生じる病気です。進行した場合、日常生活で介護が必要になることが多いため、特定疾病に指定されています。
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
変形性関節症は、膝や股関節の関節が変形し、痛みや動作障害などを引き起こす病気です。両側の関節に重度の変形が見られる場合においては、日常生活に支障をきたすことから、介護が必要となることがあります。
特定疾病を発症した場合にすべきこと
40~64歳の方で特定疾病を発症し、身の回りの生活に不自由さを感じるようになった場合、最初に行うべきは「要介護認定の申請」です。お住まいの市区町村の窓口で申請すると、認定調査員による訪問調査や医師の意見書をもとに、要支援または要介護度が決定されます。
要介護認定の結果により、介護保険サービスを利用できるようになります。サービスを利用するためには「サービス計画書(ケアプラン)」の作成が必要です。介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談し、生活状況や介護の必要性に応じた計画を立てた上で、適切なサービスが選ばれます。
これにより、必要な介護や支援を的確に受けられる体制が整うでしょう。
まとめ
介護保険は、65歳以上の高齢者や40~64歳の特定疾病に該当する方が対象です。まずは自治体に要介護認定を申請し、認定結果に基づいてケアプランを作成しましょう。
40~64歳の方が適用条件となる特定疾病には、がんや関節リウマチ、糖尿病性合併症など16種類があり、該当者は介護保険サービスを利用できます。適切に介護サービスを利用することは、生活の質を維持しながら安心して日常生活を送るための重要な手段です。
また、住環境も介護生活の質を大きく左右する要素の一つです。旭化成ホームズの「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」では、快適で安全な居住空間を提供しています。ヘーベルVillage(ヴィレッジ)は、耐震性やバリアフリー設計などを備えているため、高齢者や介護が必要な方でも安心して暮らせます。また、介護サービスの導入も容易で、入居者同士のコミュニティ支援も充実しています。そのため、孤立を防ぎ、安心感と社会的なつながりを持ちながら、心豊かな暮らしを実現できます。
このように、ヘーベルVillage(ヴィレッジ)は身体の負担を軽減させるのみならず、安心と快適さを提供する理想的な住まいといえるでしょう。安心できる環境での生活をご希望でしたら、ぜひヘーベルVillage(ヴィレッジ)にお問い合わせください。












