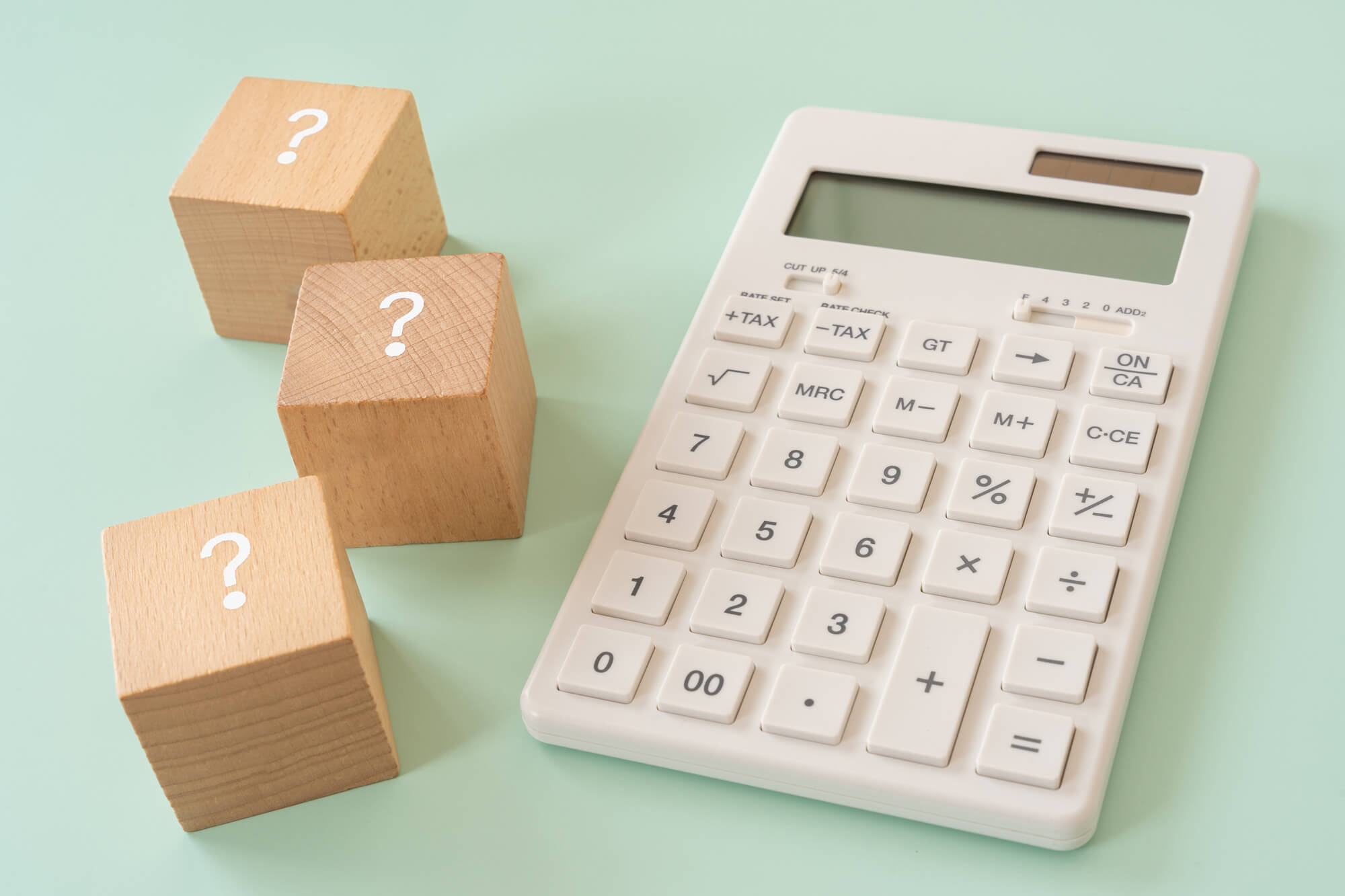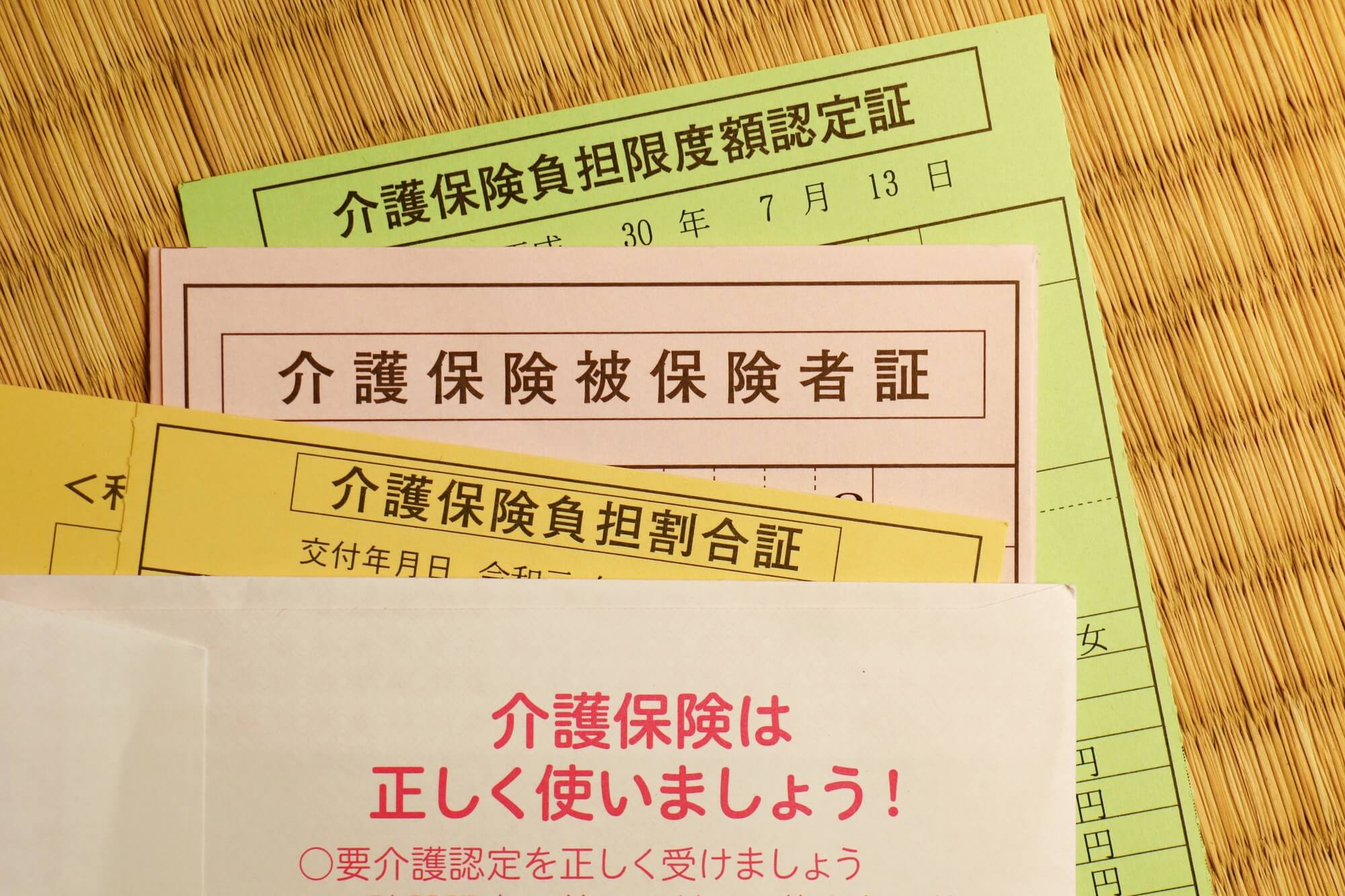介護保険は何歳から?保険料支払い、サービスを利用できる年齢を解説

介護保険は、一定の条件を満たした方が必ず加入しなければならない社会保険制度ですが、何歳から加入しないといけないのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
条件を満たしているにもかかわらず保険料が未払いの場合、後でトラブルに発展してしまうため、正しい知識をしっかり身に付けておくことが大切です。
この記事では、介護保険料の支払いを開始する年齢と介護サービスを利用できる年齢、介護保険で押さえておくべきポイントなどを解説します。介護保険について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険料の支払いは何歳から?
介護保険料の支払い義務は、介護保険料の被保険者になった方に発生します。介護保険の被保険者とは、65歳以上の方(第1号被保険者)もしくは40~64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)のことです。
参照:厚生労働省「介護保険制度について」
つまり、40歳から介護保険の被保険者となり、基本的には40歳になった月から各種医療保険料と一緒に介護保険料を納めることになります。
第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定や要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。一方で、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護(支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。介護サービスを利用できる条件は、次の見出しで説明いたします。
介護サービスを利用できるのは何歳から?
介護サービスは、介護保険に加入している方であれば誰でも利用できるというわけではありません。利用できる条件としては、介護保険の被保険者であるだけでなく、第1号被保険者・第2号被保険者のそれぞれの受給条件を満たした場合のみ介護サービスを利用できます。
では、具体的にどのような条件を満たす必要があるのか詳しく見ていきましょう。
第1号被保険者
第1号被保険者は年齢が65歳以上の方です。市区町村に要介護認定の申請を行い、要介護状態または要支援状態と認定された場合のみ、介護サービスを利用できます。
要支援状態は要支援1~2、要介護状態は要介護1~5の合計7つに分類されます。ただし、要介護認定を申請しても必ず認められるわけではありません。
要介護認定の結果、日常生活において介護や支援が特に必要ないと判断された場合は、結果が自立(非該当)となります。その場合、年齢条件を満たしていても、介護サービスを利用できないため注意してください。
第2号被保険者
第2号被保険者は40~64歳までの方です。以下のいずれかの特定疾病が理由で要介護(要支援)認定を受けた場合のみ、介護サービスを利用できます。
- ・がん(回復の見込みがない状態)
- ・関節リウマチ
- ・筋萎縮性側索硬化症
- ・後縦靭帯骨化症
- ・骨折を伴う骨粗鬆症
- ・初老期における認知症
- ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- ・脊髄小脳変性症
- ・脊柱管狭窄症
- ・早老症
- ・多系統萎縮症
- ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- ・脳血管疾患
- ・閉塞性動脈硬化症
- ・慢性閉塞性肺疾患
- ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
上記に該当しない場合は、介護サービスを利用できないため注意してください。
介護保険で押さえておくべきポイント
介護保険についての理解を深めるには、以下のポイントを押さえておくことも大切です。
- ・介護保険料の金額
- ・介護保険料の納付方法
- ・介護保険を利用する手順
- ・介護保険料を滞納した場合のペナルティ
それぞれのポイントを詳しく解説します。
介護保険料の金額
介護保険料の金額は、被保険者が第1号被保険者なのか、第2号被保険者なのかによって異なります。
第1号被保険者の場合は、年齢・収入・家族の状況などによって介護保険料の計算方法が変わります。項目ごとの基準は地域や年度によって異なるため、正確な金額を把握したい方は、居住地域の介護保険課に問い合わせましょう。
なお、前年度の所得が少ない、あるいは世帯に住民税を課されていない方がいる場合では、介護保険料の金額は通常より少なくなります。
第2号被保険者で健康保険や組合保険に加入している方は、給与や賞与の合計額に基づき、保険独自の計算方法を使って介護保険料を算出します。算出した介護保険料は、勤務先との折半となるため、負担を軽減できるという特徴があります。
一方、国民健康保険に加入している方は、前年の所得や同じ世帯に属する被保険者の人数に基づき介護保険料を算出します。介護保険料は、全額自己負担となるため注意してください。
介護保険料の納付方法
介護保険料の納付方法に関しても、被保険者が第1号被保険者なのか、第2号被保険者なのかによって異なります。
第1号被保険者の場合、年金の受給額が年間18万円以上であれば、各自治体によって年金から天引き(特別徴収)されます。年間18万円未満であれば普通徴収となり、各自治体からの納入通知書もしくは口座振替によって納付します。
第2号被保険者の場合には、公的医療保険の保険料とともに納付します。会社員であれば、職場の健康保険に加入しているため毎月の給与から健康保険料と併せて介護保険料が天引きされます。国民健康保険に加入している自営業者などは、国民健康保険料に介護保険料が上乗せされる仕組みとなっており、通常通り国民健康保険料を納めていれば問題ありません。
介護保険を利用する手順
介護保険を利用する際は、以下の手順で手続きを進める必要があります。
- 1. 要介護認定を申請する
- 2. 市区町村による認定調査を受ける
- 3. 要介護認定を受ける
- 4. 介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する
- 5. 介護サービス事業者を選択して利用を開始する
介護保険サービスの利用を希望する場合は、まず各自治体の窓口で要介護(要支援)認定の申請をしなくてはなりません。その後、各自治体の認定調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を調査します。また、各自治体は主治医に意見書の作成を依頼します。
調査で得られた情報と主治医の意見書の内容に基づき、コンピューターで一次判定を実施します。その後、二次判定で各自治体の介護認定審査会が一次判定の結果に基づき、要介護度の判定をします。
結果の通知を受けた後は、地域包括支援センターやケアマネジャーが介護サービス計画書(ケアプラン)を作成し、介護サービスの利用を開始できます。
介護保険料を滞納した場合のペナルティ
被保険者になった場合、介護保険料は基本的に必ず納めなくてはなりません。もし介護保険料を滞納した場合は、一定期間を過ぎると延滞金が発生します。
また、1年以上滞納するとサービスの利用費用の支払いについて、本来1~3割の自己負担分のみの支払いから、一度10割分の費用を支払い、後から自己負担分以上に支払った金額が返還される償還払いに変更され、1年6カ月以上滞納すると利用者負担を引き上げられてしまいます。
最終的には財産の差し押さえといった強制徴収措置がとられる可能性もあるため、介護保険料の滞納が原因でペナルティを受けないように必ず納付しましょう。
まとめ
介護保険料の支払い義務は、被保険者になった時点で発生します。被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれますが、40歳を迎えた時点で第2号被保険者となるため、実質40歳から介護保険料の支払い義務が生じることになります。
また、介護保険料を支払ったからといって、必ず介護サービスを利用できるわけではありません。要介護認定や要支援認定で一定の要件を満たす、もしくは特定疾病が原因で要介護認定を受けたなど、定められた条件に該当する方のみが利用できます。
将来的に介護サービスを利用する状況になっても、焦らずに対応できるように介護保険の仕組みを今のうちから正しく理解しておきましょう。
加齢に伴い生活に不安を抱くようになった場合には、シニア向け賃貸住宅も選択肢の一つです。
ヘーベルVillageは、シニア向け安心賃貸住宅を提供しています。シニア向け安心賃貸住宅は、駆けつけサービス・健康や暮らしをサポートする相談サービス・看護師による健康相談・医療機関の紹介サービスなど、さまざまなサポートが充実しています。
自立しながら安心して老後を暮らしたいという方は、ぜひ旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。