注文住宅の間取りの決め方とは?考える流れや12の注意点を紹介
「注文住宅の間取りで失敗したくない」
「注文住宅の間取りは、何から決めるべきかわからない」
家づくりの際、間取りの決め方を悩む方は多いでしょう。
本記事では、注文住宅における間取りの決め方や流れ、注意点を紹介します。失敗を防ぐためのコツも解説していますので、ぜひ家づくりの参考にしてください。
この記事でわかること
- 注文住宅の間取りを決める流れと決め方
- 注文住宅の間取りを決める際の注意点
- 注文住宅の間取り決めで失敗しないためのコツ
ヘーベルハウスが運営する注文住宅の情報ナレッジサイト「THINKHAUS」では、家づくりに関するオーナーの声や、間取りの事例を多数の画像や動画で紹介しています。多くの事例を見ることでイメージが膨らみ、希望する間取りを見つけやすくなるでしょう。
また、簡単な質問に答えるだけで、理想の間取りが見つかるシミュレーターも利用可能です。
以下のリンク先で会員登録できますので、間取りを検討する際にぜひご活用ください。
注文住宅で間取りを決める流れ

注文住宅の間取りを決める流れは、以下のとおりです。
どのような順番で決めていくのか解説するので、間取りを決める際の参考にしてください。
1. 間取りの事例を探して希望のイメージを膨らませる
最初に間取りの事例を探して、希望するイメージを膨らませておきます。注文住宅の事例をあまり見ていない場合、どのような間取りができるのかなど、わからないことが多くあります。
理想の暮らし方によって、必要な間取りは変わるため、事例を参考にイメージを膨らませる作業が必要です。
なお、理想の暮らし方の例としては、以下のようなものがあります。
- 共働きのため、家事は手早く終わらせたい
- リビングはゆったりした空間で、家族が集まれる場所にしたい
- 外からの視線を気にせず、子どもが屋外で元気に遊べる空間が欲しい
ハウスメーカーなどの住宅会社は、ホームページやSNSで事例を紹介していることがほとんどです。紹介されている事例を見て、自宅に取り入れたい間取りのアイデアが見つかったら、画像を保存しておきましょう。
ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINKHAUS」なら、無料で会員登録するだけで、画像や動画で紹介されている豊富な事例を閲覧できます。
さらに、家族構成など質問に答えるだけで理想の間取りがわかるシミュレーターを利用できるサイトです。
会員登録は以下のリンク先で行えますので、理想の間取りを見つけるためにご活用ください。
2. モデルハウスなどで実際の間取りを見学する
実際にハウスメーカーのモデルハウスや展示場を見学し、どのような間取りが家族に必要かイメージを固めましょう。
事例の画像や動画を見るだけでも、間取りのイメージはできます。しかし、画像や動画だけでは、以下のようなことは掴みきれません。
- 日当たりや風通し
- 部屋の広さの感覚
Webサイトやカタログで情報収集しているだけでは掴みきれない感覚が、モデルハウスや展示場では体感できます。
モデルハウスや展示場を見学すれば、実際の住宅の間取りをじかに確認できるため、イメージを掴みやすいでしょう。
3. ハウスメーカーに間取りを相談する
希望が固まったら、ハウスメーカーに間取りを相談します。
最初にチェックした事例の画像や理想の暮らし方を基に、ハウスメーカーに希望の間取りを伝えましょう。伝えた内容をベースに、ハウスメーカーに間取りと見積りを作成してもらう流れです。
理想の暮らしができる注文住宅になるよう、この段階では希望を漏れなく伝えるように意識します。
4. 提案された間取りを調整する
ハウスメーカーに提案してもらった間取りを確認し、必要があれば調整を相談します。
間取りを提案してもらったら、理想の暮らし方ができるか、生活に不便そうなところが無いかチェックしましょう。家族の生活動線がどのようになるかを意識すると、暮らしやすい間取りかが見えてきます。
後から間取りを変更することは難しいため、気になる箇所がある場合は、すぐにハウスメーカーに相談が必要です。
注文住宅における間取りの決め方

注文住宅の間取りの具体的な決め方は、以下のとおりです。
具体的な間取りの決め方を、順番に見ていきましょう。
1. 家族構成に応じた部屋数を考える
最初に、同居する家族の人数や世帯数を基に、必要な部屋数を考えます。
子ども2人の4人家族なら、LDKや浴室など共同スペースの他、夫婦の寝室と子ども部屋で最低でも2部屋が必要です。二世帯住宅の場合は、完全分離か一部共有なのかなど同居のスタイルによって必要な部屋数が増減します。
一緒に生活する家族の人数や親子世帯で同居するかどうかなど、状況に応じて必要な部屋数は変わります。
2. 必要な住宅の面積を把握する
国土交通省によると、豊かな暮らしを実現するために必要な住宅の面積は、次の計算式で把握できます。
都市部は「同居する家族の人数×20㎡+15㎡」、都市部以外の地域なら「同居する家族の人数×25㎡+25㎡」です。
世帯構成別に応じた住宅に必要な面積は、以下のように計算できます。
| 世帯構成 | 都市部の場合 | 都市部以外の地域の場合 |
|---|---|---|
| 子ども2人の4人家族 | 95㎡ | 125㎡ |
| 子ども3人の5人家族 | 115㎡ | 150㎡ |
| 親世帯と子ども2人の子世帯の6人家族 | 135㎡ | 175㎡ |
※国土交通省の「住生活基本計画(全国計画)/P30 別紙3 誘導居住面積水準」を参照し、都市部は「同居する家族の人数×20㎡+15㎡」、都市部以外の地域は「同居する家族の人数×25㎡+25㎡」の計算式を用いて算出
世帯構成や注文住宅を建てる地域に応じて、必要とされている住宅の面積は変わります。しかし、ライフスタイルや生活動線などで本当に必要な住宅の面積は変わるため、計算結果は参考程度に実際の広さを検討しましょう。
参照:国土交通省「住生活基本計画(全国計画)/P30 別紙3 誘導居住面積水準」
3. 住宅の構造を考える
敷地面積や希望する暮らし方に合った、住宅の階数などの構造を考えましょう。敷地面積や希望する暮らし方によって、最適な住宅の構造は変わります。
平屋で各部屋にゆとりを持たせたい場合、広い敷地面積が必要です。土地の広さに限りがある場合でも、3階建てにするなどの工夫で、間取りにゆとりのある注文住宅を実現できます。
建築制限のある土地などはプロの視点での意見が欠かせないため、ハウスメーカーに相談しながら住宅の構造を決める必要があります。
4. 部屋の配置を考える
希望の暮らし方や住宅の構造を基に、部屋の配置を決めていきましょう。各部屋がどこにあれば家族が暮らしやすいか考えることで、最適な部屋の配置がわかります。
効率よく家事をこなしたい場合、水廻りやLDKを近くに配置すれば、家事動線がよくなるでしょう。しかし、二世帯住宅の場合は、生活音に配慮するためにLDKの近くに水廻りを配置できない可能性が考えられます。
同じ住宅の構造でも、家族の暮らし方によって最適な部屋の配置は変わります。
5. 家族の生活動線を基に部屋の配置を調整する
最後に、家族のリアルな生活動線を基にして、部屋の配置を調整します。
最初に考えた部屋の配置で、家族の生活動線がどのようになるかチェックします。生活しにくそうな動線の場合は、部屋の配置を変えて、再び生活動線のチェックが必要です。
注文住宅を建てた後は、簡単に間取りを変更できないため、納得できるまで部屋の配置を検討しましょう。
注文住宅の間取りを決める際の12の注意点

注文住宅の間取りを決める際、忘れずにチェックしたい注意点は、以下のとおりです。
注目するべきチェックポイントは何か、順番に説明します。
1. 自然光の取り込み
自然光を取り入れられる方角や時間帯は、間取りを決める前に必ずチェックしたいポイントです。
隣家や周辺の建物との位置関係で、自宅が影になる時間や方角が変わります。自然光をどれくらい取り込めるかは、リビングを配置する位置や窓の大きさを決めるための重要な情報です。
どれくらい採光できるかによって、日中の部屋での過ごしやすさに影響するため、入念にチェックしましょう。
2. 住宅全体の風通し
住宅全体の風通しがよいかどうかも、忘れずにチェックしましょう。
一つの空間に対して、二つ以上の窓を方向がわかれるように配置すると、風が通りやすくなります。このように、窓の配置の仕方で風通しのよさは変わりますが、専門知識が無ければイメージしにくい部分です。
実際どのような住環境になるかシミュレーションできるハウスメーカーに相談すれば、風通しのよさなどイメージしやすくなります。
たとえばヘーベルハウスの場合、独自の住環境シミュレーションとして「ARIOS(アリオス)」を用意しています。隣家の位置も入力できて、敷地周辺の状況を科学的に検証するため、その土地に合った正確なシミュレーションが可能です。
風通しや採光をシミュレーションできる他、日当たりのよい場所や日射によって熱がこもりやすい場所がわかるため、自然の恵みを空間に取り入れやすくなります。
3. 防音と遮音
防音性と遮音性も、必ずチェックしましょう。寝室など静かに過ごしたい場所で外部からの音が大きいと、騒音に悩まされることになるため、防音性や遮音性は重要です。
たとえば交通量が多い道路沿いに注文住宅を建てる場合、外部からの音に対する防音性・遮音性が欠かせません。これは、寝室を道路から離れた位置に配置するなど、間取りの工夫で対策できます。
また、LDKや水廻りなど生活音が出やすい部屋と寝室を近くに配置しないことも、防音と遮音の対策方法の一つです。
4. 屋外からの視線
住宅の中が丸見えにならないよう、屋外からの視線を遮るプライバシー性の確保も重要です。窓や玄関ドアを開放した際、住宅の中が見えすぎない間取りになっているかチェックしましょう。
2階にリビングを配置すると、屋外からの視線を遮りやすくなります。また、目隠しになるよう外構に塀やフェンスを設置することも、プライバシー性を確保する方法です。
5. 家族の生活動線
家族一人ひとりの生活動線のチェックは、間取りを決める際に必ず実施しましょう。
生活動線は、暮らしやすさに直結する重要なポイントです。誰か一人の動線だけでなく、家族全員の生活動線がよくなるように間取りを工夫することで、暮らしやすさが変わります。
6. 住宅の外観
間取りは、注文住宅の外観にも影響する要素です。どのような間取りを選択するかによって建物の形が変わることがあるからです。
ただし、注文住宅の外観は間取りの他、以下の事項も影響します。
- 屋根の形状
- 外壁材や屋根材の種類と色味
- 設置する窓の形状やサイズ、配置
建物の形がどのようになるか、ハウスメーカーに確認しながら、住宅の外観も含めて間取りを決めましょう。
7. 宅内からの景観
住宅内に眺望のよい場所がある場合、景観を楽しめるようにすることも間取りを決める際のチェックポイントです。
公園など緑が見える箇所にアウトドアリビングを設置したり、窓を大きくしたりすれば、宅内から景観を楽しめます。プライバシーを確保したい場合は、2階バルコニーの設置など間取りを工夫することで、景観を楽しめる間取りが実現できるでしょう。
8. 住宅内の安全性
住宅内で危険な場所が無いか、安全性のチェックも重要です。
高齢者や小さな子どもがいる場合、とくに安全性の配慮が欠かせません。安全性を確保するための対策方法は、以下のとおりです。
- 転倒の原因にならないよう段差をなくす
- 階段から転落防止のため、隙間を子どもの頭が通り抜けない11cm以下にする
- 階段に手すりを設置する
- 車いすを使用できるよう通路を広めにする
- 介護に備えて浴室やトイレを広めにする
浴室やトイレは、坪数を大きくすることで介護のスペースを確保できます。トイレの場合、便器と壁の間に50cmの間隔を設けることが目安です。
9. 収納スペース
十分な収納スペースを確保できているかも、間取りを決める段階でチェックするべき項目です。
長く生活していくと、自然に物が増えるでしょう。注文住宅を建てる時点で収納したい物の量よりも多めの収納スペースを確保すれば、物が増えてもスッキリした状態を維持できます。
10. 家具の配置
どの家具をどこに配置したいか、間取りと一緒に決めておきましょう。
間取りを決めきってから家具の配置を検討する場合、希望の家具を設置できないことが考えられます。テレビ台や収納棚など、どの部屋にどのような家具を設置するか間取りとあわせて検討すれば、必要に応じて間取りを調整できます。
11. コンセントの設置位置
コンセントの設置位置も、間取りを決める前にチェックしたい項目です。
コンセントがどこに設置されているかは、生活のしやすさに影響します。ドライヤーやホットプレートなど、家電製品を使用する場所の近くにコンセントが無いと、不便さを感じかねません。
生活動線をチェックする中で、家電製品を使用する場所にあたりをつけてコンセントが必要な位置に目星をつけましょう。なお、コンセントは多めに設置しておくと、延長コードの使用で配線が露出せず安心です。
12. 将来のライフスタイルの変化
将来、ライフスタイルがどのように変化するかを考えて、間取りを決めることも重要です。
家族のライフステージによって、ライフスタイルは変わっていくものです。ライフスタイルが変われば、暮らしやすい間取りも変化します。
子どもの独立や親世帯の同居など、将来のライフスタイルの変化を見据えて間取りを決めることで、長く快適に生活できるでしょう。
注文住宅の間取りを考える際に失敗しない2つのコツ

注文住宅の間取りを考える際に失敗しないためのコツは、以下の二つです。
どうすれば間取り決めで失敗しないのか、一つずつ説明します。
1. 生活動線を念入りにシミュレーションする
念入りに生活動線をシミュレーションすれば、間取りを決める段階での失敗を避けられます。
間取りを決める際、生活動線の考慮は重要事項です。家事動線を短くしたい場合は、キッチンや浴室など水廻りを近くに配置するなど、日々の家事を行うときにシミュレーションすることで最適な間取りがわかります。
家族全員の生活動線を念入りにシミュレーションして、暮らしやすい間取りを決めましょう。
生活シーン別に、どの場所でどのように行動するか考えてみましょう。たとえば、食材の買い出しから帰宅した際の行動は、以下のようになります。
● 手洗い・うがい
● 冷蔵庫またはパントリーに食材を保管
最初に手洗いとうがいをしたいので、玄関の近くに手洗い場や洗面台があるとスムーズに行動できます。次にキッチンやパントリーにすぐ移動できると、距離が短く効率的です。
頭の中でイメージすることが難しい場合は、図面に線を引いてみるとわかりやすいでしょう。
2. 絶対に外したくない設備や空間を決める
「これだけは譲れない」という絶対に欲しい設備や空間を決めることで、失敗を避けられます。
間取りの参考にするために多くの事例を見ると、すべて自宅に取り入れたくなるかもしれません。しかし、土地に限りがある場合など、希望するすべての設備や空間を導入するのは難しいこともあります。
必ず取り入れたい設備や空間を決めて残すことで、取捨選択が必要になった場合でも失敗したと感じにくくなるでしょう。
間取りの決め方のポイントを押さえて理想の注文住宅を手に入れよう

間取りの決め方のポイントを押さえられれば、理想の注文住宅を手に入れられます。
実際に間取りを決める際、以下の項目を念入りにチェックすることで、理想の家づくりが可能です。
- 自然光の取り込み
- 住宅全体の風通し
- 防音と遮音
- 屋外からの視線
- 家族の生活動線
- 住宅の外観
- 宅内からの景観
- 住宅内の安全性
- 収納スペース
- 家具の配置
- コンセントの設置位置
- 将来のライフスタイルの変化
まずは、多くの事例に触れて、どのような暮らし方がしたいか希望をイメージしてみましょう。
注文住宅の事例の閲覧には、ヘーベルハウスが運営する情報ナレッジサイト「THINKHAUS」をご活用ください。
画像や動画で多数の事例を掲載している他、オーナーが家づくりに込めた想いなども紹介しています。同じ想いを持ったオーナーが建てた注文住宅の事例なら、参考にしたい間取りが見つかりやすいでしょう。
また、我が家に最適な間取りがよくわからない場合は、プランのシミュレーションをご利用ください。簡単な質問に順番に答えていくだけで、最適な間取りがわかります。
以下より会員登録し、理想の注文住宅づくりの参考にしてください。
この記事の監修者
ヘーベルハウスのコラム編集部です。
家づくりに役立つ情報をわかりやすく発信中。
注文住宅の基礎知識から、設備や間取りの情報まで、
理想の住まいづくりをサポートします。
関連記事
人気記事
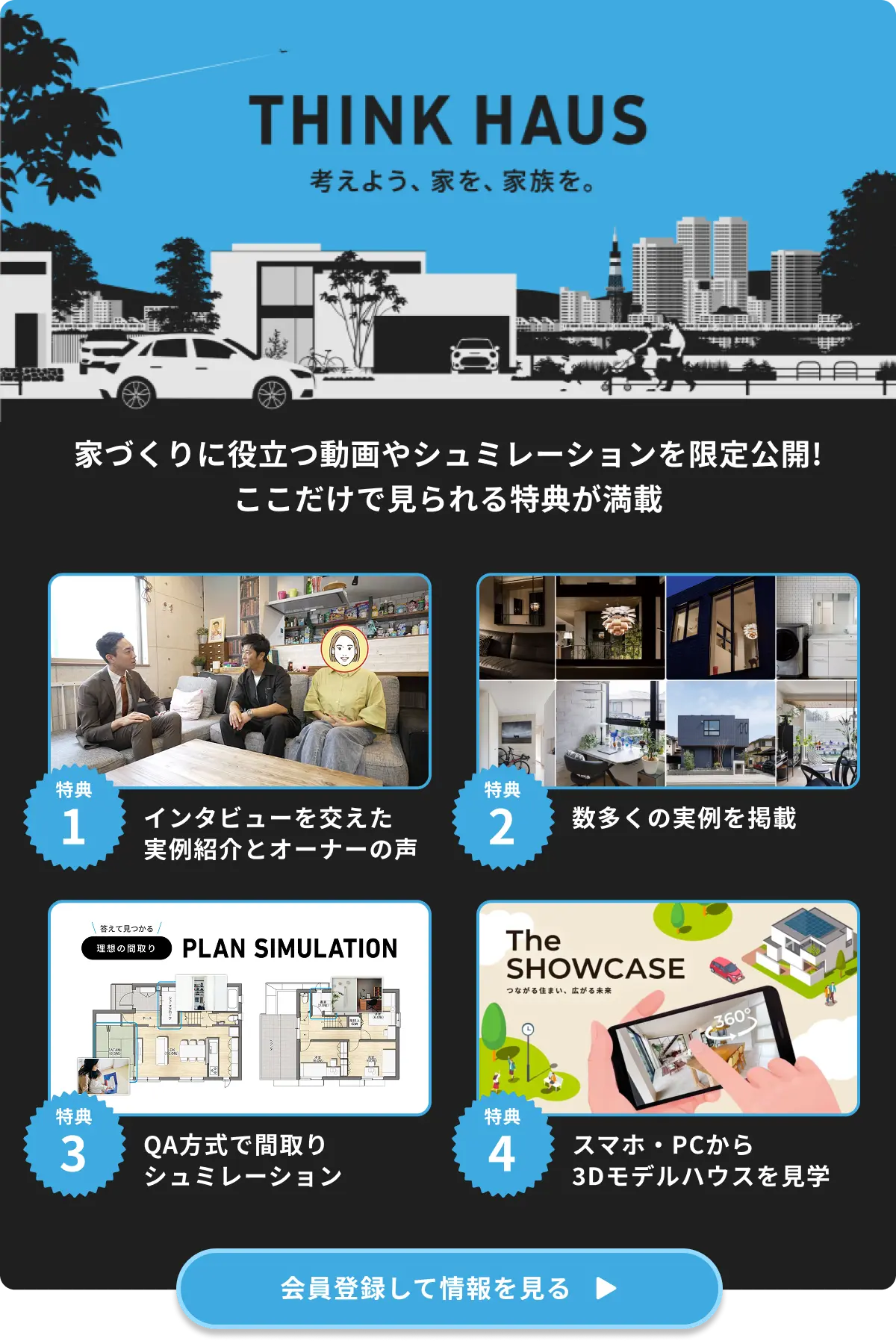











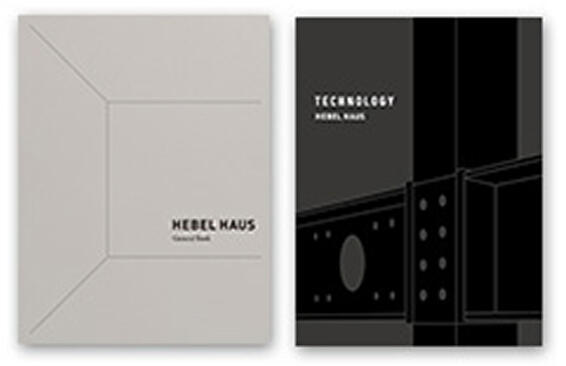
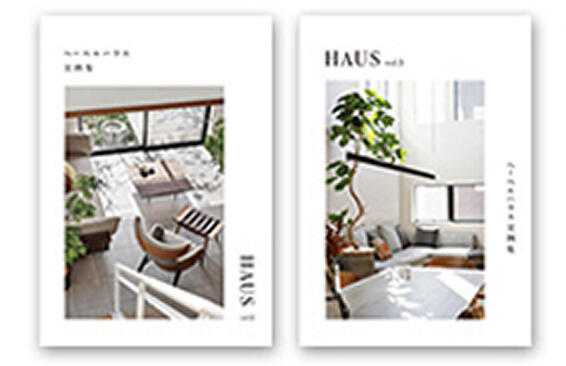

イメージを言葉だけで伝えるのは、難しいですよね。まずは、事例をたくさん見て「この間取りを真似したい」と、思える画像を保存しましょう。
次に、「なぜこの間取りを真似したいと思ったのか」「この間取りでどういう暮らしをしたいのか」などを伝えていただくと、希望の間取りが伝わりやすいだけでなく、土地の制約などで実現が難しい場合に代替案を提案しやすくなります。