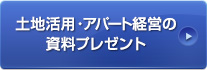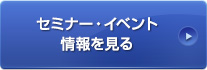9月は防災月間です。南海トラフ地震の発生確率は"今後30年以内に80%程度"、いつ起きてもおかしくないと言われています。また、近年夏場になると被害をもたらす"線状降水帯"は予測が難しく、いつ発生するか分かりません。賃貸住宅でも入居者の防災意識は高まり、自然災害への防災・減災に備えなければなりません。今回は過去の大震災の教訓を踏まえ、賃貸住宅の防災対策を考えます。
オーナーも被災者、都市型災害での教訓
賃貸住宅が密集する大都市での大地震で思い出されるのは、「阪神・淡路大震災」です。すでに30年が経過しましたが、風化させることのないよう、あらためて教訓を学ぶ必要があります。
「阪神・淡路大震災」では多くの家屋が全・半壊し、住宅の耐震の重要度を認識させられました。そして、大都市で気をつけなければならないのが、二次災害の「火災」です。三大都市圏では、まだまだ木造住宅密集地域が多く存在し、都市防災のウイークポイントとなっています。東京都をはじめ、各自治体では不燃化への対応が喫緊の課題で、助成制度を創設し木造から耐火構造への建て替えを推奨しています。
ここで「阪神・淡路大震災」でヘーベルメゾン・ハウスのオーナーが得た教訓を考えたいと思います。
大規模な震災の場合、オーナー自身も被災者となります。ヘーベルメゾンに被害はなくても、ご自宅が大きな被害を受けているケースもありました。そんな中、あるヘーベルメゾンのオーナーは入居者の安否を気遣い、被災した木造アパートの入居者を、これから入居者募集をかける予定だった新築のヘーベルメゾンに住まわせるという心温かい対応をされました。
被災したオーナーたちが口をそろえて言うのは「コミュニティと防災への意識」が大切ということです。オーナーの一人は、当時を振り返り「万が一の時、何をすべきか、またどういうことが起こりうるのか、シミュレーションしたり、心の準備をしたりしているだけでも随分違う」と言います。つまり、「共助」「自助」への備えが減災へとつながるのです。
都市型災害では、耐震性と二次災害の「火災」に気をつける。木造住宅等の不燃化が必要。そして、「共助」「自助」への備えが減災につながる。
孤立させない-コミュニティで共助を促す
「阪神・淡路大震災」ではオーナーが言うように"コミュニティ"の大切さが教訓として注目されました。災害時、多くの人命を救ったのは、消防隊や自衛隊だけではなく、コミュニティ、つまり近所の人々による「共助」が大きかったと言われています。
しかし一般的な賃貸住宅では、近所づきあいが少なくコミュニティもありません。「東日本大震災」では、単身者向けの賃貸住宅が孤立する例もあったと言います。
大地震発生時は、耐震性の高い建物では「在宅避難」が推奨されています。「在宅避難」を可能とするためには、それをサポートする設備が必要です。
例えば、共用部に太陽光発電と蓄電池を設置した「防災ステーション」では、停電時にも使える非常用コンセントがあり、スマートフォンの充電や、テレビ・ラジオからの情報収集、電気ポットによるお湯の確保などが可能となります。特に乳幼児やペットのいる入居者にとっては、大きなサポートとなり「共助」を促進することができます。
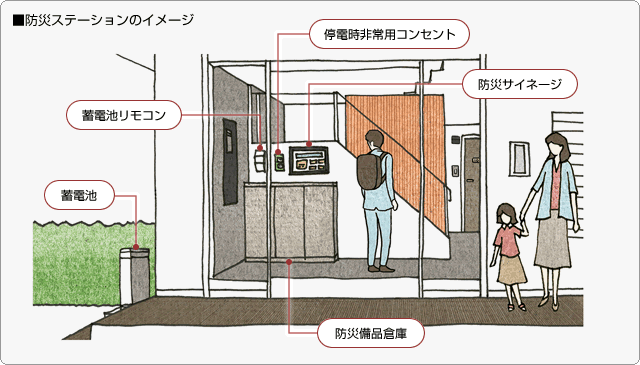
防災パッケージについては、バックナンバー「防災力で賃貸住宅の付加価値を高める」でも解説しています。ご覧ください。
また、近年では賃貸住宅であってもゆるやかなコミュニティが形成される"コミュニティ賃貸住宅"が人気です。例えば、ペット共生型賃貸住宅、子育て支援型賃貸住宅、女性限定賃貸住宅、シニア向け賃貸住宅などです。
共通の趣味やライフスタイルを通じて、入居者同士のゆるやかなコミュニティが生まれ「共助」を促します。
コミュニティ賃貸住宅については、バックナンバー「コミュニティと賃貸住宅の防災力」でも解説しています。ご覧ください。
賃貸住宅であっても、在宅避難をサポートする設備やコミュニティがあると「共助」を促すことができ、防災力が高まる。
備えが大切-防災への意識(自助)を呼びかける
「自助」については、まずは入居者に対して注意喚起を呼びかけることが求められます。
掲示板の活用や、チラシ、パンフレットの配布があります。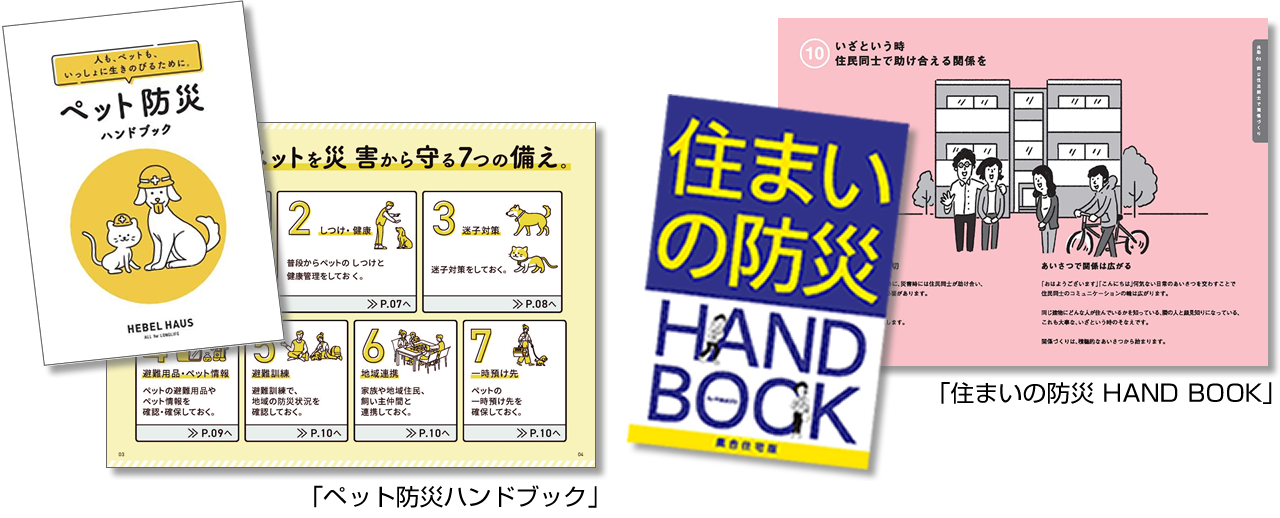
近年の線状降水帯による集中豪雨についても注意が必要です。猛暑のおり、つい窓を開けたまま外出すると、雨が室内に浸入し、水浸しになる可能性があります。また、ベランダの排水口や側溝にゴミが詰まっていると、ベランダがあっという間にプール状になり、あふれた水が室内に浸入することもあります。日常の清掃を怠らないよう入居者への呼びかけが必要です。入居者への注意喚起は、管理会社と相談して行うのがよいでしょう。
「自助」を促す居室の設備としては、転倒や落下の恐れのあるタンスを収納できる「集中収納」、「ウォークインクローゼット」、備蓄ができる大きめの収納「パントリー」があります。壁面に家具固定用の下地補強をしておくことも一つの方法です。(壁面に「家具固定OK」のプレートで表示)
「自助」を促すには、入居者への注意喚起が必要。備蓄ができる収納の他、家具固定用の下地補強も有効。
早期復旧-従来保険の補償対象外もカバーする災害保険
賃貸住宅の防災力とは入居者の「命」「暮らし」を守ること。そして、災害後も安心して住み続けられ、賃貸経営が継続できること。つまり、災害後の「復旧力」が重要になります。
自然災害からの復旧に備えておきたいのが、火災保険・地震保険です。ほとんどのオーナーが加入していると思いますが、「阪神・淡路大震災」の被害状況を見ても分かるとおり、耐震性のある建物の場合、地震による建物自体の損傷は軽微なものが多く、その場合は保険の補償の対象外となる事が多いです。
例えば地震保険では、地震によるエントランスや屋内共用廊下などのクロスの破れは補償対象外です。また水害などで床下浸水した場合、火災保険の特約で給湯器などの機械設備は補償されるケースもありますが、汚水が流れ込むこともあり、その後の土壌消毒まではカバーされません。
そこで、従来の火災保険(水災)や地震保険ではカバーされなかった災害修復工事をサポートする「ヘーベル災害保険」をヘーベルハウス・ヘーベルメゾンのオーナー様限定で開発しました。
この保険は、今加入している保険にプラスして加入することができます。軽微な損傷とはいえ修復費用はかかりますので、経営に影響する修復費の支出を抑えることができ、災害に対する復旧力を高めることができます。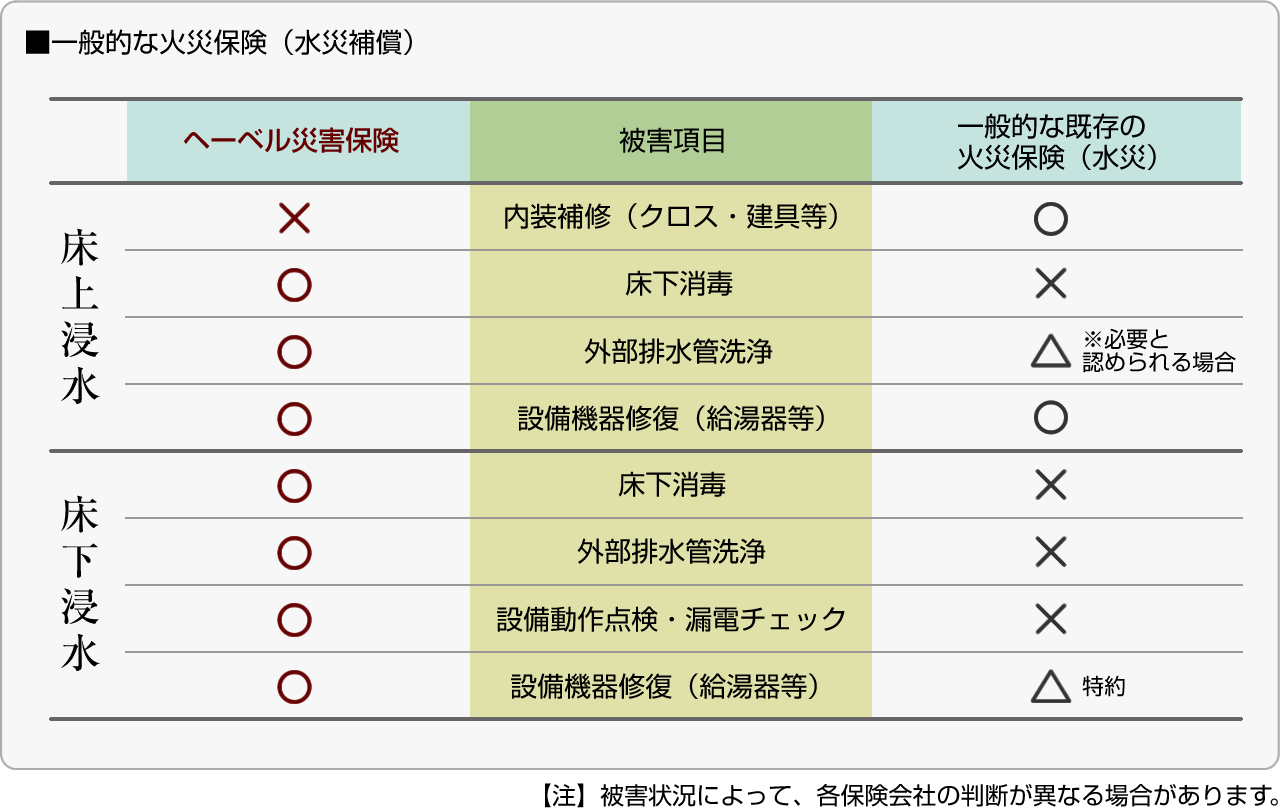
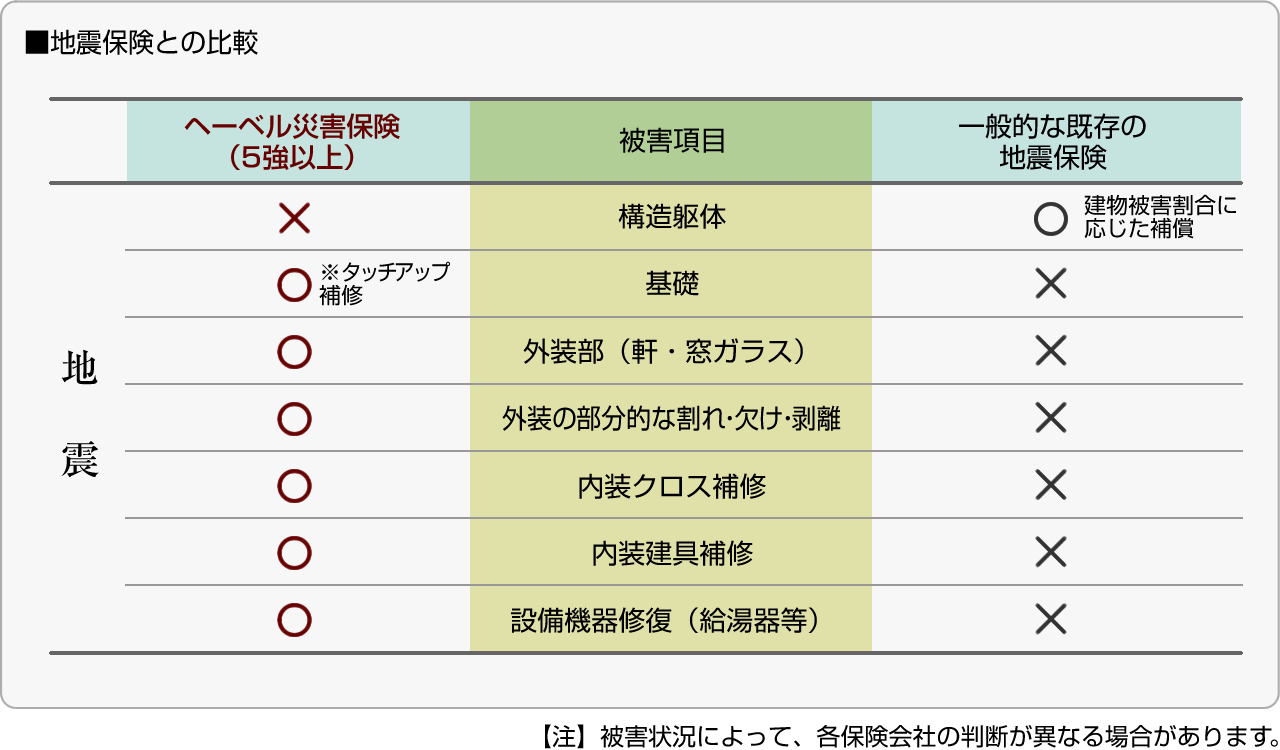
「ヘーベル災害保険」の詳細についてはコチラをご覧ください。
賃貸住宅の防災力を高めるには、災害後の「復旧力」も重要。従来の保険に加え、軽微な損傷も対象になる保険の活用が有効。