相続税対策として、自宅の土地評価額が330m2まで8割減額される「小規模宅地等の特例」があります。大きな節税効果がありますので、ぜひ活用したいところですが、その要件が税制改正で厳しくなり、使えるケースが限られています。どういうケースで使えるのか、どうしたらうまく活用できるのかを解説します。
同居の要件とは? 生活実態が問われる!二世帯住宅では登記に注意!
小規模宅地等の特例が適用できる土地であれば、仮に土地評価額が1億円の場合2,000万円まで減額になり、相続の課税対象からも外れる可能性があります。そもそも、なぜこれほど大きな評価減があるのか、まずはこの特例の目的を知っておくことが大切です。
自宅は同居する相続人にとって、相続後も大きな生活の基盤になります。主な相続財産が自宅しかない場合、多額の相続税が課税されると自宅を売却するしかなく、生活の基盤を失ってしまいます。そうならないために、大きな評価減のあるこの特例があるのです。
小規模宅地等の特例を適用させるには、いくつかの要件があります。「同居していた配偶者」が相続する場合は、無条件に適用されます。しかし、問題は子世代へ受け継ぐ二次相続です。
その場合の大きな要件の一つに、亡くなった被相続人と「同居していたこと」があります。
この「同居」の要件について、詳しく見ていきます。
同居は実態として一緒に生活をしているかどうかがポイントになります。見せかけの同居は認められません。
例えば次のようなケースです。
・住民票だけを親(被相続人)の住所、つまり実家に移す。
・平日は別の住宅に住み、週末だけ実家に帰る。
・相続人だけが親の介護等で実家に戻り、相続人の家族は別に住んでいる。
税務署は、生活実態に関して周辺住人への聞き込みや郵便物の配達状況など、かなり入念に調べるようです。
また、同居で気を付けたいのは二世帯住宅です。
かつては、完全分離型の二世帯住宅は適用されませんでしたが、2014年1月1日以降は適用されるようになりました。ただし気を付けたいのが、どのように"登記"されているかです。同居の要件が登記で判断されるということです。
登記が「共有登記」であれば同居要件を満たしますが、「区分所有登記」の場合は同居要件を満たしません。
例えば、親の土地に完全分離型の二世帯住宅を建てた場合、登記が共有登記なら敷地全体に特例が適用できますが、親世帯と子世帯と別々に区分登記してしまうと、一次相続で配偶者が相続する場合は、親世帯の建物の割合分の敷地のみ適用になり、二次相続で子世帯が相続しても特例は適用されません。
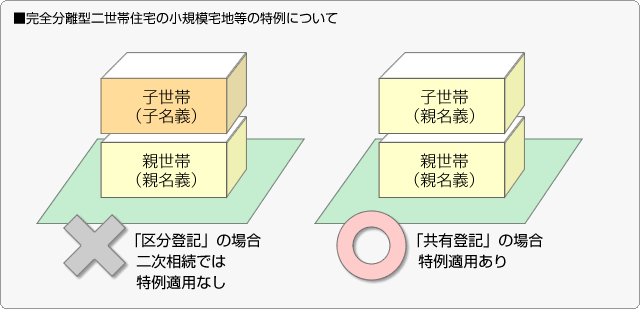
小規模宅地等の特例は、「同居」要件は生活実態が問われ、完全分離型の二世帯住宅で活用する場合は、登記に注意。区分登記ではなく共有登記にしないと二次相続では適用できない。
家なき子の要件とは? 要件の厳格化に注意!
二次相続では、子ども世帯は独立しているケースが多いと思われますので、小規模宅地等の特例は活用しづらいでしょう。ただし、同居していなくても「持ち家を持っていない」、つまり賃貸住宅に住んでいる、いわゆる"家なき子"の場合は、小規模宅地等の特例は適用されます。これは、単身赴任などやむを得ず、同居できなくなったことを想定した特例で、その要件にも注意が必要です。
家なき子の主な要件は次のとおりです。
1.被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。
2.相続開始時から相続税の申告期限まで、相続人がその土地を所有していること。
3.相続開始前3年以内に、相続人の配偶者や3親等内の親族やその親族と特別の関係がある法人等が所有する家に居住したことがないこと。
4.相続開始時に相続人が居住していた家屋を、過去に所有していたことがないこと。
要件3と4に関しては、2018年度の税制改正で厳格化されました。3に関しては、相続人の配偶者や子、叔父・叔母、またはそれらの人が役員になっている法人などが所有している家に住んでいても要件から外れることになります。
以前は"3年以内に本人または配偶者の持ち家に住んだことがないこと"というシンプルなものでしたが、不正に適用するケースが出てきました。例えば、持ち家に住んでいる相続人が、事前に自分の子ども(被相続人から見ると孫)に自宅を生前贈与し、一緒に住んでいるのにもかかわらず、登記上自身の持ち家ではないと見せかけるケースなどです。
現実的に考えれば、相続人である子どもが独立して持ち家を持てば、小規模宅地等の特例は使えなくなると考えておいたほうがよいでしょう。もちろん、相続開始3年前に持ち家を売って被相続人と同居する、または賃貸住宅で暮らせば特例は使えますが、それも家族がいれば難しいでしょう。
家なき子の要件は厳格化され、賃貸住宅に住んでいることが主な要件と考えること。
老人ホームに入居していた場合 特例の対象になる
昨今では、親が老人ホームなどに入居して、自宅が空き家になることもよくあります。原則、老人ホーム等へ入居しても自宅は親が住んでいたものとして特例の対象に含まれます。
前提条件として、「親が要介護認定または要支援認定を受けている」「自宅を賃貸していない」ことがあります。
また老人ホームは、老人福祉法等の法令の規定に基づいているもので健常者用の介護非対応の老人ホームは対象外です。仮に自宅を賃貸した場合は、小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地、つまり賃貸住宅の土地となり、評価額が8割減額ではなく、5割減額になります。
親が老人ホームに入所したあと、子ども家族が親の自宅に引っ越してきた場合はどうでしょう。この場合は、小規模宅地等の特例は適用できません。適用させるには、親が老人ホームに入所前に同居している必要があります。
親が老人ホームに入居していても、自宅は住んでいたものとして特例の対象になる。
自宅で特例が使えない場合の対策は?
人生100年時代の超高齢社会では、相続は老老相続が当たり前になり、すでにその傾向は現れています。被相続人が90代であれば、子ども世代の相続人は60~70代です。そうなると、独立して持ち家に住んでいるケースがほとんどで小規模宅地等の特例は使えないことが多いでしょう。相続税の課税対象が急増している要因の一つは、基礎控除の減額とあわせて小規模宅地等の特例の要件の厳格化で使えないことが増えているからだと思われます。
何も手を打たないと実家の相続は、相続税の負担が増すだけではなく、空き家となってしまうリスクがあります。
しかし小規模宅地等の特例をうまく活用する方法があります。特例は自宅だけではなく、事業用地や賃貸住宅の土地にも適用されます。賃貸住宅の場合の減額割合は8割ではなく5割ですが、それでも大きな節税効果があります。

活用法としては、親世代が元気なうちに、自宅を賃貸併用住宅に建て替える方法です。
自宅部分は小規模宅地等の特例が使えなくても、賃貸部分の割合に応じて、評価額が5割減額になります。
評価減が大きいだけに、小規模宅地等の特例が使えるかどうかは、相続税の負担に大きく影響します。賃貸住宅経営も一括借上げを活用すれば、安定した収益が得られ、納税資金対策としても有効です。また、実家の空き家対策にもなります。
いずれにせよ、早めの対策が必要です。専門家へ相談してみるのがよいでしょう。
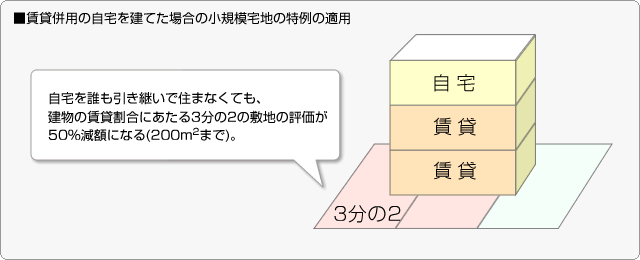
自宅の対策については、バックナンバー「実家を空き家にしないための賃貸併用住宅という選択-前編」「相続新時代! 4つのリスクとその対策」でも解説しています。
小規模宅地等の特例は賃貸住宅の土地にも適用できる。親世代が元気なうちに賃貸住宅併用の自宅に建て替えるという選択肢が相続対策や空き家対策には有効。



