化学装置材料の基礎講座
第19回 化学装置で発生した材料損傷・劣化や破損の解析を行う際の、基本的な手順を教えて下さい。
材料損傷等が顕在化した場合に、以下の手順での検討が必要です。
- 1.損傷サンプルを解析し、損傷形態を推定する。
- 2.推定された損傷形態に対応する使用条件(材料の種類や環境条件等)の情報を収集する。
- 3.以上の情報の整合性より、損傷発生機構や、その再発防止策を明確化する。その際に、損傷形態と発生条件に関連する公表情報を参考にする。
- 4.前項の検討で損傷発生機構が、明確にならない場合は、専門家を含めた調査や、必要に応じて再現試験等を行なう。これにより、損傷機構の解明や対応策を策定する。
以上の各項に関して、解説を加えます。
- 1.損傷サンプルから、外観観察や必要に応じて断面観察等の解析を行い、損傷形態を推定します。装置材料の損傷は、以下の様に分類されます。図1の下部の太線枠に、材料の損傷・劣化の形態名を示します。各形態には、その発生条件や機構の情報が関連付けられています。このため、発生した損傷・劣化の形態を明らかにすることにより、機構や対応策の推定が可能となります。この形態を推定するには、各形態特徴(形、色、変形程度等)をあらかじめ把握やそのためのデータベースの整備が必要です。損傷・劣化によっては、形態の推定に専門家との協力が必要となることがあります。この推定が可能な場合は、以下の2項に進めますが、この段階で、形態の推定が不可能な場合は、以下の4項に進みます。
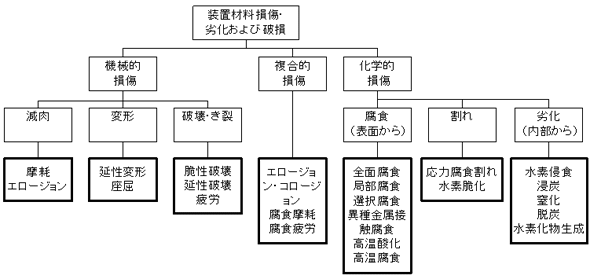
図1.化学装置材料の損傷系統図(太線の枠内に形態名)
- 2.前項の形態より推定される損傷機構に関連する、装置材料の種類や特性値(成分、熱処理、強度特性等)と、使用されていた環境条件(温度、化学成分等)、およびその期間などの情報を収集します。
- 3.以上の形態の推定と、それに関連して収集された情報の整合性を確認し、損傷機構の特定や適切な対応策を明確化します。整合性が得られた場合は、損傷機構が特定されますが、もし整合性が取れない場合は、次項に示す更なる検討が必要となります。
- 4.損傷・劣化サンプルの再度の解析、公開情報の調査、および必要により再現実験等を実施する必要が生じます。これらの結果を総合して、損傷機構の特定や再発抑制の対応を策定します。この検討を行うためには、専門家の参画が必須となります。
以上の検討の流れを、図2に示します。
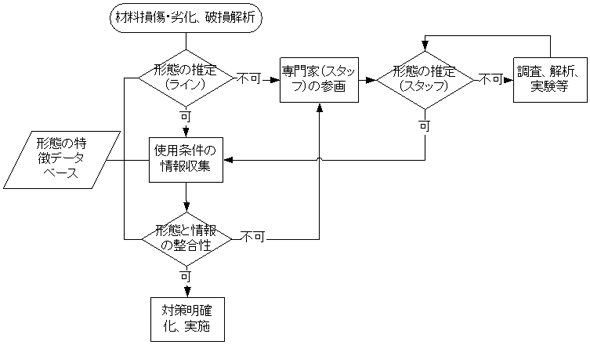
図2.材料損傷・劣化および破壊の解析の流れ