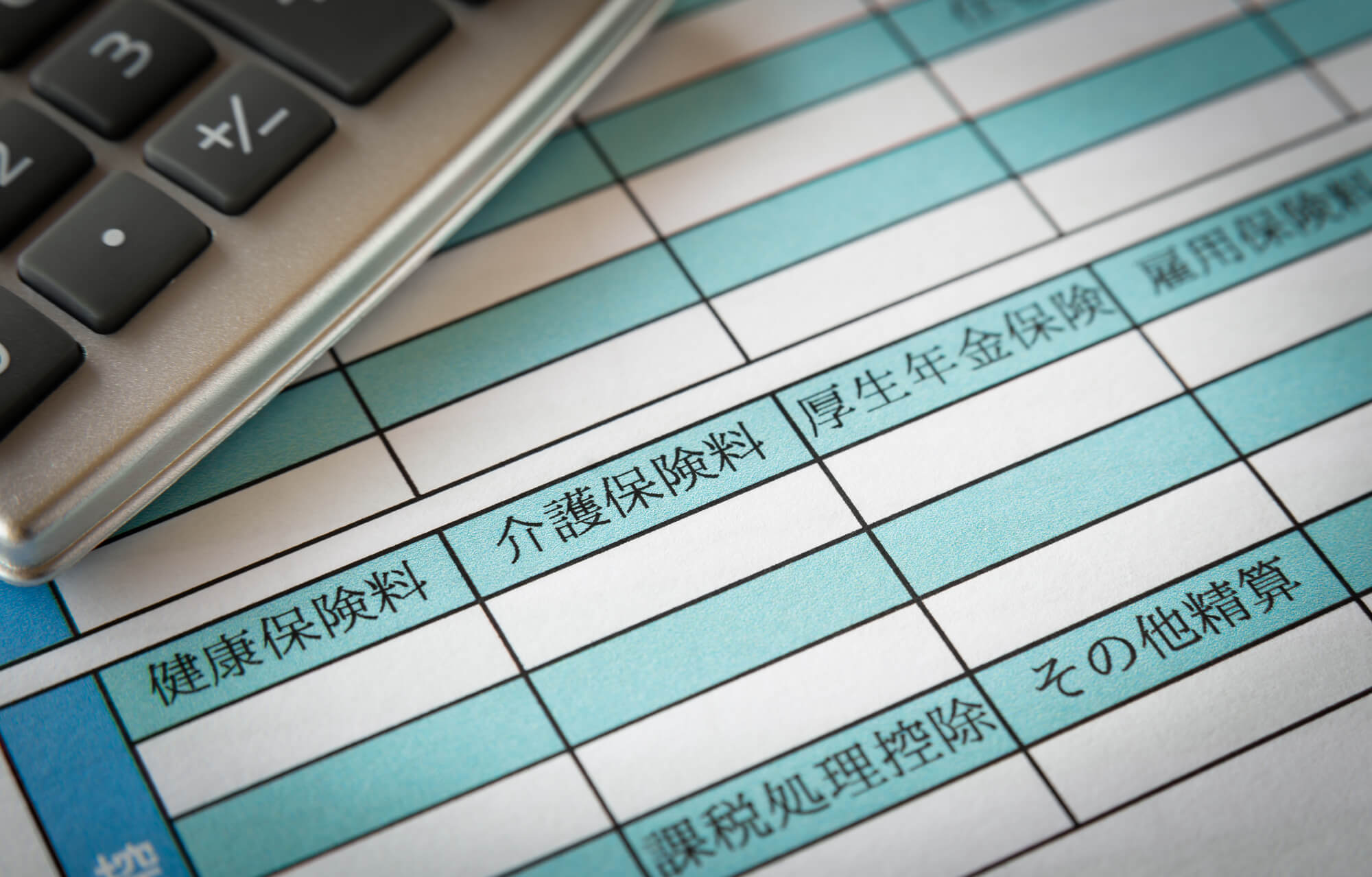介護保険料計算|加入対象者や負担割合、納付方法などを紹介
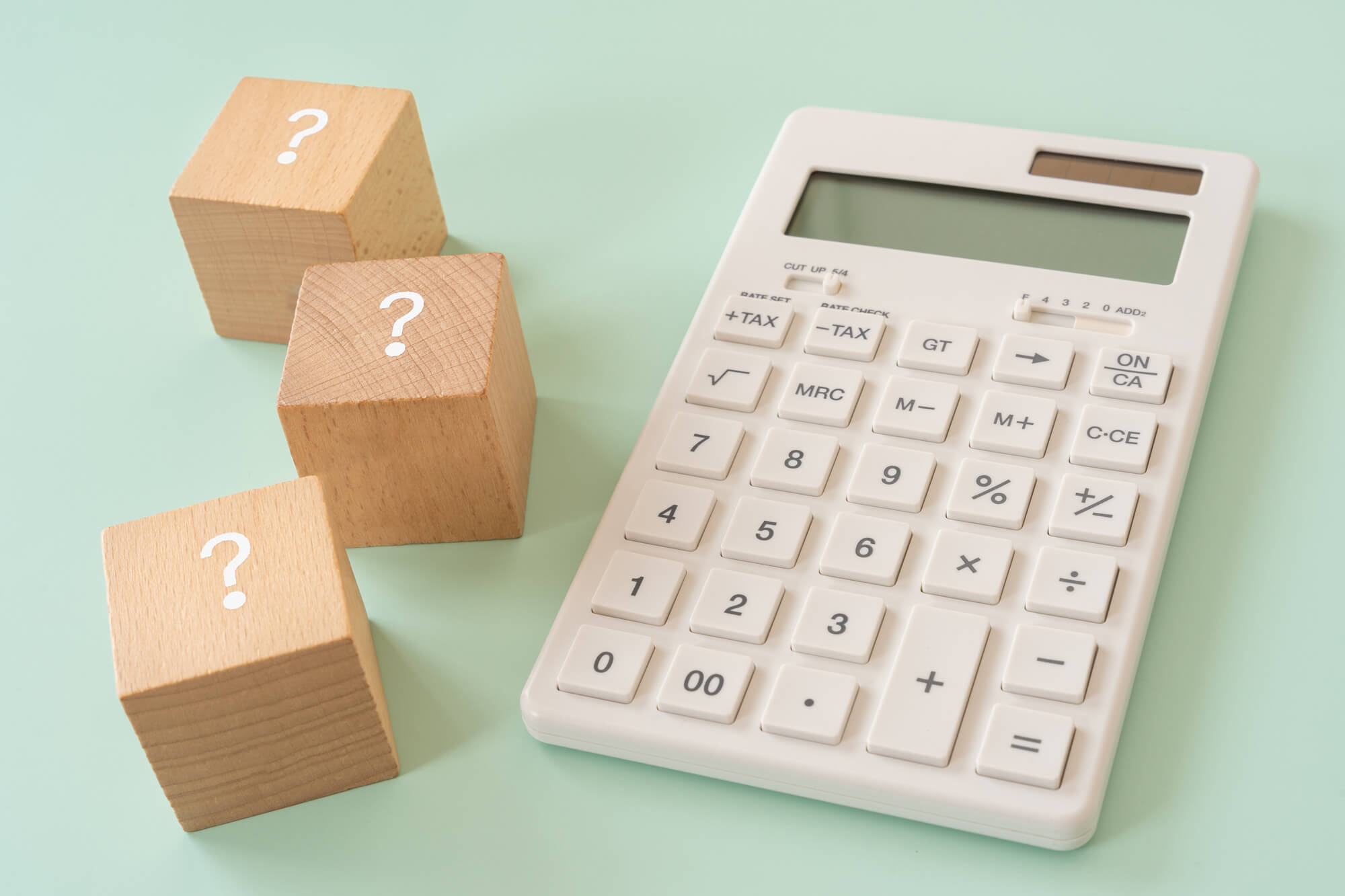
高齢者や一定の年齢以上の障害者が必要な介護サービスを受けられるようにするための公的保険制度である介護保険制度。
会社員の場合は、給与やボーナスから介護保険料が天引きされますが、いくら引かれるのか詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護保険料とは何なのか、計算方法、介護保険料で知っておくべきポイント・注意点などについて解説します。介護保険料の計算方法について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険料とは
介護保険料とは、日本の介護保険制度に基づき、40歳以上の国民が支払う公的保険料です。
介護保険制度とはどのようなもので、介護保険料はどのような方が負担するのでしょうか。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
高齢者を社会全体で支える仕組み
介護保険制度は、高齢化社会に対応し、高齢者が安心して暮らせるようにするための重要な仕組みです。
介護保険制度の基本理念は、高齢者を社会全体で支えるという考えに基づきます。高齢によって介護が必要になった場合に、家族だけでなく社会全体でその負担を分担し、支えることが目的とされています。
そのため、40歳以上の国民全員が介護保険料を支払う必要があり、徴収した介護保険料は、高齢者や障害者が必要な介護サービスを受けるための財源として使用されます。
介護保険料の被保険者は2種類
介護保険料の被保険者は、年齢に応じて以下の2種類に分けられます。
- ・ 第1号被保険者:65歳以上の方
- ・ 第2号被保険者:40~64歳の方
第1号被保険者は、要介護認定を受けた場合に介護サービスを利用できます。一方、第2号被保険者は、がんや脳血管疾患といった国が指定する特定疾病によって介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用することが可能です。
介護保険料の計算方法
会社員で給与から介護保険料を天引きされる場合は、計算方法が給与とボーナス(賞与)で異なります。
どのような計算方法で介護保険料が算出されているのかを詳しく解説します。
介護保険料の計算式
介護保険料の計算式は給与とボーナス(賞与)で以下のように異なります。
- ・ 給与の介護保険料:標準報酬月額×介護保険料率
- ・ ボーナス(賞与)の介護保険料:標準賞与額×介護保険料率
各項目について説明します。
標準報酬月額
標準報酬月額とは、給与所得者の介護保険料や健康保険料などを計算する基準となる月額報酬のことです。
この月額報酬は、従業員が毎月受け取る給与や手当に基づき計算されています。具体的には、基本給に加え、残業手当、通勤手当、家族手当などです。
これらの総額を一定の区分(等級)に分け、標準報酬月額として設定しています。標準報酬月額の設定は年1回見直されることが一般的で、4月~6月の給与に基づいて翌年度の報酬月額が決定されます。
標準賞与額
標準賞与額とは、ボーナス(賞与)に対して介護保険料や健康保険料などを計算する場合の基準額です。
賞与は通常の月々の給与とは別に支給されるもので、標準報酬月額とは別に計算されます。標準賞与額の計算は、支給された賞与額に基づき行われますが、上限が設定される可能性があります。
ボーナスに対しても適切な保険料を徴収するために設定されているのが標準賞与額です。
介護保険料率
介護保険料率とは、介護保険料を計算するための割合を表す数値です。保険料率は健康保険組合や共済組合といった保険者が定めます。国の介護保険制度全体の財政状況や医療費の動向などに応じて、毎年見直されることがあるという点に注意してください。
介護保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に介護保険料率をかけて計算します。例えば、標準報酬月額が30万円、介護保険料率が1.5%だと、30万円×1.5%=4,500円の介護保険料を支払う必要があります。
介護保険料で知っておくべきポイント・注意点
介護保険料についての理解を深めるためにも、以下の知っておくべきポイントや注意点を押さえておくことが大切です。
- ・ 介護保険料の負担割合
- ・ 介護保険料の納付方法
- ・ 加入手続きは不要
- ・ 介護保険料率は変化する
それぞれのポイント・注意点について詳しく説明していきます。
介護保険料の負担割合
介護保険料の負担割合は、人によって異なります。例えば給与所得者の場合、介護保険料は健康保険料と一緒に天引きされます。労使折半のため、従業員と会社で半分ずつ負担します。
一方、国民健康保険に加入している方は、労使折半ではないので全額自己負担です。また、65歳以上の第1号被保険者も、全額自己負担となります。
介護保険料の納付方法
介護保険料の納付方法は、第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。65歳以上の第1号被保険者は、年金からの天引き(特別徴収)または口座振替(普通徴収)のいずれかに分類されますが、自由に選択できるわけではありません。年金の年額が年間18万円未満は普通徴収、18万円以上は原則特別徴収です。
40~64歳の第2号被保険者で会社員や公務員の場合は、給与から健康保険料と一緒に介護保険料が天引きされます。自営業者やフリーランスのような国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険料に介護保険料が含まれており、口座振替や納付書で支払います。
加入手続きは不要
介護保険料の支払い義務が発生する40歳を迎えても、特別な加入手続きは必要ありません。その理由は、40歳以上の国民が自動的に被保険者となる仕組みが採用されているためです。
40歳~64歳までの方は、介護保険に第2号被保険者として、40歳の誕生日を迎えた時点で自動的に加入します。健康保険や国民健康保険などに加入しているため、介護保険料も健康保険料と一緒に徴収されるという仕組みです。
介護保険料率は変化する
介護保険料率は一律というわけではありません。介護保険制度の財政状況・介護サービスの需要に応じて変化します。
例えば、日本は高齢化が進行しています。介護保険制度を利用する方が増えることで、介護保険制度の支出が増えるため、介護保険料率が将来的に引き上げられる可能性が高いです。
また、円安による物価高が続く昨今においては、物価の変動や賃金の変動なども保険料率に影響を与えます。実際に、年々介護保険料は引き上げられているため、今後も引き上げが続く可能性が高いでしょう。
まとめ
介護保険制度は、高齢者や一定の年齢以上の障害者が必要な介護サービスを受けられるようにするための公的保険制度です。
40歳以上の国民が介護保険料を支払うことで、介護サービスの財源を確保し、誰もが必要なときに適切な介護サービスを受けられるようにしています。
40歳を迎えると、介護保険料の計算方法に基づいて介護保険料が算出され、給与所得者は健康保険料と一緒に給与から天引き、自営業者やフリーランスは国民健康保険料と一緒に支払います。
介護保険料は、所得または賞与によって変わるため、金額は人によって異なるということを理解しておきましょう。
まだ介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴い生活に不安を抱いている方には、シニア向け賃貸住宅がおすすめです。
ヘーベルVillageは、シニア向け安心賃貸住宅を提供しています。駆けつけサービス・健康や暮らしをサポートする相談サービス・看護師による健康相談・医療機関の紹介サービスなど、さまざまなサポートが充実しています。
自立しながら安心して老後を暮らしたいという方は、旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。