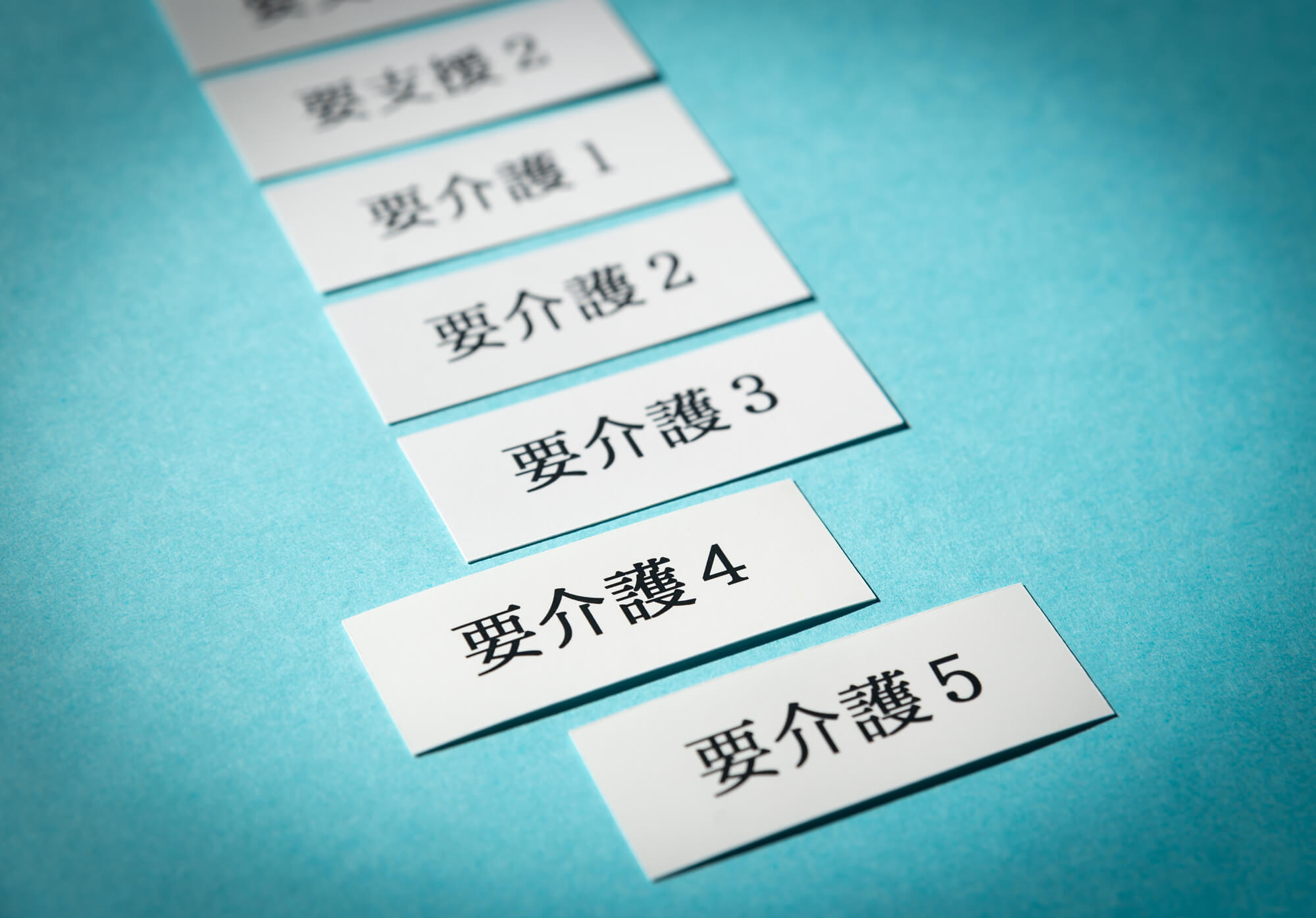要支援1とはどんな状態?利用できるサービスや費用などについて解説
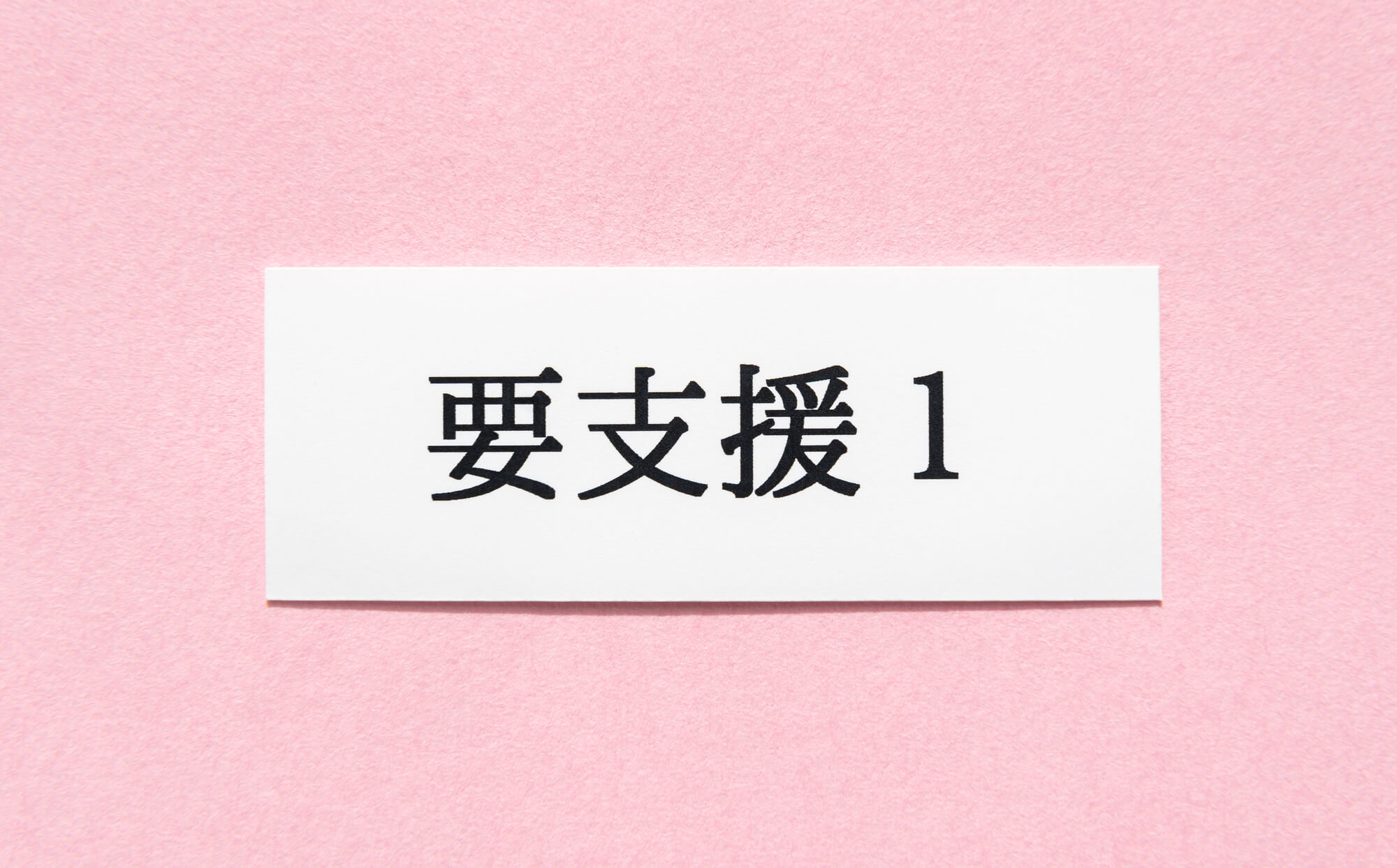
介護保険を用いて介護サービスを利用するためには、要介護認定で要支援1以上の認定を受ける必要があります。
しかし、要支援1がどのような状態なのか分からず、自身が介護サービスを利用できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、介護認定の要支援1とはどのような状態か、要支援1の場合に利用可能なサービス、支給限度額、ケアプランの事例などを解説します。介護認定の要支援1について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。
要支援1とはどのような状態?
生活環境が良くなった、医療技術が進歩したといったさまざまな理由で、平均寿命の延びが顕著になりました、しかし、平均寿命が延びても健康寿命まで延びたわけではありません。
そのため、高齢化が進行する日本では、病気や体力的な衰えなどを理由に介護が必要な方が年々増えています。
参照:厚生労働省「介護の状況」
介護保険では、高齢者が介護サービスを安心して利用できるように、介護サービスにかかる費用の負担を軽減(通常1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割)しています。
介護保険は高齢者だけが利用できるものではありません。介護保険の被保険者の場合には市町村の区域内に住所を有し、以下の条件を満たしていれば介護保険を利用できます。
- ・65歳以上の者(第一号被保険者)
- ・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
ただし、上記の条件を満たしていれば誰でも利用できるわけではありません。要介護認定で要支援1~要介護5のいずれかに認定される必要があります。要介護認定の流れについては以下のサイトをご確認ください。
要支援1は要介護認定で最も低い基準ですが、どのような状態なのでしょうか。
多少サポートが必要な状態
要支援1とは、日常生活における基本的な動作については自身で行えるものの、サポートが多少必要な状態です。
例えば、立ったり座ったりする際にふらつくことがたまにあるものの、食事やトイレなどの基本的な動作で問題が生じることはありません。
要介護認定では、要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態が要支援1です。
自宅での生活が可能であり、在宅での介護サービスを利用する方がほとんどです。
要支援1と自立の違い
要支援1の方は、日常生活における基本的な動作については介護をほとんど必要としません。そのため、自立との違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
自立した状態とは、身の回りの基本的なことを原則自分でできる状態です。つまり、歩行や起き上がりなどの日常生活における基本動作、薬の内服や電話をかけるなどの生活動作を問題なく行うことができれば自立した状態と言えます。
要支援1は上記のような日常生活における基本動作や生活動作に一部問題が生じており、サポートを必要としている状態です。
全くサポートを必要としていないのか、多少必要なのかという違いが自立と要支援1の大きく異なる点と言えるでしょう。
要支援1と要支援2の違い
要介護認定では、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満となるのが要支援2です。要介護認定等基準時間が要支援1よりも長いですが、具体的な違いは何なのでしょうか。
要支援1と要支援2の違いをまとめると以下の通りです。
| 要介護度 | 要介護認定の目安 | 具体的な状態 |
| 要支援1 |
・ 日常的な動作は自分でできる ・ 日常生活の一部に支援が必要 ・ サポートを受けることにより要介護状態を防げる |
・ 日常生活は基本的に自分だけで行える ・ 掃除や身の回りのことの一部で見守りや手助けが必要 |
| 要支援2 |
・ 日常的な動作は自分でできる ・ 要支援1と比べて支援が必要なシーンが多い ・ サポートを受けることにより要介護状態を防げる |
・ 立ち上がりや歩行などでふらつきが見られる ・ 入浴時に背中を洗えない ・ 身だしなみを自分だけで整えることが困難 |
両者は日常的な動作は自分でできる、サポートを受けることで要介護状態を防げる点では同じです。しかし、要支援1はほとんど支援を必要としないのに対し、要支援2では支援を必要とする状況が増えるのが唯一の違いです。
要支援1で利用できるサービス一覧
要支援1では以下のようなサービスを利用できます。
| 在宅でのサービス |
・ 介護予防訪問介護 ・ 介護予防訪問看護 ・ 介護予防訪問入浴 ・ 介護予防訪問リハビリテーション ・ 介護予防居宅療養管理指導 |
| 通所によるサービス |
・ 介護予防通所介護(デイサービス) ・ 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) |
| 短期入所によるサービス |
・ 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) ・ 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |
| 福祉用具のサービス |
・ 介護予防福祉用具の貸与費の支給 ・ 介護予防福祉用具の購入費の支給 |
| 住宅改修のサービス | ・ 介護予防住宅改修費の支給 |
| 地域密着型のサービス |
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護 ・ 介護予防認知症対応型通所介護 |
| その他 | ・ 介護予防特定施設入居者生活介護 |
特定施設入居者生活介護、短期入所療養介護、地域密着型サービスがどのようなものなのか、詳しく知りたい方は以下のサイトをご覧ください。
参照:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」
参照:厚生労働省「短期入所療養介護」
参照:厚生労働省「地域密着型サービスの概要」
要支援1の支給限度額とケアプラン事例
要介護度によって介護保険の支給限度額が異なります。支給限度額がいくらか、要支援1で利用できるケアプランの事例について詳しく見ていきましょう。
要支援1の支給限度額
要支援1の方が居宅サービスを利用する場合の1か月の支給限度額は50,320円です。日常生活において介護を必要とする状況が要支援1は少ないため、少額に設定されています。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が自己負担です。限度額を超えた場合は全額自己負担になるので注意しましょう。
ケアプラン事例
以下の条件で介護サービスを自宅で利用した場合、自己負担はいくらになるのでしょうか。
- ・介護予防訪問看護:4回(18,080円)
- ・介護予防訪問リハビリテーション:4回(12,600円)
- ・介護予防通所リハビリテーション:4回(25,220円)
- ・介護予防福祉用具貸与:(5,880円)
上記を合算すると61,780円です。自己負担1割の場合は6,178円で利用できます。
介護サービスの利用にどのくらいの費用がかかるか、自己負担がいくらになるかは以下のサイトで確認できます。
まとめ
介護保険を用いて介護サービスを利用するには、年齢条件を満たすだけではなく、要介護認定で要支援1~要介護5のいずれかの認定を受ける必要があります。
要支援1は日常生活を自分一人の力で行える状況ですが、掃除や身の回りのことの一部で見守りや手助けを必要とします。
要介護度によって利用できるサービスや支給限度額が異なるため、要支援1がどのような内容なのかを事前に確認しておくと安心でしょう。
まだ、介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴い生活に不安を抱いている方にはシニア向け賃貸住宅がおすすめです。
ヘーベルVillageはシニア向け安心賃貸住宅を提供しています。駆けつけサービス、健康や暮らしをサポートする相談サービス、看護師による健康相談、医療機関の紹介サービスなどサポートが充実しています。
自立しながら安心して老後を過ごしたいという方は、旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。