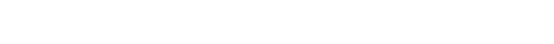第11回 くらしノベーションフォーラム 2013.9.5開催
テーマ:デザイン論から心地よい暮らしを考える ~認知心理学の視点から~
旭化成ホームズでは、自然の上手な取り入れ方やそのライフスタイルなど、さまざまな側面から暮らしの心地よさを提案してきました。今回は認知心理学の専門家をお招きし、人が物に愛着を感じる心理要因やデザイン論についてご講演いただきました。また、くらしノベーション研究所からは、住まいの居心地についての調査結果をご報告します。
- 講 演:デザインが暮らしと人を変える
― 認知心理学から考えるこれからのデザイン論 ―
講 師:荷方 邦夫氏 - 金沢美術工芸大学 美術工芸学部 准教授
1972年生まれ。筑波大学大学院心理学研究科単位取得退学、博士(心理学)
認知心理学の立場から、わかりやすさ・理解の仕組みの解明を考えている。また、それらを用いて、教育、メディア表現、人工物のデザインなど、さまざまな場面での応用を積極的に進めている。
主な著書:『心理学の「現在」がわかるブックガイド』(実務教育出版、共著)、『「使える」教育心理学』(北樹出版、共編著)、『心を動かすデザインの秘密』(実務教育出版)
- 報 告:心地よく住まうために大切なこと
― 居心地因子に関する調査結果より ― - 旭化成ホームズ(株)くらしノベーション研究所 主幹研究員
下川 美代子
「魅力あるモノ」なぜデザインが重要なのか?
私たちは日常、人間の手によってつくられた「人工物(Artifact)」に囲まれています。唐突ですが、お手持ちの携帯電話をご覧ください。カバーやフィルム、ストラップがついていたりと、自分流にカスタマイズされていると思います。このように私たちは日々の営みのなかで身の回りにあるモノや世界にはたらきかけ、さまざまな手段で「加工」を行っています。デザインとは「人間が生きていく中で、目の前にある世界を何らかの目的をもって手を加え変化させること。あるいは、自分を取り巻く世界を変化させる工夫のこと」。人は誰もがデザイナーであり、デザインの基本は、美しさや使いやすさではなく「工夫」なのです。これは英語のdesignという言葉が「意匠」よりも「計画」という言葉で訳されることが多いことからもわかります。
こうしたデザインが、なぜ重要なのでしょうか。イタリアの経営学者ベルガンティは、今後30年くらいの世界について「テクノロジーの発展が緩やかな市場では、デザインが主力の開発競争を生む(デザイン・ドリブン・イノベーション )」と主張しています。コモディティ化(世の中の商品が急速に発展し、競争できるのは価格だけという状態)という言葉がよく聞かれるようになってきましたが、 21世紀は、ある意味で価格競争や技術競争の限界に達する中で競争力が著しく失われていきます。アジアなどの製品がどんどん市場に進出し、競争力を失いつつある日本にとって、文化的水準の高さ、100年以上の歴史で培われた文化・芸術コンテンツの蓄積、人的資源が多いという点で、デザインは残された強みである可能性があるのです。
では、そうした流れを踏まえて「魅力あるモノ」を考えてみましょう。
身近なお酒の瓶ひとつをとっても、多種多様なデザインがなされていますが、ボトルのよさという問題よりは、お祝いのために買ってもらった生まれ年のワインであるとか、10年越しでやっと手に入れたという世俗的な喜びが、そのモノをとても素敵に見せます。
また、ある地域では特徴的なモニュメント(環境彫刻)が誰でもわかる待ち合わせ場所となって日常生活に溶け込んでいたり、町ではガードレールを椅子代わりに座っている光景が見られたりします。このように、何でもない日常で私たちが環境とやりとりしていることの中に、よく生きる、素敵に生きる、心地よく生きるヒントがあるということがとても重要になります。
どうしてそれが素敵に見えるの?
私たちが身の回りでデザインされたモノを感じるとき、デザインの評価には3つのレベルがあると考えられてきました。
最も古くから知られるのは「本能レベルのデザイン」。 色・形、におい、音といった知覚的レベル、質感、キレイ・シンプルといった直感的な印象など、審美性といわれる領域です。そして、このようなデザインは、たいていの場合、芸術家に近い人達のものだと考えられてきました。
1980年代以降になると、使いやすさ、わかりやすさ、軽さ、耐久性、機能といったユーザビリティが備えられているかという「行動レベルのデザイン」が提唱されます。1988年に心理学者のノーマンという人が「美しいだけで使えなかったらそれは物として劣悪である」と唱え、デザインの考え方に一大転換が訪れます。それから20年、工学系の設計者たちは、見た目はデザイナーに任せて、いかに使いやすく、その中に機能を盛り込むかということに腐心してきました。ただ、作り手が腐心して作っている割には、ユーザは使いづらくて腹が立つという経験はよくあると思います。私たちはデザインされた環境を経験する前から、「メンタルモデル」といって、事物の構造やはたらきについての固定した知識やイメージを持っています。このメンタルモデルに合っている限り、そのモノはよくできているのですが、合わないと環境の中で齟齬が起こります。一方で、何度も見ているものは初めてのものよりも圧倒的に魅力的に見えるという「単純接触効果」を示した研究もあります。
その後、2000年代初頭から「内省レベルのデザイン」が始まりました。先ほどのお酒の例のように、モノのよさというのは、機能や見た目以上に、そのモノとの間でできる記憶、思い出、思考がとても重要になってくるということが、「内省的視点」「経験価値」(User experiences:UX)という言葉で盛んに言われるようになりました。すでに私たちの内側にある知識や感情、思考、認識、記憶などを結びつけることによりデザインに「意味」をもたらす活動。これが内省レベルのデザインです。
デザイナーは「多くの人はこういう風に使うだろう」というシステマティックな視点(システム・ビュー)であるのに対して、ユーザは「私が思うこと」という別の視点を(パーソナル・ビュー)を持っています。デザインはパーソナル・ビューというもう一つの視点から考えるべきではないかというのが重要なポイントです。
パーソナルな視点からのデザイン論を考えると、モノを通じてユーザが感じるエピソード的な内容が、人工物に対する主観的な評価をつくります。特に体験によって得られる感情的、感覚的記憶によって左右され、中でも「ナラティブ(物語性)」というのがとても重要です。私たちはデザインされたモノについて、受け取る立場よりは、自分が関わっていくという側面が多く、関与できる側面がいかに多いかがデザインを支えています。これからは、こうした意味論的なデザイン研究が重視されてくると思います。