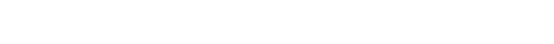第11回 くらしノベーションフォーラム 2013.9.5開催
テーマ:デザイン論から心地よい暮らしを考える ~認知心理学の視点から~
旭化成ホームズでは、自然の上手な取り入れ方やそのライフスタイルなど、さまざまな側面から暮らしの心地よさを提案してきました。今回は認知心理学の専門家をお招きし、人が物に愛着を感じる心理要因やデザイン論についてご講演いただきました。また、くらしノベーション研究所からは、住まいの居心地についての調査結果をご報告します。
- 講 演:デザインが暮らしと人を変える
― 認知心理学から考えるこれからのデザイン論 ―
講 師:荷方 邦夫氏 - 金沢美術工芸大学 美術工芸学部 准教授
1972年生まれ。筑波大学大学院心理学研究科単位取得退学、博士(心理学)
認知心理学の立場から、わかりやすさ・理解の仕組みの解明を考えている。また、それらを用いて、教育、メディア表現、人工物のデザインなど、さまざまな場面での応用を積極的に進めている。
主な著書:『心理学の「現在」がわかるブックガイド』(実務教育出版、共著)、『「使える」教育心理学』(北樹出版、共編著)、『心を動かすデザインの秘密』(実務教育出版)
- 報 告:心地よく住まうために大切なこと
― 居心地因子に関する調査結果より ― - 旭化成ホームズ(株)くらしノベーション研究所 主幹研究員
下川 美代子
心地よい生活空間のデザインを考える
生活空間のデザインでも、システム・ビューで設計する側と、パーソナル・ビューを持つユーザとの間には大きなすきまがあります。ユーザは好き勝手に高い自由度を発揮し、デザイン側の想定とは全く違う工夫が入り込みます。また、当初と異なる視点から満足を感じることがとても多く、ナラティブベースの満足という要素が入ってきます。さらに、大量の買い込んだ生活財とのせめぎ合いの中で生活空間は決定されます。
このように身の回りの環境との間で、やりとりをしながら生きているユーザの長期の使用に対して、デザインする側はどう関わっていくのか。人間とデザインされた環境をフィットさせるということがとても重要になってくるでしょう。
じつは、人は外界を手がかりに思考・行動します。思考は内側にある知識と、外側にあるモノとの相互作用なのです。このような考え方を「状況論的アプローチ」といい、手がかりとなりやすいデザインをアレンジすることができます。また、例えば引く側のみに取っ手がついていて、押す側には押し手を置くスペースがついている扉のように、そこにあるモノが、あたかもそうすることを求めているように設計されていると、頭で考える必要がなくフィットしたモノになります。このような考え方を「アフォーダンス」といいます。人間は体の大きさも機能もさまざまに制約されており、その制約に合ったデザインを作る「状況論的アプローチやアフォーダンス」といった側面も、これからのデザインを支えるキーワードの一つになってくると思います。
これからのデザインを支える「半径10メートル以内の心理学」
今までのデザインや設計論では、見た目・形から人間中心設計へというのが新しい流れといわれてきました。これからはモノ中心、そのモノを取り巻く状況まで拡張してデザインの幅を考えるということが出てくるでしょう。また、使いやすさはずいぶん研究されてきましたが、これからは使いやすさの向こうにある、ユーザがはたらきかけることができる自由度の高さをデザインに備える。ユーザビリティからユーティリティへというのがキーワードになるでしょう。
今までの道具は自分の手や体の延長として考えればよく、これからは考えている世界が自分の身の回りに表現されていることが重要視されてくるでしょう。バーチャルもそうですが、心の延長が半径10メートルの間に満たされるようにデザインを考えていく。体の延長でもあり、心の延長でもある世界をどう考えていくかによって、これからの生活や居心地というものが美しくデザインされ、工夫の入り込む余地が生まれてきます。重要なのは、私たちの半径10メートル以内の「工夫」なのです。