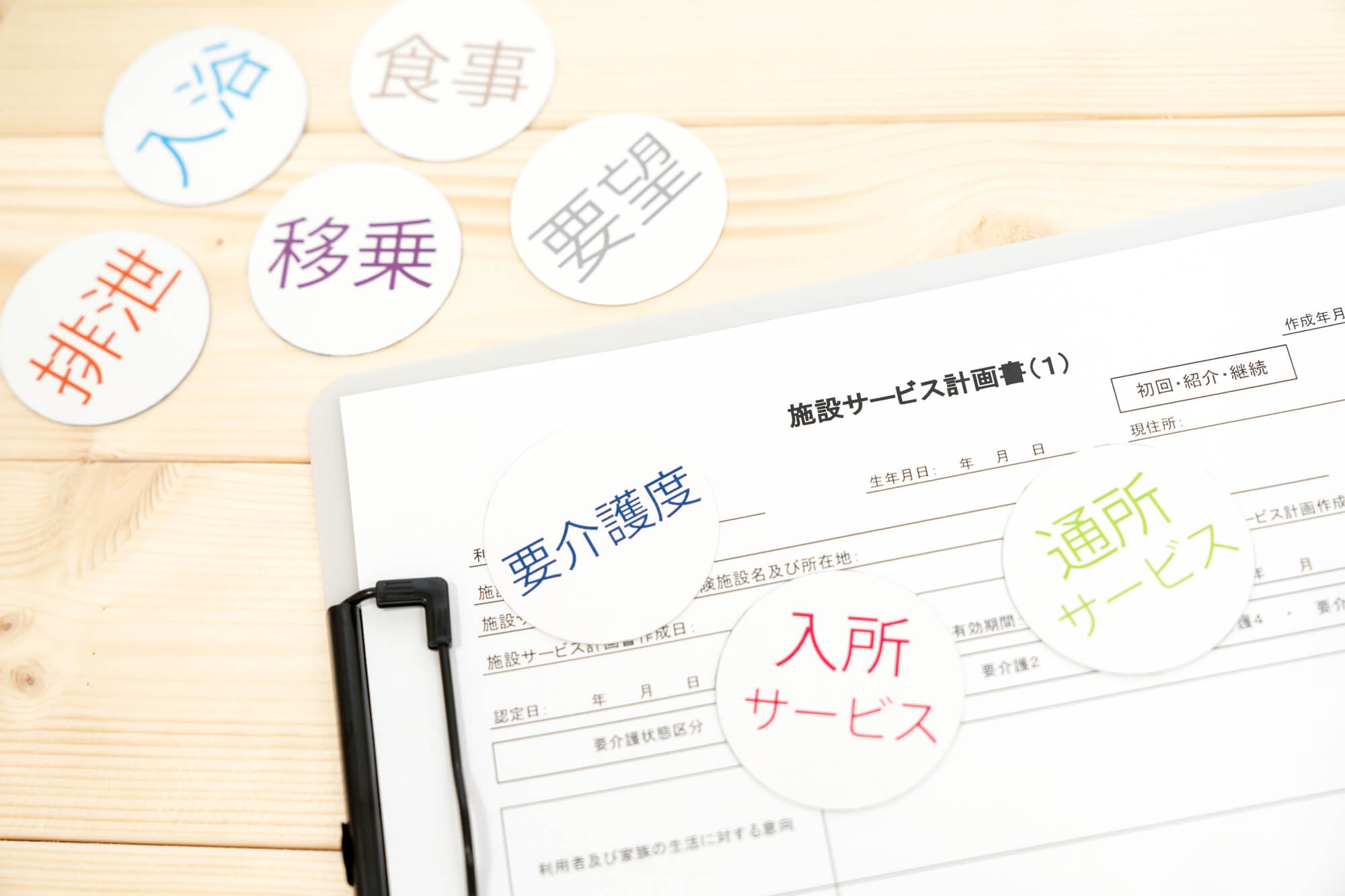介護保険制度とは?対象者やサービス、申請の流れなどを解説

介護サービスの利用を検討している方の中には、介護保険の仕組みが気になっている方も多いのではないでしょうか。
介護保険を利用することによって、自己負担の金額が変わるため、事前に仕組みを正しく把握しておくことが大切です。
この記事では、介護保険とは何なのか、利用できるサービス、申請の流れなどを解説します。介護保険について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。
介護保険とは?
介護保険とは、高齢化が進行する日本で、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設されました。1997年に介護保険法が成立、2000年に介護保険法が施行されました。
介護保険の基本的な考え方は以下の3つです。
- ・自立支援
- ・利用者本位
- ・社会保険方式
介護保険では、介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念としています。
また、利用者の選択によって多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを総合的に受けられます。給付と負担の関係が明確な社会保険方式が採用されています。
介護保険について詳しく見ていきましょう。
介護保険制度
介護保険制度では、40歳以上の方は毎月介護保険料を支払うことが義務化されています。介護保険に加入することによって、65歳以上の方は市区町村が実施する要介護認定で介護が必要と認定された場合、介護サービスを利用できるようになります。
40歳~64歳までの方は介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合、サービスを利用することが可能です。あくまでも認定を受けた場合に限定されている点に注意してください。
介護保険制度について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。参照:厚生労働省「介護保険制度の概要」
対象者
介護保険制度の対象者は以下の介護保険の被保険者です。
- ・65歳以上の方(第1号被保険者)
- ・40~64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
65歳以上の方は、寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった際、介護保険のサービスを利用できます。
40~64歳までの方は、初老期の認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる病気(特定疾病)によって要介護状態や要支援状態になった場合が対象です。
特定疾病の詳細は以下の通りです。
| 筋萎縮性側索硬化症 | 脳血管疾患 |
| 後縦靭帯骨化症 | 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
| 骨折を伴う骨粗しょう症 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 多系統萎縮症 | 慢性関節リウマチ |
| 初老期における認知症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 脊髄小脳変性症 | 脊柱管狭窄症 |
| 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 早老症 | 末期がん |
参照:厚生労働省「介護保険とは」
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスとして、以下の5つが挙げられます。
- ・居宅介護支援
- ・居宅サービス
- ・施設サービス
- ・福祉用具に関するサービス
- ・住宅改修
それぞれのサービスを詳しく説明していきます。
居宅介護支援
居宅介護支援とは、介護サービスの利用にあたって受けられる以下のようなサービスです。
- ・ケアプランの作成
- ・家族の相談対応
居宅サービス
居宅サービスとは、自宅に住んでいる方に向けた介護サービスです。訪問型、通所型、短期滞在型の大きく3つに分類されます。
訪問型では、訪問介護(生活援助・身体介護)、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導などのサポートを受けられます。
通所型では、デイサービス(食事や入浴、リハビリやレクリエーションなど)、デイケア、認知症対応型通所介護などのサービスを受けることが可能です。
短期滞在型では、施設に短期間宿泊して食事や入浴、リハビリの支援などを受けることで、家族の介護負担軽減が可能なショートステイに対応しています。
施設サービス
施設サービスとして、以下の3つが挙げられます。
- ・特別養護老人ホーム
- ・介護老人保健施設
- ・介護療養型医療施設
福祉用具に関するサービス
福祉用具に関するサービスとして、以下の2つが挙げられます。
- ・介護ベッドや車いすなどのレンタル
- ・入浴・排泄関係の福祉用具の購入費の助成
福祉用具の購入費の助成は年間10万円が上限となっており、1~3割を自己負担することで購入できます。
住宅改修
手すりの設置やバリアフリー化、和式トイレを洋式に変更するといった工事費用に対して補助金が支給されます。
最大20万円までとなっており、1~3割を負担することで利用できます。
要介護認定の申請の流れ
介護保険を利用して介護サービスを利用するには、要介護認定を受けなくてはなりません。速やかに認定を受けるためにも、申請の流れを事前に把握しておくことが大切です。
要介護認定の申請の流れは以下の通りです。
- 1.市区町村の窓口へ申請する
- 2.訪問調査
- 3.主治医の意見書
- 4.一次判定
- 5.二次判定
それぞれの流れを詳しく解説していきます。
①市区町村の窓口へ申請する
申請先は居住地の市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センターとなります。
②訪問調査
介護保険サービスを利用するには、要支援または要介護の認定を受けるための訪問調査を受ける必要があります。
市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための調査を実施します。
基本的な調査項目だけでは把握しきれない介護の状態や心配事などがある場合は、認定調査員に伝えることで「特記事項」として記録され、審査の際の重要な判断材料になります。
③主治医の意見書
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼して作成します。主治医がいない場合、市区町村の指定医の診察を受けなくてはなりません。
④一次判定
調査結果および主治医意見書の一部の項目がコンピューターに入力されます。全国一律の判定方法にて要介護度の判定が行われます。
⑤二次判定
一次判定の結果と主治医意見書、訪問調査の特記事項の内容を踏まえ、介護認定審査会が要介護度を判定します。
市区町村は介護認定審査会の判定結果を踏まえながら要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
介護サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)が必要です。ケアプランの作成では、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の希望、心身の状況などを十分考慮して、介護サービス計画書を作成し、介護サービス計画書に基づいたサービスの利用を開始できます。
まとめ
高齢化が進行する日本においては、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みを確立する必要がありました。介護保険制度はこのような状況下で誕生した制度で、40歳以上の方は毎月介護保険料を支払うことが義務化されています。
65歳以上の被保険者は要介護認定を受けた場合において介護サービスを利用できますが、40~64歳までは特定疾病を発症した場合のみ利用できます。
介護保険に加入することで介護サービスを利用する際の利用料の負担を軽減できますが、介護サービスを利用するには認定を受けなくてはなりません。
手続きを速やかに進めるためにも、事前に手続きの流れを確認しておきましょう。
まだ、介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴い生活に不安を抱いている方にはシニア向け賃貸住宅がおすすめです。
ヘーベルVillageはシニア向け安心賃貸住宅を提供しています。駆けつけサービス、健康や暮らしをサポートする相談サービス、看護師による健康相談、医療機関の紹介サービスなどサポートが充実しています。
自立しながら安心した老後を暮らしたいという方は、旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。