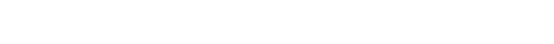第6回 くらしノベーションフォーラム 2011.12.6開催
テーマ:多様な家族が循環的に住み続けられるための地域と住まい ~近居・隣居はなぜ大切な現象なのか?~
- 講 師:大月敏雄氏
- 東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 准教授
福岡県出身。1991年、東京大学工学部建築学科卒業。1996年、同大学大学院工学系研究科博士課程単位取得退学、博士(工学)取得、横浜国立大学工学部建設学科助手。東京理科大学工学部建築学科助教授を経て、2008年から現職。専門分野は、建築計画・ハウジング・住宅地計画。主な著作は、「奇跡の団地阿佐ヶ谷住宅」(共著・王国社 2010)、「集合住宅の時間」(王国社 2006)、「近現代都市生活調査同潤会基礎資料Ⅲ第1-12巻」(共編著・柏書房2004)等。
はじめに
東日本大震災のあと、家族のつながりが再認識され、世の中が家族というものをもう一度考えようという雰囲気になってきたような気がします。
今まで我々は「ハウジング」と称して住宅を計画したり、設計したり、供給したりしてきたわけですが、そういうものに、もう一度疑問を投げかけて、今までのつくり方では、こういうところを見失ってきていたのではないかということを今日、お伝えしていきたいと思っています。
計画住宅地が生まれた時代背景
日本が高度成長を迎えた昭和30年代頃、都市の労働力を支える「金の卵」として大量の人々が都会に出て来る現象が起きました。そうした人々の住まいは、すでにインフラが整った都会の中には余地が少ないので、郊外の処女地を開発してインフラを新たに建設してそこに家を建てようということになったわけです。
戦前は田舎から都会にやってくる人々はそんなに多くはなく、まだまだ都心に余力がありました。関東大震災のあとの同潤会アパートなどはかなり都心に建っていたし、戦後すぐの公営とか公団も比較的都心に建っていました。しかし、昭和30年代ぐらいになると、もう都心に外から人を受け入れる余力はないということで、どんどん郊外を開発していくわけです。郊外の処女地に移住した人たちというのは第一世代であって、その第一世代がこうしたまちを第二世代以降に引き継ぐことができるのか、あるいは居住地をたたんでしまうのか、今、その瀬戸際に立たされているというのが、今の郊外の問題なのではないでしょうか。
逆に、田舎は、「金の卵」をどんどん都会に輩出してしまったので、今都会が抱えている超高齢化という問題は、既に昭和50年代ぐらいからずっと言われていたわけで、それでも細々と生き延びてきたのが田舎なのです。それでは「金の卵」を輩出する前の田舎はどうだったのかというと、実は、何百年もの昔から、代々住み継がれて成熟した環境であったということができます。
私自身は九州の農村の出身なので、昔の田舎はどんなものなのか、よく分かっているつもりですが、こういう郊外の処女地と何が違うかというと、「混ざっている」ことです。たとえば、お金持ちもいれば貧乏人もいる。金持ちの子どものほうがいろんな意味で強いわけですけど、貧乏人の子どものほうは根性があったりして、ナニクソと思ったりする。あるいは近所に障害をもった子どもがいると、お母さんとかお祖母ちゃんが、あの子と遊ぶときはこんなことに気をつけなさいと教えてくれたりする。教え方や接し方が、多少ぶっきらぼうだったりして、完璧主義的人道主義者からすると差別と糾弾されるかもしれなさそうな場面もないわけではありませんが、そういう全人格的な教育的な環境というものを、我々はどう次世代以降につくることができるかということが、本当の究極的な居住環境の形成だと思っております。
20世紀の計画住宅地の問題
第一世代の我々の先輩たちが戦後営々とつくりあげてきた新しい戦後の団地、つまり計画団地というものはやっぱり100点満点ではなく、不都合なところがあります。それを100点に近づけていくためには色々なことを考えなければいけないのですけれど、ゼロからつくり直すことはできないので、今ある環境を足したり引いたりしながら、どうやったら成熟したまちにつくり変えられるのかということをこれから考えなければいけない、そういう時代に入ってきたのではないかと思います。
そもそもこういう計画団地をつくっていくときの前提条件というのが、我々が無意識のうちに、「1家族というものは1住宅に住むものだ」と考えられていたと思うのです。つまり行政の計画的な目標として「1家族にどれだけの空間を与えるか」みたいなことが政策目標になったのです。そのこと自体は決して悪いことではなく、いわゆるセーフティーネットを政府が底支えすることは大切なことですが、必要条件ではあるけど十分条件ではないわけで、これだけでは成熟する居住環境、あるいは子どもが全人格的に育っていける環境はできないわけです。住宅の数だけを見て、質の問題がおいてけぼり、というのが第一の問題です。
二番目は、「プロセス」すなわち時間経過を無視してきたことです。家族もまちも植物も、時間が経つと変わるわけで、ある瞬間の時間断面において、1家族に1つの住宅をあてがうというような発想で来た結果、ふっと後ろを振り返ると、すでにそこで営まれる生活と、供給された空間がマッチしていません。今から申し上げます「近居・隣居」と言われる状況が自然発生的にできたり、あるいは今まで家だったところが店舗になったり、さまざまなことが起きてくるわけです。しかし、住宅供給時点から先の世界は供給者側、計画者側、行政の仕事ではもはやなく、生活の話なので、居住者側が勝手にやってくれということになっているわけです。企業も学識者も行政も、いわゆる専門家といわれる人たちは、つくることまでが仕事なのであって、それが、供給された後、時間経過とともにどう変わっていくのかということを考えることは仕事ではないと観念してきたわけです。
しかし新築がどんどん建たなくなった今に至って、供給後の生活世界のただ中に、仕事の宝庫があるという様に考え直さないと、空き家がたくさん増え行くこの日本は、なかなか立ち行かないのではないかと思います。
そういった意味で、ものごとを計画するときには必ず時間変化をどう考慮するかということが重要です。特に家族の構成員は、離合集散します。増えたり減ったりします。そういうものをどういう装置で、どういう空間的なデバイスで解決していくのか、そういうことは、これまであまり本気で考えられて来ていません。今一度、そのような視点から考え直さなくてはいけないのではないかと考えます。
三番目は、記憶の継承の問題です。成熟したまちを子どもたちにまち引き継ぐときに重要なのは、時間の蓄積であると思っています。様々な建築物、広場、あるいは樹木などには、そこで活動してきた何十年分もの記憶が託されているのです。きれいなまちだといいのか、あるいは便利なまちだったらいいのか、どんなまちだったら子どもが喜んで引き継ごうという意思が生まれるのか。20世紀のハウジングが決定的に忘れていたことは、この記憶と継承の問題ではないでしょうか。
建築の機能には耐震性だとか耐火性だとか津波で流れないとか、色々あると思うのですが、「記憶の器である」というのも、私は重要な機能のひとつではないかと思っています。そういうものをどのように形成していくのかというのも、実は20世紀が忘れてきていた問題で、これから取り組まなければいけない問題ではないかと思います。
新旧「住宅双六」で何が変わったか
1973年に上田篤先生が「住宅双六」という有名な住み替えモデルを発表されました。高度経済成長の“それいけドンドン”の時代だった当時の住まい方のモデルを表現したもので、成長するに連れて大きな家に住み替え、真ん中の上がりはただ一つ、郊外の庭付き一戸建て、という表現となっています。
それから30年以上経った2007年に、再度上田先生が新しい住宅双六をつくって発表しました。今度は真ん中にふり出しがあって、どんどん外に出ていき、上がりが複数用意されています。73年の住宅双六と大きく違うのは、「長生きしたらどうするか」ということを考えて、庭付き一戸建てやマンションの先に高齢期の住まいとして多様な上がりがあることです。有料老人ホームで入会金数千万を払って、とにかく死ぬまで面倒みてもらおうというお金持ちしかできない方法もあるだろうし、生涯現役でピンピンコロリで頑張ろうというような人もいるだろうし、今みたいな円高なら海外に移り住んでしまうことを考えている方もいるでしょう。そのような多様な上がりが世の中に用意されるべき状況なのではないかという問いかけです。現代の庶民心理をうまくモデル化されていると思います。しかし、本当に重要なのは、こうしたすごろくが地域の中で成立するための、地域のあり方だと思うんです。
たとえば、自分は生涯現役でピンピンコロリでいこうと思っていても、途中で嫁さんがぼけ始めたりすると、これはグループホームに入れないとダメかなと思ったりします。でも、グループホームが今の自宅から20キロ先にしかなかったら、高齢の身になってからそこへ引越すのかという深刻な問題が出てきたりします。よくよく考えると、すごろくの上がりが物理的に自分の住み慣れた近くに按配よくないと、これは上がれないぞということになります。つまり、これからの地域のテーマは、あるひとつの地域を捉まえたときに、この上がりとなる終の棲家がどういうに用意されているのかではないかと思います。そこで参考になるのは実例を調べることなのです。