高齢者(シニア)の一人暮らしのリスクと対策9つ|老後に適した住宅選びを解説

一人暮らしをしている高齢者(シニア)にとって、どうすれば安心して老後の生活を送れるようになるのかは大きな関心事でしょう。また、一人暮らしをしている高齢の親が無事に生活を送れるのか、不安に感じるご家族の方もいるのではないでしょうか。
近年、65歳以上の高齢者(シニア)のうち、一人暮らしをしている方の割合は年々増えており、2035年には全体の5割を超えると予測されています。高齢者(シニア)が安心して、かつ快適に一人暮らしを送れるようにするには、事前にリスクを把握したうえで適切な対策を講じることが大切です。
この記事では、一人暮らしをする高齢者(シニア)が増加している背景や潜むリスク、必要な対策、安心できる住まい選びについて詳しく解説します。
高齢者(シニア)の一人暮らし数は年々増加している

内閣府が発表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の人がいる世帯数は、2023年(令和5年)時点で全世帯の49.5%を占めています。さらに、65歳以上のうち一人暮らしをしている方の割合は、2020年(令和2年)時点で女性が22.1%、男性が15.0%と、全体の40%近くにのぼっています。1980年(昭和55年)時点の割合(女性11.2%、男性4.3%)と比較すると、一人暮らしをする65歳以上の方の割合は倍以上となっているのが実情です。
高齢者(シニア)の一人暮らしの割合は増加傾向にあり、2035年には男女合わせて50.2%に達する見込みとなっています。

なぜ高齢者(シニア)の一人暮らしが増えているのか
ここからは、なぜ一人暮らしをする高齢者(シニア)が増えているのか、そのおもな背景と理由を5つ紹介します。
家族など頼れる人が近くにいないから
まず理由として挙げられるのは、頼れる家族が身近に住んでいないことです。
核家族化や少子化の影響で、子どもが遠方に住んでいたり、身近に頼れる家族がいなかったりする高齢者(シニア)は少なくありません。配偶者や兄弟、友人、知人の他界により、孤立するケースも考えられます。このような理由により周囲とのつながりが薄れ、誰かに頼りたくても頼ることができず、やむを得ず一人暮らしを選択している実情があります。
家族に迷惑をかけたくないから
子や孫に精神的・経済的な負担をかけたくないとの気遣いから、「自分のことは自分でする」と考えて一人暮らしを選ぶ高齢者(シニア)もいます。その背景には、年を重ねても精神的・経済的に自立していたいという価値観が横たわっているともいえるでしょう。
現状に満足しているから
現在の生活に不満がないために一人暮らしを選択する高齢者(シニア)もいます。
経済的に不安がなく、趣味の活動や友人との交流、仕事などで充実した生活を送れている方は、今の暮らしに十分満足していて現状を変えたくないと考えることが多いようです。生きがいや働きがいを持ち、誰かに頼らず暮らしているという実感が生活にハリを与えているといえるでしょう。
転居に抵抗を感じるから
高齢になると、新しい生活環境に移ることに対して不安や抵抗を感じやすくなります。長年住み慣れた家や地域に愛着もあり、知らない場所に引越したくないと考える高齢者(シニア)は少なくありません。
見知らぬ土地に対する不安、転居による友人・知人との別れ、同居による精神的な負担、荷物の整理といった物理的な負担などが転居に抵抗を感じる要因です。
一人暮らしのほうが好きだから
単純に「一人暮らしが好きだから」というケースもあります。
一人暮らしの自由さや気楽さを好み、他人と暮らすことで気を遣う生活を避けたいと感じる方は少なくありません。子どもとの同居や高齢者(シニア)向け施設への入居といった選択肢があっても、「住み慣れた場所で自分らしく暮らしたい」「自由なペースで生活したほうが快適」と感じる高齢者(シニア)は多いのです。
高齢者(シニア)の一人暮らしに潜むリスクや不安
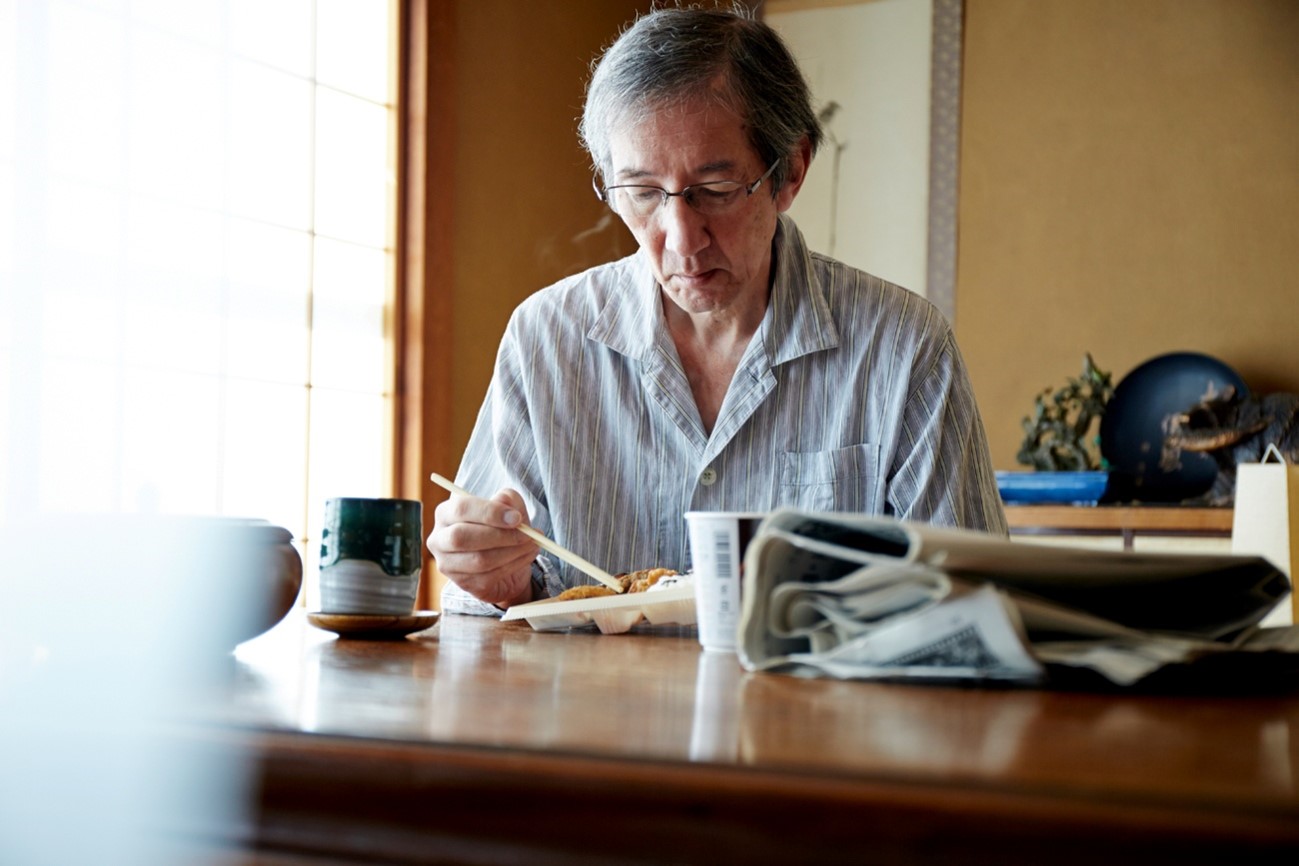
高齢者(シニア)の一人暮らしには、さまざまなリスクが潜んでいます。ここでは、高齢者(シニア)が一人暮らしをするときに懸念されるおもな問題点を6つ紹介します。
家事や家の管理が負担になる
高齢になると、体力や関節の衰えなどの影響で料理・掃除・洗濯などの日常的な家事が負担になることが少なくありません。家事を怠ることで生活環境が不衛生になり、場合によっては健康を損なう可能性も考えられるでしょう。
一戸建てに一人で住んでいる場合には、誰も使っていない部屋や昇り降りが負担になる2階の部屋の掃除が行き届かなくなったり、庭の管理が難しくなったりといったことも考えられます。家のメンテナンスに手が回らなくなると、床に置かれているものにつまずいてケガをするなどのリスクが高まりかねません。
栄養バランスの乱れ・病気・ケガのリスクが高まる
自炊が面倒になったり買い物や調理が困難になったりすると、食生活が偏ってしまいます。一人の食事を味気なく感じ、簡単に済ませてしまう方も少なくないでしょう。そのため、一人暮らしの高齢者(シニア)はどうしても栄養バランスが崩れやすい傾向にあります。偏った食生活は栄養不足をもたらすだけでなく、高血圧、脳梗塞といった病気発症のリスクを高めるため、要注意です。
また、一人暮らしだとケガをしたり病気になったりしたときに誰にも気付いてもらえず、発見が遅れてしまうこともあります。対応の遅れが原因で重症化したり、命にかかわる事態にまで発展したりするリスクもあるのです。
社会参加の機会が減り生活意欲が低下する
一人暮らしをしていて外出する機会が減ると、運動不足やコミュニケーション不足に陥り、生活意欲だけでなく、心身の機能の低下を招きやすくなります。この状態を「フレイル」と呼びます。フレイルになると、食事や入浴といった基本的な家事に加えて日常生活までおろそかになってしまいかねません。フレイルを放置すると要介護状態になる危険性が高まるといわれているため、注意が必要です。
また、社会とのかかわりが薄れることは、生きがいや楽しみの喪失にもつながります。社会参加の機会が減ると、他者とのコミュニケーション不足が原因で認知症発症リスクが高まる恐れもあります。
自然災害発生時に対応しにくくなる
地震や台風などの自然災害が発生したときに迅速な避難が難しい点も、高齢者(シニア)が一人暮らしをする際のリスクです。避難の遅れから、命にかかわる状況に陥る可能性も高いといえるでしょう。また、避難後の環境変化にも対応しにくく、健康への影響も懸念されます。
詐欺や犯罪に巻き込まれやすくなる
判断力が低下していたり、スマートフォンなどのデジタル機器の操作に不慣れだったりする高齢者(シニア)は、振り込め詐欺やフィッシング詐欺のターゲットにされやすい傾向があります。ほかにも、空き巣や強盗のターゲットにされることも少なくありません。周囲に相談相手がいないことで、不審な連絡や金銭要求にも気付かず被害に遭うケースが多発しているのです。
孤独死のリスクが高まる
一人暮らしでは体調の急変や事故が起きても誰にも気付かれず、長期間発見されにくいため、「孤独死」につながるリスクが高いといえます。警察庁のデータによると、2024年に孤独死した方の総数は7万6,020人で、そのうち約5万8,000人が65歳以上という結果でした。
また、高齢者(シニア)の一人暮らしでは、ヒートショックによる入浴事故が起こりやすい点にも注意が必要です。ヒートショックとは急激な温度の変化によって血圧が急上昇・急降下し、心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気などを引き起こす現象です。ヒートショックは特に11月~2月の冬場の入浴時、暖かい室内・浴槽と寒い脱衣所・浴室の温度差が原因で発生しやすく、一人暮らしの高齢者(シニア)の場合は発見・救助が遅れる可能性が高いといえます。
実際、厚生労働省の「人口動態調査」によると、「不慮の溺死および溺水」事故で亡くなった高齢者のうち約8割が入浴中に亡くなっているということです<./span>。
高齢者(シニア)の一人暮らしを安全・快適にするための9つの対策
ここまで解説してきたように、高齢者(シニア)の一人暮らしにはさまざまなリスクが潜んでいます。それでは、そのリスクを軽減し、安心して暮らすためにはどうしたらよいのでしょうか。ここでは、以下9つの対策を紹介します。
- ・見守りサービスを利用する
- ・食事の配達サービスを利用する
- ・生活支援サービスを利用する
- ・介護保険サービスを利用する
- ・家族や親戚の家の近くに住む
- ・成年後見制度を利用する
- ・家の防犯性を高める
- ・社会とのつながりを多く持つ
- ・高齢者(シニア)向け物件に住み替える
見守りサービスを利用する
自治体や民間の見守りサービスを利用すると、一人暮らしをする高齢者(シニア)の安否確認・緊急時の対応が可能です。ただし、一口に見守りサービスといっても、センサーカメラを用いた自動見守りから訪問型のサービスまでさまざまな形態があり、サービス内容や費用、導入条件は提供主体によって異なります。どの形態が自分たちに合っているのか、自治体や地域包括支援センターなどに相談しながら決定しましょう。
食事の配達サービスを利用する
自炊や買い物をするのが難しい高齢者(シニア)の場合には、食事の配達サービスを利用するという選択肢があります。栄養バランスの整った食事を取れば、健康維持や病気の予防に役立ちます。また、宅配担当者とのコミュニケーションの機会は、孤独感の軽減にも効果的です。宅配担当者に安否確認をしてもらうこともでき、より安心して高齢者(シニア)が一人暮らしを送れるようになります。
生活支援サービスを利用する
掃除や買い物、通院の付き添いなど、日常生活に必要な支援を受けることで、高齢者(シニア)の一人暮らしの不安や不便さを大きく軽減できる可能性があります。こうした支援はボランティアやNPOなど多様な団体が提供しており、必要に応じたサービスを選ぶことが可能です。自治体や地域包括支援センターに相談すると利用可能なサービスの情報を得られるので、気になる方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
介護保険サービスを利用する
高齢者(シニア)が要介護認定を受けていると、訪問介護やデイサービス、福祉用具レンタルなど幅広い介護保険サービスを、費用の1~3割を負担することで利用できます。金銭的負担を抑えながら、高齢者(シニア)が一人暮らしを送る生活環境を整えられる点がメリットです。適用範囲内で利用できる訪問系のサービスを活用すれば、住み慣れた自宅を離れることなく生活の質を高められるでしょう。
ただし、介護保険サービスの利用には要介護認定を受ける必要があります。利用を考えている場合は、まず地域包括支援センターや自治体の窓口に相談してみましょう。
家族や親戚の家の近くに住む
近くに家族が住んでいれば、それだけで緊急時や日常のサポートを受けやすくなり、高齢者(シニア)も安心して生活を続けられます。一人暮らしをしたい、プライバシーを守りたいという高齢者(シニア)の希望も、それを近くで見守りたいという家族側の要望も叶えられるでしょう。双方の意向を尊重しつつ、無理のない範囲でお互いが安心して暮らせる環境を整えることが大切です。
成年後見制度を利用する
一人暮らしをする高齢者(シニア)の判断能力が低下したときに備えて、成年後見制度を利用するのもおすすめの対策です。成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方に代わって後見人が財産管理や契約手続きなどをサポートする制度です。成年後見制度には、判断能力が衰えた方の後見人を家庭裁判所が選任する「法定後見制度」、本人の判断能力がある段階で事前に後見人を決めておく「任意後見制度」があります。
任意後見制度を活用すれば、家族などの信頼できる方を後見人に指定できます。そのため、将来高齢者(シニア)の判断能力が衰えたときでも、詐欺被害などに遭うことを未然に防ぐことが可能です。
家の防犯性を高める
高齢者(シニア)が安心して一人暮らしを送れるようにするためには、家の防犯性を高めることも欠かせません。具体的には、窓を防犯ガラスにしたり、防犯フィルムを貼ったりすることで、空き巣などの侵入を防ぎやすくなります。また、ワンドアツーロック(1つのドアに2つ以上の鍵を付けること)やセンサーライトの導入、防犯カメラなどの設置も、空き巣の侵入防止に効果的です。
さらに、近隣住民との日常的なコミュニケーションや防犯パトロールへの参加も、犯罪を未然に防ぐために有効な対策です。地域の方々との関係を密にすることで、犯罪抑止力につながります。
社会とのつながりを多く持つ
社会とのつながりを持つことも、高齢者(シニア)が安心して暮らすうえで大切です。例えば、地域のサークルや行事に参加すると生活に張り合いや楽しみが生まれ、心身の健康維持につながるでしょう。地域の方々とのコミュニケーションの機会が増えれば心身の機能が向上し、認知症の予防やフレイルの対策にもなります。また、異変の早期発見や孤独感の軽減といった効果も期待できるほか、災害時には近隣の方同士で助け合うことも可能です。
高齢者(シニア)向け住宅に住み替える
バリアフリー設計や緊急通報システム付きなど、高齢者(シニア)向けの賃貸住宅に住み替えると、一人暮らしでも安全性と快適性を高めることができます。防犯・見守り体制が整った賃貸住宅ならさらに安心でしょう。
近年、高齢者(シニア)向けの賃貸住宅数は増えつつありますが、設備が充実している分、家賃も高くなる傾向にあります。住み替えを検討する場合は、費用と安全性・快適性のバランスを慎重に検討する必要があるといえるでしょう。
旭化成ホームズが提供する「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」は、バリアフリー機能や防犯性の高さを備えた高齢者(シニア)向けの賃貸住宅です。特徴については、以下で詳しく解説しています。
シニア向け賃貸住宅「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」が選ばれる理由はこちら
高齢者(シニア)の一人暮らしに向いている住宅を選ぼう
高齢者(シニア)が安心して一人暮らしを送るためには、適切な住環境を選択することが重要です。ここでは、高齢者(シニア)向けの住宅を紹介します。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、60歳以上の方を対象とした賃貸住宅です。バリアフリー設計はもちろん、日中の安否確認、生活相談サービスなどを利用できる点に特徴があります。また、必要に応じて食事提供や緊急対応、家事代行などのオプションサービスを利用できる仕組みとなっています。医療・介護スタッフの常駐しているケースは少なく、介護度が比較的低い高齢者(シニア)に適した賃貸住宅です。
高齢者(シニア)向け分譲マンション
バリアフリー仕様で自立した生活を送れる高齢者(シニア)向けに設計された分譲マンションです。生活支援や安否確認などのサービスが受けられるマンションもあり、高齢者(シニア)の一人暮らしでも安全で快適な生活を送れるでしょう。リノベーションにより、自分に合った間取りに変更することも可能です。
また、資産として所有できる点も魅力です。さらに、一部のマンションには温泉やフィットネスジムなどの共用施設が備えられており、より充実したシニアライフを送れます。
高齢者(シニア)向けシェアハウス
複数の高齢者(シニア)が、バリアフリー機能を備えた賃貸住宅で共同生活を送る形態です。光熱費などの費用を複数の入居者で分担するため、一人暮らしのときよりも生活費を抑えやすい点がメリットです。また、同居人がいることで日々の孤独感も軽減されるでしょう。女性専用の高齢者(シニア)向けシェアハウスも存在します。定期的にセミナーを開催し、入居者間の交流や社会参加を促進する仕組みを作っているところもあります。
ただし、シェアハウスには基本的に介護サービスの提供はなく、自立して生活できる高齢者(シニア)向けです。そのため、シェアハウスを選ぶときには介護や医療サポートを受けられるか、病気などになったときにはどのようなサポートがあるのかを確認しておきましょう。
住宅型有料老人ホーム
一人暮らしに近い自由な生活を送りながら、食事、洗濯、掃除などの生活支援を受けられる施設が住宅型有料老人ホームです。一人暮らしの快適さやプライバシーを守りながら生活支援サービスを受けたい方に向いているでしょう。
必要に応じて外部の訪問介護や通所介護サービスを契約し、柔軟なサポートを受けることもできます。レクリエーションやイベントの実施により、入居者同士やスタッフとの交流機会が豊富にあるのも魅力です。
高齢者(シニア)の一人暮らしを力強くサポートする「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」
「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」は、介護施設とは異なる、自由でアクティブな暮らしをサポートする高齢者(シニア)向け賃貸住宅です。自立した生活を基本としながらも、24時間の見守り体制や月1回の相談員面談、看護師による健康相談などのサポート体制が整っている点が特徴です。
また、コミュニティラウンジでは入居者同士が自然に交流できるだけでなく、茶話会やイベントも豊富に開催されており、充実したセカンドライフを実現したい方にも適しています。
家事代行サービス、訪問介護サービス、訪問診療サービス、老人ホームの情報提供などのサポートも利用可能です。旭化成ホームズならではの耐火・耐震・制震構造により、日々の暮らしの安全もしっかりと支えます。
自立した生活を楽しみながらも安心した生活を送りたいと考えている高齢者(シニア)は、ぜひ「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」を検討してみてください。
シニア向け賃貸住宅「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」についてさらに詳しく知りたい方は、以下をご参照ください。

まとめ
一人暮らしをする高齢者(シニア)の数は増加の一途をたどっていますが、同時にさまざまなリスクもともないます。ただし、見守り体制の強化や住環境の整備、社会とのつながりを持つことで、そのリスクは大きく軽減できるでしょう。
自分らしく安心した老後の生活を送るためには、適切な住まいやサービスを選ぶことが大切です。旭化成ホームズでは、高齢者(シニア)が健康で自分らしい生活を送ることが可能な賃貸住宅「へーベルVillage(ヴィレッジ)」を提供しています。一人暮らしの生活を楽しみながら安全で快適な暮らしを送りたい方は、ぜひ検討してみてください。
シニア向け賃貸住宅「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」へのお問い合わせはこちら
一人暮らしをする高齢者(シニア)の数は年々増加しており、2035年には65歳以上の方の半数を超える見込みです。その背景には核家族化や自立志向、転居への抵抗などがあります。
しかし、高齢者(シニア)の一人暮らしには家事の負担、栄養の偏り、孤独、詐欺被害、災害時の対応遅れ、孤独死などのリスクがあるのも事実です。対策としては、見守りサービスや食事の宅配、生活支援、介護サービスなどの活用が挙げられるでしょう。ほかにも、防犯対策の徹底、地域コミュニティへの参加、適切な住環境の選択などが重要です。より充実したセカンドライフを送りたいとお考えの方は、以下の記事もご参照ください。
→ 高齢者の一人暮らしにはどんな危険性がある?考えておきたいリスクと対策
→ 高齢者の一人暮らしは犯罪被害のリスクが高い?やるべき防犯とは
→ 高齢者の一人暮らしの実情とリスク|賃貸住宅を選ぶポイントも紹介













