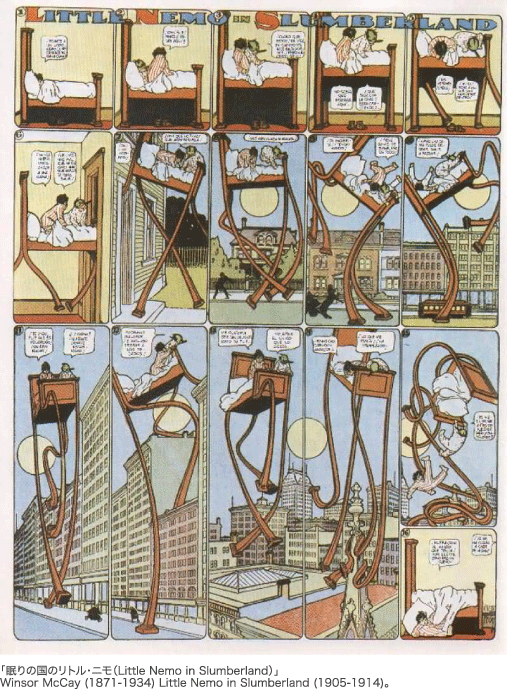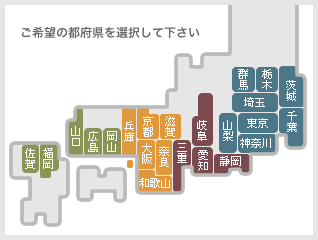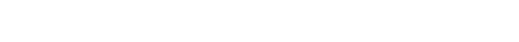── 眠り文学50選は小説だけではなくコミックも選ばれていますね(つげ義春「夜が掴む」、エイドリアン・トミーネ「ハワイでの休暇」)。
柴田さん 本当はもう少しヴィジュアルも載せたかったんですよ。アメリカの古典漫画「眠りの国のリトル・ニモ(Little Nemo in Slumberland)」(1905~1914年)も事情が許せば載せたかった。「リトル・ニモ」は新聞の日曜版の全面を使ったフルカラーの美しい漫画で、毎回、ニモの夢が描かれるのですが、最後は目覚めるシーンの一コマで終わるというパターンだけは不変でした。連載が始まった頃はテレビはもちろん、まだラジオもなく、人々のエンターテインメントの中心が新聞漫画だった時代で、日曜日のカラー漫画は新聞の売れ行きを左右する目玉企画だったんですね。だから子供だけじゃなく大人も楽しめる作品として描かれています。
鍛治さん 「リトル・ニモ」って聞いたことありますね。なんで知ってるんだろう(注:日本でアニメ映画として製作されました。1989年公開)。
柴田さん 本来年の5月頃、私が監訳と一部翻訳を担当する「初期アメリカ新聞コミック傑作選」として全4巻で創元社から出版される予定なんですよ。新聞漫画を原寸版(ブランケット版)で選集化するのですが……。
── それは面白そうです。出版されたらぜひ買わなくては。
柴田さん ただ、そんな凝った造本なので価格が10万円超えちゃうんですよ(全4巻+別冊113,400円)。
── じ、じゅうまんえん……。
柴田さん 図書館や研究機関が購入してみなさんに公開してくれると良いのですが……。監訳はもう終わっていて、ただ、掲載時の新聞漫画の色の再現が大変なんですね。当時も眠りの世界の感触を伝えるためにはフルページ、フルカラーが必要だったのでしょう。光と影、闇は線画だけでは表現することは難しい。スヌーピーとチャーリ・ブラウンの「ピーナツ」のような、線画で描かれる4コマ漫画の時代になってから、新聞漫画は「昼」の世界になったと思いますよ。夢オチもなくなりましたよね。
鍛治さん 今や夢オチは漫画や文学では禁じ手の一つですよね。
柴田さん 文学は型通りに演じるのが良いと思われる時代と、外すほうが良いと思われる時代があるとすると、今はどう定形から外れるかを重視する時代ですよね。そうなると「胡蝶の夢」のような定形からどう外れるかが大事になっているので、確かに夢オチは禁じ手みたいになっているかもしれませんね。
鍛治さん 「眠り文学50選」では最初に核になる作品があったのでしょうか。
柴田さん 核というよりは出発点。村上春樹さんの「ねむり」と、あとはスティーヴ・エリクソン(1950年~)かチャールズ・ブロックデン・ブラウン(1771~1810年)、アメリカ文学の中で「眠り」が印象的な作品が出発点にありました。それらを考えると、眠りそのものではなく、どうしても周辺的な話にならざるを得ないことも見えてきた。村上さんの作品は「眠れない」話ですし、ブロックデン・ブラウンやエリクソンは「目が覚める」と、そこがどこなのか分からない、という話の系譜なんです。
鍛治さん 後者は眠りが「仕掛け」になっている作品……。
柴田さん それは一種のギミックにすぎないように思えるのだけど、たぶんそうではなくて、アメリカ文学の根底にある「自分が何者か分からない」テーマにつながっていると思うんですよ。まあ、どんな文学も芝居も少なからずそのテーマが底流していますが、アメリカ文学ではそれが特に強いわけ。そして、アイデンティティの不安みたいなものを抱えている作家ほど、目が覚めたら知らないところにいる、ここはどこ? 私は誰? という作品が多い。
──チャールズ・ブロックデン・ブラウンの小説は確かに。
柴田さん ブロックデン・ブラウンは18世紀末から19世紀始めを代表するアメリカ人作家ですが、当時は彼とジェイムズ・フェニモア・クーパー(1789~1851年)という大作家がいて、クーパーはもっぱら昼の世界を描いていた。白人アメリカ人の西部開拓の話など、建設的な世界を書くクーパーのような作家は「目が覚めたらどこ?」みたいな話ではなく、白昼の世界で、描かれる人物像には揺るぎがない。それに対してブロックデン・ブラウンは、夢遊病者や精神を病んでいる人間を書くことが多く、出てくる状況も夜が多い。こういう雰囲気を持つ作品と、村上さんの「ねむり」のように「不眠」をテーマにした作品を探すことが50選の出発点でした。アメリカでは眠り文学をまとめた書籍は2冊が有名で、一つはタイトルがそのまま「Sleep」、もうひとつは「眠れない」作品のアンソロジー「The Literary Insomniac」。不眠症は小説のテーマになるんですよね。でも眠りそのものを扱う作品はやはり難しい。それがこの2冊のアンソロジーのつくられ方にも表れていました。
私はまるで眠りから覚めたように、はっとした。眠りこんだとき、私はどんな状態にあったか? 現在とはちがう状態にいた。そのとき、私は明るい部屋におり、羽根ぶとんの寝台に横たわっていた。いま私は粗い岩のうえに坐り、漆黒の闇に包まれている。あのとき、私は完全に健康だった。いま私は全身傷だらけで、節々はずきすきと痛む、いかなる土牢ないし穴ぐらに私はいるのか? 誰の命令で私はここに連れてこられたのか?
(チャールズ・ブロックデン・ブラウン『エドガー・ハントリー』。国書刊行会、八木敏雄訳)
鍛治さん 柴田さんは眠りと文学について、国や時代によって違いを感じることはありますか。
柴田さん 小説でも詩でも、外の世界に目が向く人と、自分の内面に向く人がいて、前者は昼の覚醒した社会が書かれることが多く、その反対に、執筆する部屋中にコルクを貼り、子宮のような空間をつくったプルーストのように、内面に沈み込んでいく作家は、闇や夢、眠り系に流れています。ジェイムズ・フェニモア・クーパーとブロックデン・ブラウンの典型的な二つの流れは、近代社会であれば国や時代を選ばず、どこにでもあるものだと思いますよ。
鍛治さん 日本の夏目漱石は後者ですね。
柴田さん 「夢十夜」とか、地下の世界をさまよう「坑夫」のような作品が魅力的ですから後者でしょうね。
漱石の登場人物はやたらとよく眠る。しかも、彼らは昼間から惰眠をむさぼるのだ。『吾輩は猫である』の「吾輩」は、主人がいるも昼寝をしていることを告発するし、遺作となった『明暗』でも、津田は入院先の療養所で昼間から寝てばかりいる。しかし右に並べた三部作(注:「三四郎」「それから」「門」)の書き出しのように、漱石の作品においては登場人物のうたた寝が物語の貴店になることが多い。というより、登場人物の眠りが遮られることで、にわかに物語が始動するのだ。
(大和田俊之、『Monkey Business』vol.2「眠り文学50選」より)
──漱石を読むと登場人物はよくお昼寝してます。
柴田さん まあ、高等遊民を書いてた人ですから。今では高等遊民なんてありえないですけどね。文学を読むと「人は今も昔も変わっていない」と思うこともありますが、現実には、例えばこの数年でビジネスマンの平均睡眠時間は約1時間減っているんですよね。これは以前、鍜治さんとお話しした時にも話題になりましたが、10年程度で1時間減るってスゴイことですよ。人はいつも「今は激動の時代」とか「変化の時代」と言いたがるけれど、眠りについてはまさに激動の時代です。まあ、それはともかく、お昼寝はいいですよねえ。
鍛治さん あははははは。実感がこもってます。
柴田さん ウチの奥さんから新聞に載った「効率的な昼寝」を教えてもらったんですが、15分昼寝はいいですよ。ベッドに横になってタイマーをセットして15分。目覚めるとスッキリしているし、起きてすぐに仕事に戻ることができる。
鍛治さん 15分よりさらに長く眠ると深部体温がどんどん下がって、眠りが深くなり、起きづらくなるんですよ。15分くらいの睡眠は根を詰めた仕事中の休息には理想的です。
柴田さん そうなんですよね。1時間寝てしまうともうダメです。すぐに仕事には戻れない。