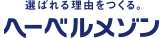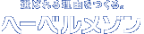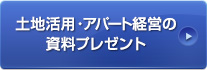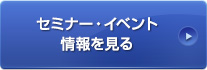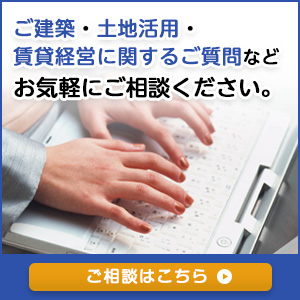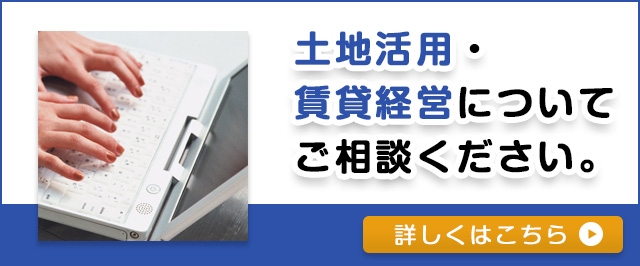土地活用の基礎知識:土地の売却編
不動産の運用を考えた時、選択肢として「現状維持」「活用」「売却」の3つが考えられます
ここでは土地の売却で重要な要素となる土地の価格と、売却した場合のメリット・デメリットなどを説明していきます
- ・土地の価格はどう決まるのか?
- ・土地の4つの価格と特徴
- ・実勢価格と4つの地価の関係
- ・土地売却のメリットとデメリット
- ・土地売却の税金のシミュレーション
- ・事業用資産の買換え特例について
土地の価格はどう決まるのか?
土地を実際に売買する場合の価格(実勢価格)を決める最も一般的な方法が「取引事例比較法」です。
多くの成約事例を基に、相場を見ながら決める方法です。この方法であれば、周辺の土地取引の事例などと比較して妥当な査定価格を導き出すことができます。
条件が優れていれば査定価格はプラスに、劣っていればマイナスに変動させることで調整します。事例と査定対象地の条件や情報を詳しくつき合わせれば、それだけ正確な査定価格を算出できます。その条件のことを査定項目と言います。
例えば接する道路の幅員や土地の形状、また接道部の間口、隣接地の利用状況など、基本的に土地自体の基礎情報以外の情報が重要な査定項目となります。
土地の4つの価格と特徴
土地の価格には、実勢価格とは別に、その目安となる「公示地価」、それを補完する「基準地価」があります。
それ以外に相続税・贈与税を算出する基準となる「路線価」、固定資産税等を算出する基準となる「固定資産税評価額」の4つがあります。
■地価の種類
| 種 類 | 実施機関 | 評価時点 | 公表時期 | 目 的 |
|---|---|---|---|---|
| 公示地価 | 国土交通省 | 1月1日 | 3月下旬 | 土地取引価額の目安、他の地価のベース |
| 路線価 | 国税庁 | 1月1日 | 7月1日 | 相続税、贈与税等を算出する基準の価額 |
| 基準地価 | 都道府県 | 7月1日 | 9月下旬 | 公示地価を補完、土地取引価額の目安 |
| 固定資産税評価額 | 市町村(東京23区は東京都) | 基準年度の前年の 1月1日(3年に一度) |
4月1日 | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税等を算出する基準の価額 |
※表は左右にスクロールします。
実勢価格と4つの地価の関係
公示地価、基準地価は、調査時点の周辺の土地条件や公表のタイムラグがあるので、実勢価格とは一致しません。
地価が上昇している時は、実勢価格は公示地価を上回り、下落傾向にある時は公示地価を下回る傾向にあります。
また、路線価は公示地価と同じ1月1日の評価で、公示地価の80%を目安に設定されています。固定資産税評価額は、公示地価の70%を目安に設定され、3年に一度の評価替えが行われます。
■地価の比較
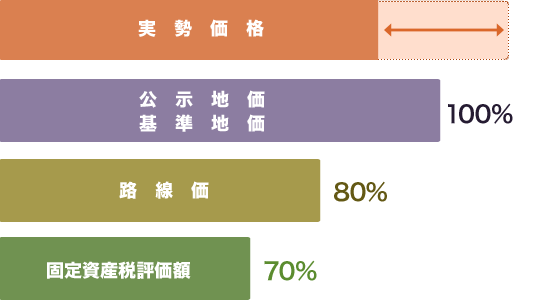
土地売却のメリットとデメリット
土地を売却するとまとまった資金が得られますので、納税資金の確保や資産の組み替えができるなどのメリットがあります。
しかし、土地を手放してしまうことになるので、土地を活用した際に得られる収入と比較検討することをお勧めします。
土地売却のメリットとデメリットを表にまとめましたので、参考にしてください。
■土地売却のメリットとデメリット
- メリット
- 納税資金の確保ができる
- 現金にすることで遺産分割しやすくなる
- 資産の組み替え(他の金融商品や不動産へ)がしやすくなる
- 固定資産税負担の軽減ができる
- デメリット
- 土地活用による定期的な収入を得る機会の損失
- 譲渡税、譲渡費用がかかる
- 不動産という固有の承継資産がなくなる
土地売却の税金のシミュレーション
土地を売却すると譲渡益に対して譲渡税がかかります。では、土地を売却した場合、どのくらい譲渡税がかかるのかをシミュレーションしてみます。
(特例を受けない一般の譲渡とします)
(1)「譲渡所得金額」を求める
まずは「譲渡所得金額」を求めます。計算方法は以下の通りです。
「売却金額」-「取得費」-「必要経費」=「譲渡所得金額」
※「取得費」が相続などで分からない場合は「売却金額×5%」になります。
※「必要経費」は収入印紙代、仲介手数料、アパートなどが建っている場合は売却する時に借家人に支払った立ち退き料、建物を解体して売却する時の解体費用などです。
(2)「譲渡所得税」を計算する
「譲渡所得金額」に対し、税率を掛けて譲渡所得税を計算します。
ただし、土地を取得してからの所有期間(※)によって、税率が変わります。
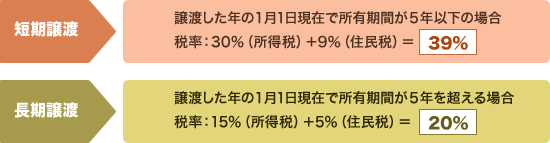
- 短期譲渡
- 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合
税率:30%(所得税)+9%(住民税)=39%
- 長期譲渡
- 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合
税率:15%(所得税)+5%(住民税)=20%
注)上記税率には、「復興特別所得税」は含まれていません。
仮に土地の売却金額が4,000万円の場合、取得費を200万円(売却金額×5%)、必要経費を180万円とそれぞれ仮定して税額を計算してみます。
<短期譲渡の場合>
{ 4,000万円-200万円(取得費)-180万円(必要経費)}×税率(39%)
1,412万円(所得税+住民税)
<長期譲渡の場合>
{4,000万円-200万円(取得費)-180万円(必要経費)}×税率(20%)
724万円(所得税+住民税)
※所有期間:相続や贈与により取得したものは、原則として被相続人や贈与者の取得した日から計算。
※上記税率には、「復興特別所得税」は含まれていません。
事業用資産の買換え特例について
アパートや工場などの事業用資産を、より有利な事業用資産に買い換える場合には譲渡税の軽減措置があります。
これを「特定事業用資産の買換えの特例」と言います。これは所有期間が10年を超える土地・建物(貸地・駐車場等も可)を譲渡して買い換える場合が該当します。
先に説明した通り、「長期譲渡」の場合は通常20%の譲渡税(所得税+住民税)が課税されます。
ところが、10年以上所有の事業用資産を売却して買い換えた場合には、譲渡所得金額の80%(地方から都市部等への買換えの場合は70%または75%)が繰り延べられます。
つまり譲渡所得金額の20%に対して20%の譲渡税(所得税+住民税)が課税されることになり、実質的には4%の課税で済みます。
ただし、適用期限は2026年3月31日までです。また、買い換える資産の事業用の土地に関しては面積が300㎡以上等の条件があります。
土地が300㎡に満たない場合は、建物を買換え資産として適用できます。ただし、その場合は買換えて取得した建物の減価償却費が小さくなってしまい、特例を使わないほうが有利な場合もありますので注意が必要です。