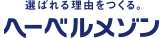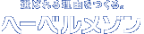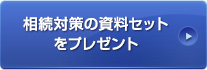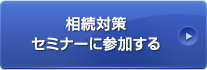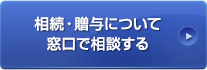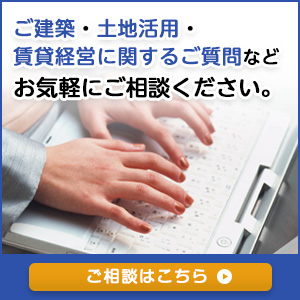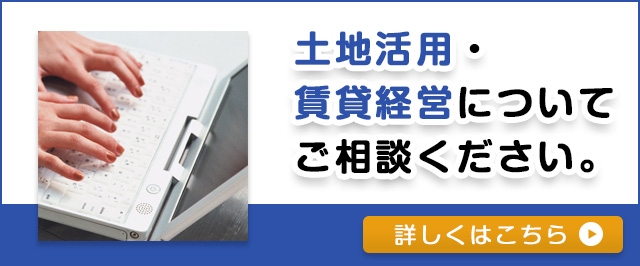相続・贈与の基礎知識:贈与の基礎知識
どんな時に贈与税が発生するのか、また贈与税の税率など、贈与に関する基礎知識を解説します。
- ・贈与税とは? どのくらいかかるのか?
- ・贈与税の課税制度
- ・贈与税の特例
- ・夫婦間の贈与について
- ・贈与課税が対象外になるケース
贈与税とは? どのくらいかかるのか?
贈与税とは、個人が自分の財産を個人に無償で譲渡した場合、財産を受け取った方にかかる税金です。
贈与税の基礎控除は110万円です。従って、毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。110万円を超えた分について課税されます。納税期日は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告し納税します。
税率は下記の速算表にある通り累進課税になっています。
■贈与税の計算
贈与税=(贈与財産価格-基礎控除110万円)×税率-控除額
■贈与税の速算表
・18歳以上の者が直系尊属(父母等)から贈与を受けた場合の贈与税の税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下の金額 | 10% | - |
| 400万円以下の金額 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下の金額 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下の金額 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下の金額 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下の金額 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下の金額 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超の金額 | 55% | 640万円 |
・通常の贈与(上記以外)の贈与税の税率
| 基礎控除・配偶者控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下の金額 | 10% | - |
| 300万円以下の金額 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下の金額 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下の金額 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下の金額 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下の金額 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下の金額 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超の金額 | 55% | 400万円 |
●土地・家屋の評価方法
贈与税の土地・家屋の評価は、相続税評価と同じです。売買価格ではなく、税計算上の土地や家屋の評価方法が決められています。この評価方法に従って、相続税や贈与税の納税額が決定されます。
- 土地:路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。
- 家屋:固定資産税評価額で評価。
詳しくは、「財産評価の引き下げ編」をご覧ください。
贈与税の課税制度
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
■暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されることです。従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし、贈与税の申告は不要です。
間違いやすいのは、もらう側の合計が110万円ということです。二人から110万円ずつ贈与を受けた場合、合計の220万円のうち110万円には贈与税がかかります。
また特に注意したいのが名義預金です。贈与者が管理している子どもや孫名義の銀行口座に、本人に知らせずに資産を移しているケースです。確実に受取人に資産を譲渡し、受取人がその資産を自由にできる状態にないと認められません。
暦年贈与の注意点
- 通帳・印鑑は必ず受け取った本人が管理する
- 贈与を受けた資産は受取人が自由に使える状態になっている
- その都度、契約書を作成し、事実を明確にする
- 生前贈与加算は相続開始前7年以内なので、早めに計画する
(2024年1月1日以降の贈与から適用され、段階的に生前贈与加算の期間が延びます)
■相続時精算課税
相続時精算課税制度とは、贈与時に本来かかるはずの贈与税を先送りし、相続時にあらためて相続税として精算するという制度で、相続税と贈与税が一体化されたものです。
2,500万円の非課税枠があるので、一度に大きな財産を贈与することができます。2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税がかかります。
※2024年1月1日より年間110万円の基礎控除が追加され、その分は生前贈与加算の対象になりません。
60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の推定相続人である子または孫への贈与が対象で、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。贈与者1人につき、限度額に達するまで何回でも利用することができ、例えば、祖父から2,500万円、祖母から2,500万円の贈与も可能になります。
また、「相続時精算課税」を選択すると、それ以降「暦年課税」に変更できませんので注意が必要です。
相続時精算課税の具体例は「財産の移転編-生前贈与を活用する」をご覧ください。
・暦年贈与と相続時精算課税制度の比較
| 暦年贈与 | 相続時精算 課税制度 |
|
|---|---|---|
| 税率 | 10%(200万円以下)~55% (直系尊属の場合4500万円超) |
一律20% |
| 基礎控除額 | 110万円 | 110万円 (2024年1月1日より) |
| 非課税枠 | なし (住宅取得資金の場合は Q住宅取得資金の贈与を受けた場合はどうなるか? を参照のこと) |
贈与者1人につき2,500万円 (住宅取得資金贈与の非課税制度と併用可能) |
| 手続き | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税申告 | 受贈者が当制度を選択し、所轄税務署長に届け出をおこなう。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書とあわせて届け出をする |
| 適用対象者 | 定めなし | 贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は18歳以上の子または孫(住宅取得資金の場合は、親の年齢制限なし) |
| 生前贈与加算 | 相続開始前7年以内の贈与は基礎控除も含めて相続税の対象。相続開始前4年から7年以内の贈与については、4年間の合計額から100万円控除後の金額が加算される(2024年1月1日より) | 相続時に「贈与財産」と「相続財産」を合算。年間110万円の基礎控除は生前贈与加算の対象にならない |
※表は左右にスクロールします。
贈与税の特例
親世代の資産を子世代に贈与することは、経済効果も高いとして、贈与税には様々な非課税特例が打ち出されています。
●住宅取得資金の贈与税の非課税特例
直系尊属(父母・祖父母等)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の金額について非課税となる特例です。
一般住宅で500万円、省エネ・耐震・バリアフリー住宅で1,000万円などがあります。非課税額や期限に関しては、毎年税制改正で見直しがあります。
※この特例は、2026年12月31日までの贈与が対象です。詳しくは「財産の移転編-生前贈与を活用する」をご覧ください。
●教育資金一括贈与制度
直系尊属(父母・祖父母等)から、孫(または子等)に教育資金を1,500万円まで非課税で一括贈与できる制度です。その資金は信託銀行などの金融機関に受取人名義の口座を設け利用することになります。受贈者は30歳未満であり、30歳時に残った金額は贈与税が課税されます。
また教育資金管理契約中に贈与者が死亡した場合には、管理残高を受贈者が相続したものとして相続税が課税されます。
教育資金は、その都度でも非課税なのですが、一度に贈与した方が都合がよいと人気です。
※この特例は、2026年3月31日までの贈与が対象
●結婚・子育て資金一括贈与制度
教育資金同様、直系尊属(父母・祖父母等)から、孫(または子等)に結婚・子育て資金を1,000万円まで(結婚式資金は300万円まで)が非課税で一括贈与できる制度です。受贈者は18歳以上50歳未満です。
※この特例は2027年3月31日までの贈与が対象
夫婦間の贈与について
贈与税は、個人から財産を譲渡されたときに課税対象となります。たとえ夫婦間でも課税対象となります。
特に住宅を取得した際に、所有権と購入資金の負担割合が異なると、贈与税の対象となることもあるので、注意しなくてはなりません。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が3,000万円の住宅ローン(資金負担)を組んだものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1としたとします。この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1となり、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。
しかし、購入のための資金は負担していないので、差額の1,500万円については夫から妻へ贈与があったとみなされるのです。資金の負担割合に応じて夫の所有権登記がされていれば問題は生じません。
また、共働きの夫婦が連帯債務型で住宅ローンを組んだ場合、予定する返済割合に応じた共有名義にすればよいのですが、100%夫名義にした場合は、贈与税がかかる場合があります。
ローン返済は共働きの収入から行うとした場合でも、返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされます。その年の返済額に妻の所得が夫婦の所得の合計に占める割合を乗じて計算した金額がその年の贈与額になりますので、この点も注意が必要です。
■居住用不動産の贈与の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合は、暦年課税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除ができます。
特例を受ける主な要件は、以下の3つです。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産や居住用不動産の購入資金であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた方が住んでいて、引き続き住む見込みがあること
居住用不動産は、国内の家屋またはその敷地です。敷地には借地権も含まれます。居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。従って、居住用家屋または敷地のみの贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。
ただし、配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんので注意が必要です。
贈与課税が対象外になるケース
以下のものは、贈与税の課税対象外になっています。中には社会通念上あたり前のものもありますが、チェックしておきましょう。なお、一定の条件を満たすことが必要な場合があります。
- 法人からの贈与により取得した財産(※)
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費として提供された財産
- 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどの金品
- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産
- 奨学金の支給を目的とする特定公益信託
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金
- 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
- 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産。
(この場合は、贈与税ではなく、相続税がかかりますが、相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人から贈与によって取得した居住用不動産については、過去に配偶者控除を受けていないときは、贈与税の配偶者控除があるものとして、相続税から控除されます)
※法人・個人間の贈与は、組み合わせにより課税される種別が異なります。下表をご参照ください。
| 組み合わせ | 課 税 | |
|---|---|---|
| 贈与者 | 受贈者 | |
| 個人→個人 | なし | 贈与税 |
| 個人→法人 | みなし譲渡所得税 | 法人税 |
| 法人→個人 | 法人税 | 所得税 |
| 法人→法人 | 法人税 | 法人税 |