家のローンはいくらにするといい?年収別の借入可能額の目安や利用のポイントを解説

「家のローンはいくらにするといい?」
「自分の年収でどれくらいの金額が借りられる?」
住宅ローンの利用を検討中の方で、上記のようにお悩みではありませんか。
住宅ローンを利用することで、資金がなくても家づくりができるようになります。事前に自分の借入可能額を知っておけば、今後の返済の見通しがつき、資金計画が立てやすくなるでしょう。
本記事では、住宅ローンの年収別借入可能額の目安や利用のポイントを解説します。ローンを利用する際の頭金の金額についても解説するので、住宅ローンの利用を検討中の方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 住宅ローンの借入可能額の目安
- 住宅ローンを利用する際の頭金の決め方
- 住宅ローンを利用する際のポイント
具体的な資金計画の立て方を知りたい方は、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイトを活用してみてはいかがでしょう。
ヘーベルハウスの「THINK HAUS」では、資金計画のコツや家の資産価値の基礎知識などの情報を公開しています。家づくりにかかる費用や資産価値が高い家の条件がわかるため、これからの資金計画の参考になるでしょう。
THINK HAUSの会員登録は、以下のリンクから行えます。
もくじ
住宅ローンとは

住宅ローンとは、契約者本人や家族が居住する住宅の購入資金を融資してもらえるサービスのことです。住宅を購入したくても資金が足りない、またはない場合に選択される方法で、利用すれば年収の数倍におよぶ住宅を購入できます。
住宅ローンには、大きく分けて以下の3つがあります。
| 民間ローン | 銀行や信用組合など民間金融機関が提供するローン |
| 公的ローン | 公的機関が提供するローン |
| 準公的ローン | 公的機関と民間金融機関が提携して提供するローン |
いずれのローンも融資の実行は、基本的に住宅の引き渡し日と同日に行われます。融資の実行後、住宅代金の決済を行うことで、住宅が引き渡される仕組みです。
ただし、利用には事前審査や本審査を受ける必要があります。
土地と建物を別々に購入する場合は、それぞれでローンを組む方法もあります。
家のローンの平均借入額

国土交通省が発表した令和5年の調査によると、家のローンの平均借入額は2,964万円です(土地あり新築注文住宅の場合)。購入代金の平均額は4,034万円であり、73.5%がローン、26.5%が自己資金でまかなわれていることがわかりました。
また、同調査は、注文住宅を取得した世帯において、住宅ローンを利用している人の割合は74.8%にのぼるとも報告しています。
これらの結果から、注文住宅を建築した人の7~8割がローンを利用し、購入代金の7割程度を借りているといえるでしょう。
しかし、上記はあくまでも平均的な数値であり、実際の返済では、借入総額に利息を上乗せした金額を支払う必要があります。また、ローンの借入可能額は年収によって異なるため、一概にどれくらいの金額が借りられるかとはいえません。
そのため、ローンの利用を検討する際は、まず自身や家族の年収からおおよその借入可能額を知ることが大切です。
※参照:国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」
【年収別】住宅ローンの借入可能額の目安

住宅ローンの借入可能額の目安を、以下の世帯年収別に解説します。
自分のおおまかなローンの借入可能額を知る際の参考にしてください。
なお、各年収の借入可能額を計算するにあたり、住宅金融支援機構のシミュレーションを活用しました。金利はフラット35の21~35年プランの最頻金利1.820%(固定)、返済期間は35年とします。
※年間の返済額は借入可能額÷35、月々の返済額は年間返済額÷12で計算
※参照:住宅金融支援機構「年収から借入可能額を計算」
1. 年収400万円
世帯年収400万円の場合、借入可能額は3,622万円です。年間の返済額は約103.5万円、月々の返済額は約8.6万円になる計算です。全国の平均借入額よりは多いものの、購入代金の平均額4,034万円を下回っています。
そのため、一部の代金は自己資金でまかなわなければならない可能性があります。外観や間取りをなるべくシンプルにするなど、費用を抑えるための工夫をする必要があるでしょう。
2. 年収600万円
世帯年収600万円の借入可能額は5,433万円です。年間の返済額は約155.2万円で、月約12.9万円の支払いが必要になります。
全国の平均借入額、購入代金の平均額よりも多いことから、比較的余裕のある家づくりができるでしょう。ただし、土地も新たに購入するとなると、住宅の購入代金が借入可能額をオーバーする可能性があります。
3. 年収800万円
世帯年収800万円の場合の借入可能額は7,244万円になります。年間の返済額は約206.9万円、月の返済額は約17.2万円です。
年収800万円以上では、借入可能額が全国の平均借入額、購入代金の平均額をともに大きく上回ります。金銭的に余裕が出るため、さまざまな要素を詰め込んだ家づくりができます。
4. 年収1,200万円
世帯年収1,200万円では、利用するローンにもよりますが、年収の8~9倍である9,000万円~1億円前後が借入可能な額の目安といわれています。
資金が9,000万円を超えてくると、趣味や娯楽の要素もふんだんに盛り込んだ高級住宅がつくれます。建材や設備などの外装・内装にもこだわった家づくりが可能です。
家のローンを利用する際に頭金はいくら払うといい?

注文住宅の建築を依頼する際に支払う頭金は、明確に金額が決まっていません。頭金の金額は基本的に買主が自由に決められますが、一般的には住宅の購入代金の1割程度を払うケースが多いです。
そもそも頭金とは、住宅会社と契約する際、建築代金の一部として事前に支払う金銭のことをいいます。住宅ローンを利用してマイホームを購入するケースでは、住宅代金の一部を頭金として支払い、残りを借入金でまかなうことが一般的です。
しかし、住宅ローンのなかには、住宅の購入代金の全額を借り入れられるものもあり、頭金は必ずしも必要なものではありません。頭金を用意するか、いくら払うかは、自分の年収や経済状況に応じて決めるとよいでしょう。
家のローンを利用する際のポイント

家のローンを利用する際のポイントは、以下の4つです。
住宅ローンは資金がなくても住宅を購入できる便利なサービスですが、使い方を間違えると、のちの返済で苦労するおそれがあります。
しっかりとポイントを押さえて、住宅ローンをうまく活用しましょう。
1. 実際に借りる金額は年収の8~9倍前後を目安にする
家のローンを利用する場合、実際の借入金額は年収の8~9倍前後を目安に設定することが理想です。
ローンを借入可能額ギリギリまで利用すると、急な出費や将来年収が下がったときに、返済金が家計を圧迫するおそれがあります。場合によっては返済が滞りかねません。
また、住宅購入後のメンテナンスコストやランニングコストを考えると、限度額までローンを利用することは現実的ではないでしょう。
そのため、ローンの借入金額を決める際は、将来のライフイベントや年収、ライフサイクルコストを考慮することが大切です。自分の年収の8~9倍を上限として、返せる金額を基準にゆとりのある資金計画を立てましょう。
2. 月々の返済額は無理なく返済できる金額に設定する
マイホーム購入後、安定した生活を送るためには、月々の返済額は無理なく返済できる金額にすることが大切です。
具体的な返済イメージがわかない場合は、現在住んでいる賃貸住宅の家賃を目安にするとよいでしょう。また、マイホームを建てるために貯蓄をしている場合は、その金額を家賃に上乗せした額をベースに考えてみてください。
無理なく返済できる月々の返済額を検討することで、適した借入額、返済年数がわかり、返済計画が立てやすくなります。
3. 金利は自分に合ったタイプを選ぶ
自分に合った金利タイプを選ぶことも、住宅ローンを利用するうえで重要なポイントです。
住宅ローンの金利には、主に変動金利、全期間固定金利、期間選択固定金利の3種類があります。それぞれの違いは以下の通りです。
| 変動金利 | 返済期間中に金利が変動し、一定期間ごとに金利が見直される |
| 全期間固定金利 | 金利確定後、完済まで金利が変わらない |
| 期間選択固定金利 | 変動金利と固定金利の両方の特徴をもった方式で、2年・3年・5年など、金利を固定する期間を選べる |
変動金利は、比較的金利は低いものの、一定期間で金利が変動するため返済計画が立てにくいデメリットがあります。全期間固定金利と期間選択固定金利は、返済計画が立てやすい一方で、金利が高めです。
このように、それぞれにメリット、デメリットがあり、どの金利タイプが合っているかは人によって異なります。現在の経済状況や将来の年収などを考慮したうえで選択しましょう。
4. 頭金の金額は生活資金や備えを考えて決める
頭金の金額は生活資金や備えを考えて決めましょう。
頭金は少しでも多く払うことで返済の負担を抑えられますが、貯蓄のすべてを頭金にすると、急な出費などに対応できなくなります。また、建物代以外に手続きや引っ越しの費用など、さまざまな費用がかかることも考えなければなりません。
そのため、頭金を払う場合は、万が一の病気や入院に備えた生活予備費や将来の生活に必要な費用を手元に残しておくことが大切です。
家づくりにかかる費用を詳しく知りたい方は、ぜひヘーベルハウスの「THINK HAUS」をご利用ください。
THINK HAUSでは、注文住宅の費用や土地の選び方など、マイホームづくりに役立つ情報を公開しています。家づくりの資金計画についても解説しているため、はじめての家づくりで資金計画を立てる際の参考になります。
自分に合った家のローン計画を立てて理想の家づくりを始めよう

家のローンの借入可能額は、世帯年収によって異なります。家づくりを始める前に、おおよその借入可能額を知ることで、自分の年収や希望に合った理想の家づくりができるでしょう。
ただし、将来年収が下がる可能性やのちのメンテナンス費用を考えると、借入可能額ギリギリまでローンを利用することは危険です。
また、近年は40~50年の超長期ローンも一般的になっています。月々の返済額を抑えたい場合は、超長期ローンを利用することも方法の一つです。
返済期間を長くすることで、団体信用生命保険に長く加入できたり、抑えた分の金額をNISAなどの投資に回したりできます。
借入可能額=適切な借入額ではないことを理解し、自分に合ったローン計画と資金計画を立てましょう。
ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」では、資金計画や家の資産価値に関する情報を掲載しています。資金計画の立て方や資産価値の高い家の条件などの情報を網羅的に解説しているため、はじめての家づくりに役立つでしょう。
登録は以下のリンクからできます。
家づくりお役立ちコンテンツ
- 注文住宅のメリット・デメリットとは?
建売住宅や分譲住宅とどう違う? - 注文住宅のローンを組むには?
手続きの流れを徹底解説! - 【坪数別】注文住宅の間取り例をご紹介!
シミュレーションは可能? - ZEH(ゼッチ)とは?
ZEHのしくみをご紹介! - 注文住宅の相場はいくら?
平均的な費用、建築費以外にかかる付帯
工事費や諸費用もふまえて資金計画を - 注文住宅がもたらす嬉しいメリットとは?
デメリットもおさえて
快適な家づくりを - 【実例①】実例とともにご紹介。
住む人を豊かにする
ヘーベルハウスの家づくり - 【実例も紹介】3階建て住宅を快適に過ごすための間取りとは?
知っておくべき魅力点&注意点 - 二世帯住宅がもたらすメリットとは?
快適に住むために知っておくべき
3つの間取りスタイル - 狭小住宅ならではの贅沢空間!
狭さを感じさせない
夢の間取りのコツとは? - 注文住宅の間取りは
どうやって決める?
家づくりで取り入れたい
人気の間取りアイデアを紹介 - 戸建て住宅とは
メリットとほかの住宅との違い
種類や家づくりにおけるポイントまで
分かりやすく解説! - 三階建ての家づくりを
柔軟に楽しくする
間取りアイデア集 - 二世帯住宅の間取りに悩んだときの
おすすめとは?
失敗事例に潜む注意点も詳しく解説 - 注目されつつある平屋の家。
平屋のメリット・デメリットを知って
理想的な暮らしを叶える - 建て替えするなら知っておきたい費用のこと
リフォームや住み替えと
迷ったときの判断ポイント - アウトドアリビングで充実した“おうち時間”を…!
アウトドアリビングのメリットや
後悔しないためのポイントをご紹介 - 注文住宅ができるまで
情報収集から完成までの
基本の流れを知って始める家づくり - 家づくりの流れ12ステップ!
何から始めるかや
期間をわかりやすく解説 - 家の構造6種類の特徴を解説!
5つの工法や選び方の
ポイントも紹介 - 家を建てる際の基礎知識を解説!
費用、流れ、依頼先など
注意点を紹介 - 家づくりの初心者向けガイド!
流れや費用の目安、後悔しないための
ポイントなどをすべて解説 - 家の外観は何で決まる?
デザインの種類や実例、
決め方のポイントを紹介 - 注文住宅で人気の間取り10選!
後悔しない決め方の
ポイントも紹介 - 家の内装を決める3つのポイントを解説!
おしゃれにする方法や事例も紹介 - 注文住宅を大阪に建てる費用はいくら?
人気エリアと土地代の相場も紹介 - 注文住宅の相場をエリア別・坪数別で紹介!
土地あり・なしでいくら変わるかも解説 - 注文住宅の平屋のメリット・デメリット!
相場や間取り事例を紹介 - 愛知で注文住宅を建てたい!
費用の相場や
年収いくらで建てられるかを解説 - 注文住宅を千葉県に建てる費用相場は?
依頼先の種類や
選び方も解説 - 群馬県で注文住宅を建てる費用相場は?
気候に合わせた住宅の特徴も紹介 - 注文住宅を埼玉県に建てる費用は?
人気エリアやローンの金額も紹介 - 注文住宅の坪単価とは?
相場や費用を比較する際の
注意点を解説 - 家のローンはいくらにするといい?
年収別の借入可能額の目安や利用の
ポイントを解説 - 注文住宅を東京都に建てる費用の相場は?
9つの人気のエリアと業者の
選び方も紹介 - 注文住宅の玄関のおしゃれな事例8選!
よくある失敗例や回避するための
ポイントも紹介 - 注文住宅で人気のキッチンの種類は?
7つのおしゃれな事例や決め方の
ポイントを紹介 - 注文住宅のリビングづくりで
重視すべき6つのポイント!
おしゃれにするための
コツや実例を紹介 - 注文住宅のおしゃれなガレージの実例を紹介!
メリット・デメリットも解説 - 注文住宅の見積もりをとりたい!
依頼する流れや注意点を解説 - 注文住宅の諸費用はいくら?
内訳ごとの相場や
抑えるための方法を解説 - 注文住宅は相談先選びが重要!
相談内容や事前に準備することを
紹介 - 注文住宅の窓の種類とは?
選び方のポイントや
おしゃれな実例も紹介


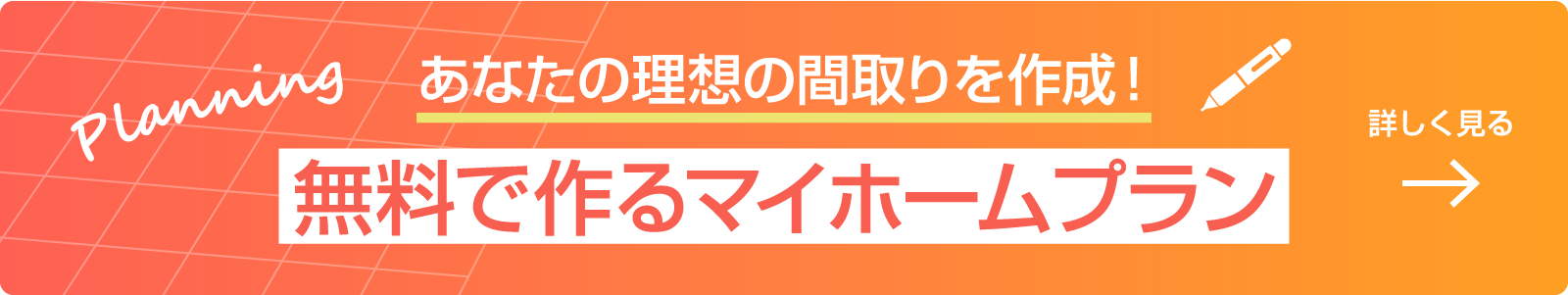
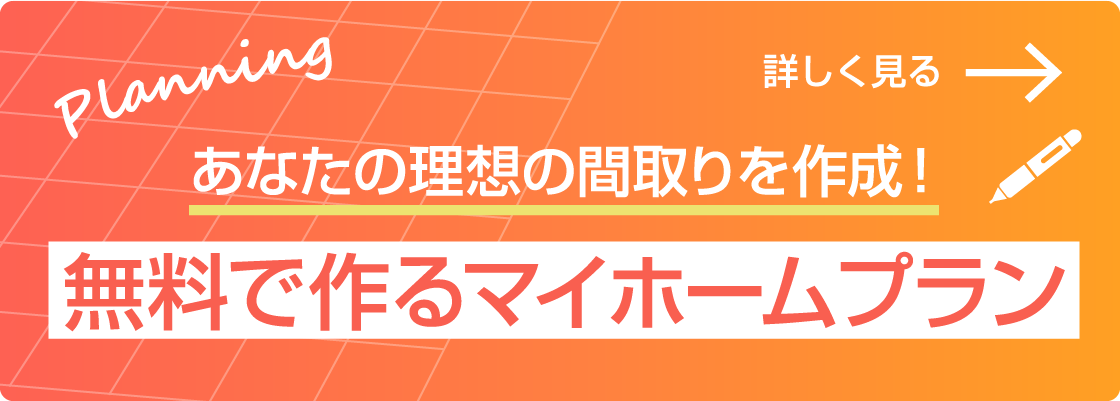
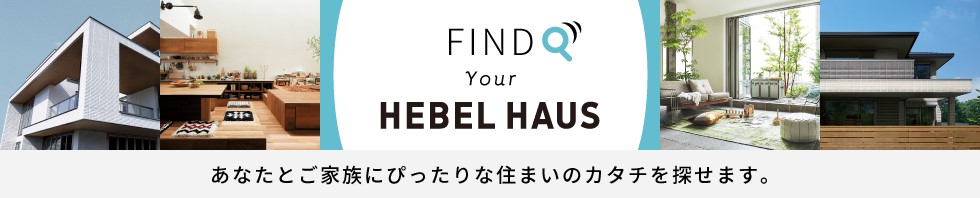





専門家コメント
頭金を払うことでローンの借入額が減り、返済の負担を抑えられるため、頭金はできるだけ多く用意したいと考える人も多いでしょう。しかし、頭金無しで早めに家を購入したほうが、費用負担を抑えられる場合もある点に注意が必要です。
たとえば頭金が貯まるまで賃貸に住む場合、家賃によっては頭金無しで家を購入したほうが、最終的に費用が安く済むことがあります。また、頭金を貯めている間に金利が上がってしまう可能性もあるでしょう。
頭金無しで購入する場合には、繰り上げ返済をして返済期間を短縮することで、最終的な返済金額を抑えられます。