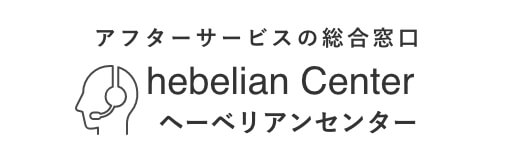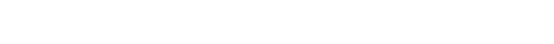基本的な考え方
私たちの事業は、お客様をはじめとした多様なステークホルダーとの関わりの上で成り立っています。企業の存続には社会的な意義のある存在として認知されることが必要であり、そのためにはステークホルダーの皆様からの信頼を獲得することが重要です。私たちは、事業活動を通じて、また事業活動で得られた知見や技術を活かして、地域や社会の発展に貢献する取り組みでさまざまなステークホルダーの皆様との信頼関係を強化します。
施工人財の定着・育成
2024年度は、各エリアの住宅事業本部ごとに、工事店現場責任者などが協働し、施工人財の定着や育成に資する活動を企画・実施しました。例えば、住宅建設業界における市場の変化や生産性向上が求められる社会的な背景に対応し、業務効率を図りながら安全・品質・コンプライアンスなどをどのように確保するかについて工事担当と工事店現場責任者のディスカッションを行ったエリアや、クレーン配置計画や地縄計画などの工事計画力向上を目的とした研修を行ったエリア、施工者が品質や施工効率向上に向けた活動を発表する場を設け、好事例として展開したエリアもありました。また全国の工事店に対する統一した活動としては、工事店に対する安全衛生講習を実施し、2024年度は延べ1,449名が受講しました。
工事店・施工者との結束力の強化
2024年度は、2025年1月に第3回となる自然災害初期対応訓練を実施しました。2023年度に実施した災害を想定した近接エリア間での工事店に対する応援要請対応をシミュレーションに加え、応援要請の連絡手法に、工事店・施工者との既存コミュニケーションツールを活用することで、効率的に連携する取り組みを実施しました。
また各エリアの住宅事業本部ごとに、工事店と協働し、工事店・施工者との結束力強化に向けた活動を企画・実施しました。例えば施工現場の公開イベントを当社工事担当と工事店が協働して開催し、ヘーベルハウス・へーベルメゾンの魅力を伝える取り組みを行ったエリアがありました。イベントには関係者のご家族も来場し、当社との親睦を深めることで、ロイヤリティの向上に繋がりました。
凛とした現場づくり
2016年以降、HEBEL HAUSの施工現場では「凛とした現場づくり」をスローガンに取り組みを進めています。「凛」という言葉にはピシッと隙がない、「ひきしまった」態度・状態の意味があります。事故が生じる現場には、どこかゆるみがあり、不注意・不安全が入り込む「すき」が現場に生じていると考え、緊張感のある「凛とした現場」を目指し、活動を進めています。
「凛とした現場づくり」の3つのキーワード
-
1.整然
整理整頓している、安全な通路の確保、ガードフェンスなどが真っ直ぐ設置されている
-
2.気遣い
ご高齢者・ご近隣さらに仲間への安全配慮
清潔な環境の維持(音・汚れを出さない努力、仮設物の見栄え) -
3.マナー
積極的な挨拶、清潔な身だしなみを心掛ける
2024年度はより隙のない工事現場や工程管理を目指し、現場の細部や工事中の敷地内管理にも目を向け、「凛とした現場づくりを工事完了まで維持」をテーマに活動しました。特に「安全通路の確保」と「外部資材の整理整頓」の2項目に重点的に取り組みました。本社として全エリアの監査を行い、結果を各工事課および工事店へフィードバックし、改善につなげています。また改善指示だけでなく、「安全通路」や「外部資材の整理整頓」の好事例を全エリアに展開しました。この活動により、工事店から「工事店毎の工夫が分かり意識の向上につながる」「取り組みが認められ励みになる」「現場について、お客様やご近隣様より高評価をいただいた」など前向きな報告があり、現場の品質向上にもつながっています。今後も「凛とした現場づくり」活動を継続し、安全で快適な働きやすい環境を持続していきます。
良かった事例



豪州事業会社に拡がる現場美化活動
オーストラリアの事業会社では、日本の「凛とした現場」で学んだ「お客様へのリスペクト」をテーマにClean site(現場美化)活動を継続して取り組んでいます。工事車両侵入経路に砕石敷きを徹底することによる、土・泥の道路への流出防止や、よりきれいなアプローチを構成するためにゴムマット利用をトライアルするなど、新たなClean site活動にも積極的に取り組んでいます。
加えて、産廃量の現状を把握するため外部産廃業者と連携を図り、種類別に分けてkg単位で計測する活動も開始しました。この活動は訪日時に見学した資源循環センターを参考にしたものであり、現場のゴミ箱に混廃状態で廃棄され、大まかな計測しかできていなかったこれまでの状況に対し、今後の産廃分析手段の一つになりえる活動となります。今後も、自社だけでなく外部業者とも協力しながら豪州建設現場をより良いものに変えていきます。

「BORIKI 絵本リユースプロジェクト」
「BORIKI絵本リユースプロジェクト」は、子育て世代をターゲットに展開する「子育て共感賃貸住宅『ヘーベルメゾンBORIKI』」の入居者様へ、社員の自宅に眠っていた絵本を「BORIKIえほん箱」と一緒にお届けする取り組みです。使われなくなった資源を有効活用するとともに、子どもたちの学びや絵本を通じた交流の機会を創出する効果も得られます。
本プロジェクトは2023年10月から開始し、2024年7月には有志のBORIKI入居者様と社員サポーターが、交流しながら仕分け作業などを行いました。そして、2024年9月に運用が開始され、入居者様にリユース絵本が届けられました。リユース活動は、入居者様と社員が直接対話できる機会となり、入居者様に旭化成ホームズグループについて知っていただく場にもなりました。今後も本プロジェクトを通して、「地域」での子育て応援を展開していきます。


保護犬保護猫 譲渡会
HEBEL HAUSは「ペットも家族の一員」という考えのもと、ペットと人が安心して暮らせる社会の実現を目指しています。その一環として、「HEBEL HAUS」と「sippo」(朝日新聞社が運営するペット情報メディア)共催で、「保護犬保護猫譲渡会」を開催しています。この譲渡会は、保護団体と協力してペットの保護・譲渡活動を支援することにより保護活動そのものを広く周知すること、またペットと新しい飼い主との出会いを通じていのちを守ることを目的として、2024年から実施しています。この活動は多くの方より共感の声をいただき、2025年2月に開催した譲渡会では、227名(内34名がへーべリアン)の皆様にご参加いただきました。私たちは引き続き、ペットと人がより豊かに暮らすことができるよう、ペット共生社会の実現に向けて取り組みを続けてまいります。

大阪・関西万博 ブロンズパートナーとして協賛
旭化成ホームズグループはVision For 2030「For Society」で社会課題に真正面から取り組む「環境貢献のリーディングカンパニー」を目指しています。この取り組みの一環として、2024年度に大阪・関西万博(以下、万博)のシグネチャーパビリオン「null²」にブロンズパートナーとして協賛を決定し、万博のパビリオン制作に参画しています。万博のテーマである「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」は私たちのVision For 2030と非常に親和性が高く、旭化成ホームズグループが掲げるALL for LONGLIFEをさらに進化させるものと認識しています。
協賛する落合陽一氏プロデュースのシグネチャーパビリオン「null²」は、世界最先端のデジタル技術を駆使し、デジタル上に自分の分身を創り出す「デジタルヒューマン」をテーマに、リアルとデジタルが融合した世界を表現したパビリオンです。このデジタルヒューマンは、健常者・高齢者・障碍者の誰もが、時間や距離といった制約を超えて、個々人が多様性を維持しながらも快適に過ごし、自己実現できる社会やそのためのサービスの実現を目指すものです。
今後も、リアルとデジタルを融合させる世界最先端技術を活用し、あらゆる制約を超える幅広いサービスの展開やさまざまな顧客体験を実現することで、社会課題の解決に貢献できるよう活動を続けていきます。

「開成町ゼロカーボンシティ創成パートナー企業」協定を締結
旭化成ホームズ住宅事業神奈川本部では、防災、環境、子育てなど、当社の強みを生かしたテーマを軸に、行政との協業を通じて地域貢献を進めています。2024年6月には、開成町(神奈川県足柄上郡)と「開成町ゼロカーボンシティ創成パートナー企業」協定を締結しました。その一環として、2024年7月には厚木支店が主導し、開成町在住の小学3~6年生とその保護者を対象にした「地球にやさしいまちづくり講座~気候変動と防災のはなし~」を開催しました。本講座では、「長持ちする家」を実現するためのヘーベルハウスの3つの取り組み「災害に負けない家をつくる」「きちんと手入れをする」「次の人に引き継ぐ」を紹介しました。また、「永く住み続けられる街づくりには人と人とのつながりが大切」とのメッセージも子どもたちへ伝えることで、未来を担う世代の意識向上を図りました。
これらの活動は、地域社会に貢献するだけでなく、社員にとっても自社が提供する商品・サービスの社会的意義の大きさを実感し、仕事への誇りを深める機会となっています。他の地域でもこのようなイベントを展開し、さらなる地域連携と価値創出を目指します。

神保町オープン・オフィス・デイ
2024年8月2日、旭化成ホームズグループ従業員のご家族を対象とした職場見学会「神保町オープン・オフィス・デイ」を開催し、総勢99組271名が参加しました。本イベントは、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上を図るとともに、次世代を担う子供たちに体験や学びの場を提供することで、社会貢献につなげることを目的としています。当日は12種類の「体験学習ブース」や「社長訪問ツアー」を通じ、日頃より従業員を支えてくださるご家族に職場への理解と親しみを深めていただきました。参加者からは「家族の仕事を知れてよかった」、「次回もぜひ参加したい」といった声が多く寄せられました。今後は2年に1度の開催を目指し、ご家族とのつながりを大切にしながら、働きがいのある職場づくりに取り組んでまいります。